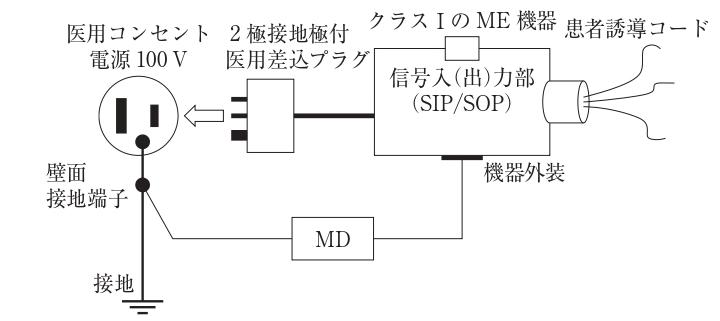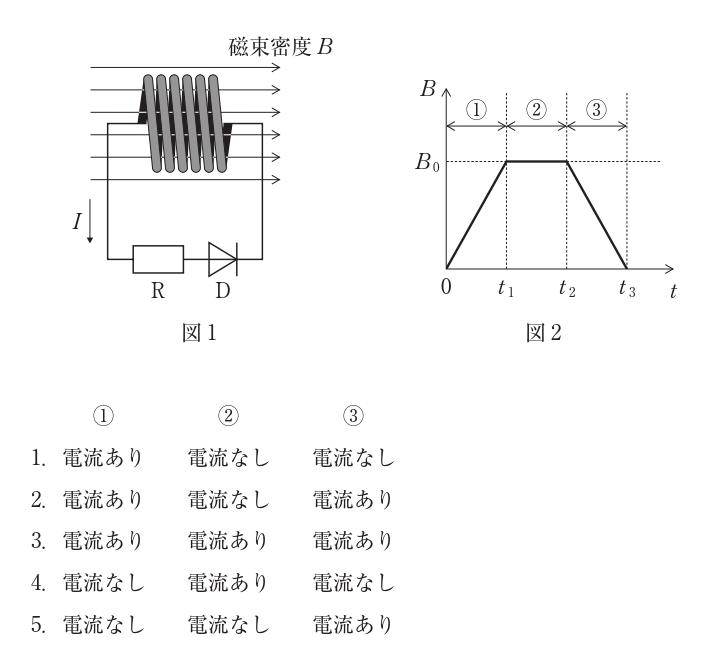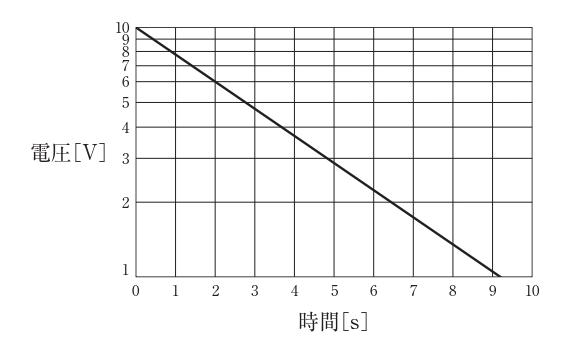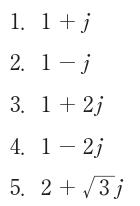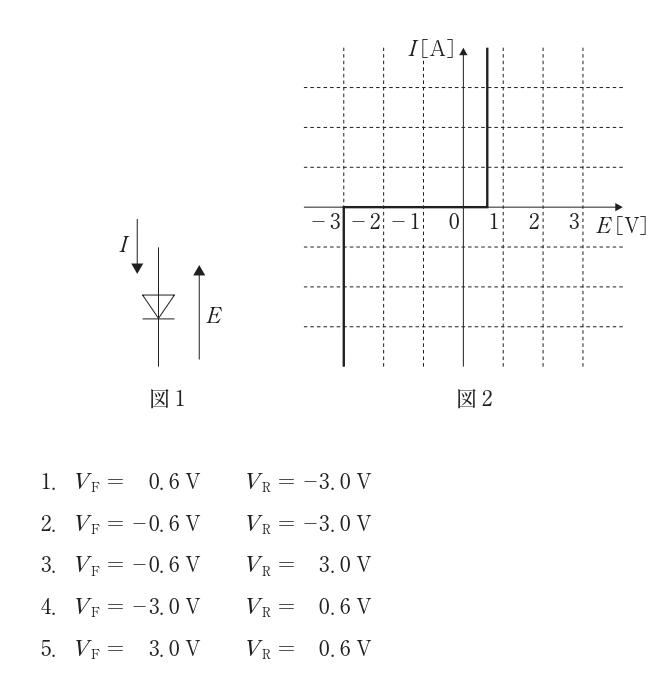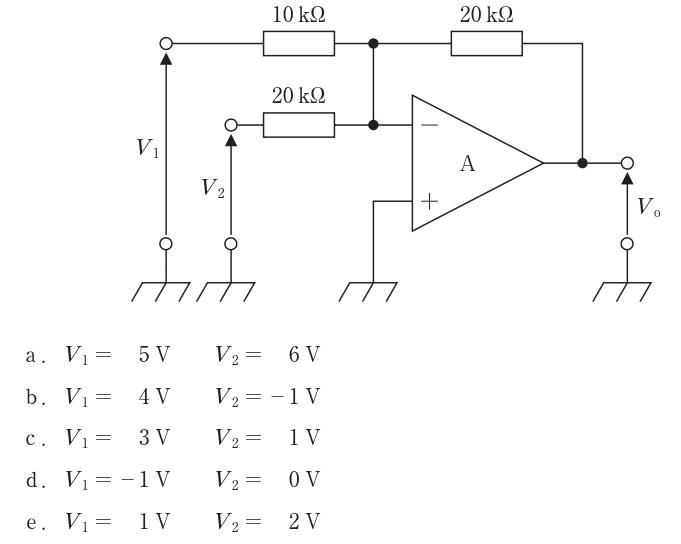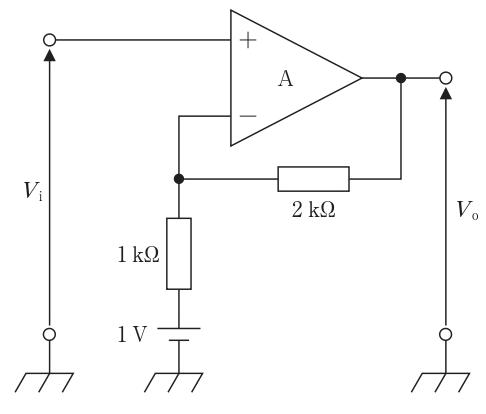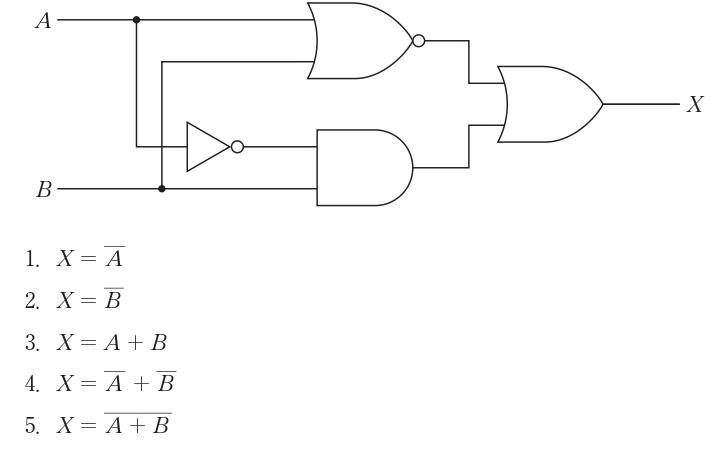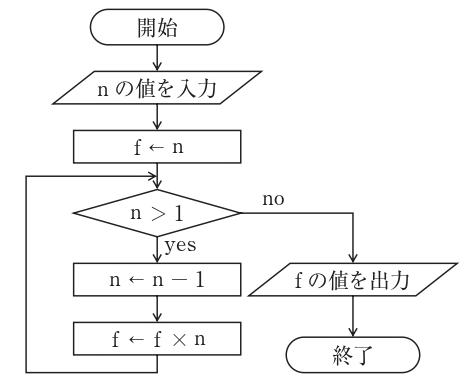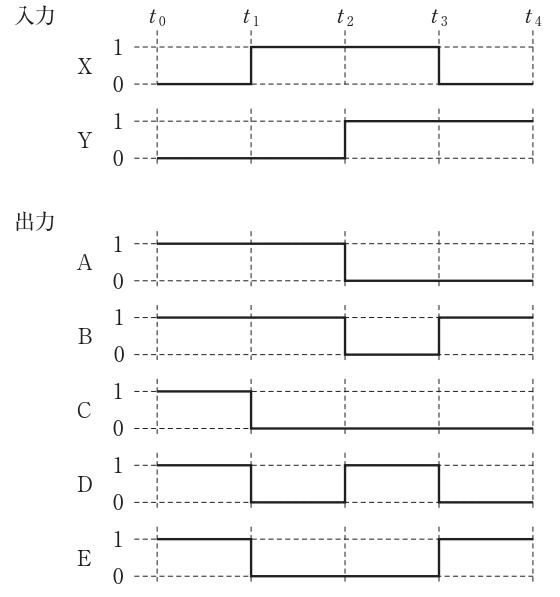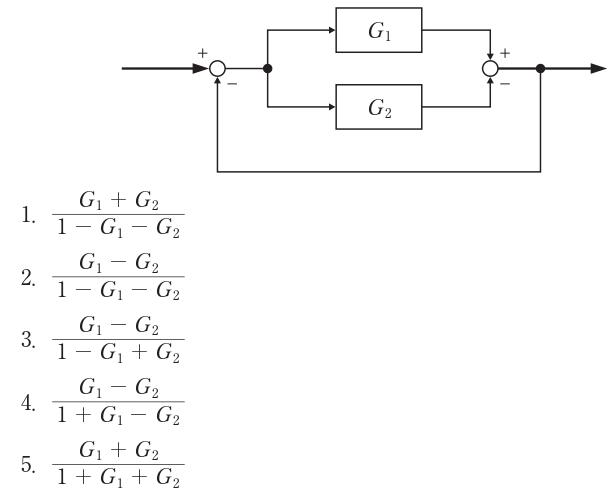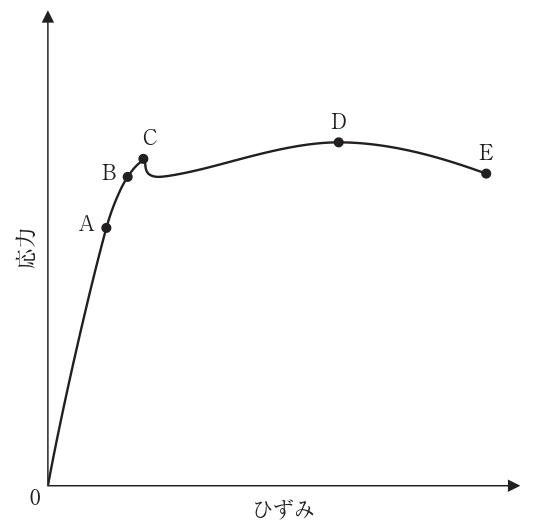第34回午後の過去問
国試第34回午後:第2問
疾病とその原因となる作業との組合せで誤っているのはどれか。
1:難 聴 騒音下での作業
2:眼精疲労 VDT 作業
3:減圧症 高圧線保守作業
4:じん肺 鉱山掘削作業
5:振動障害 削岩機作業
国試第34回午後:第3問
酵素について誤っているのはどれか。
1:触媒の一種である。
2:基質は酵素が作用する物質を示す。
3:体内での至適温度は 25℃付近である。
4:酵素ごとの至適 pH が存在する。
5:タンパク質で構成される。
国試第34回午後:第4問
炎症の 5 徴に含まれないのはどれか。
1:発 赤
2:発 熱
3:掻痒感
4:疼痛
5:機能障害
国試第34回午後:第17問
尿路結石の診断や治療適応の判断に用いられない画像検査はどれか。
1:腹部超音波検査
2:単純 X 線検査
3:点滴静注腎盂造影法
4:腹部 CT 検査
5:腎動脈造影法
国試第34回午後:第20問
表面麻酔を用いるのはどれか。
a:脱臼整復
b:気管支鏡検査
c:胃内視鏡検査
d:気管切開術
e:三叉神経ブロック
1. a b 2. a e 3. b c 4. c d 5. d e
国試第34回午後:第23問
医療安全について正しいのはどれか。
1:医療行為により患者に重篤な損害を与えた事例をインシデントという。
2:アクシデントが発生する背景には数多くのインシデントが隠れている。
3:患者がベッドから転落した場合、怪我がなければ報告しなくてよい。
4:再診であれば患者確認作業は省略してよい。
5:患者識別バンドを確認すればフルネームを名乗ってもらう必要はない。
国試第34回午後:第28問
オシロメトリック法による血圧測定で正しいのはどれか。
1:最低血圧は測定できない。
2:圧振動の周波数から算出する。
3:不整脈は計測誤差の原因とならない。
4:最高血圧以上では圧振動は検出されない。
5:平均血圧付近で圧振動の振幅が最大となる。
国試第34回午後:第29問
カプノメータについて正しいのはどれか。
a:サイドストリーム型では測定に時間的な遅れが生じる。
b:脱酸素化ヘモグロビンの吸光特性を利用する。
c:窒素ガス濃度は誤差の原因となる。
d:ゼロ点校正が不要である。
e:二酸化炭素ガスは 4.3 nm に光吸収のピークをもつ。
1. a b 2. a e 3. b c 4. c d 5. d e
国試第34回午後:第30問
医用サーモグラフについて正しいのはどれか。
a:赤外線を照射して体温を計測する。
b:光量子型検出器は赤外線検出器として用いられている。
c:ステファン・ボルツマンの法則から温度を求めている。
d:深部の温度分布がわかる。
e:温度分解能は 1℃である。
1. a b 2. a e 3. b c 4. c d 5. d e
国試第34回午後:第39問
100 kHz の電流を成人男性に通電したときの最小感知電流[mA]に近いのはどれか。
1:0.1
2:1
3:10
4:100
5:1000
国試第34回午後:第58問
標的型攻撃メールの特徴について誤っているのはどれか。
1:特定組織(官公庁、企業、医療機関等)の機密情報の窃取を目的とする。
2:件名、本文、添付ファイル名を業務に関連したものに偽装する。
3:本文や添付ファイルに記載したリンク先にウイルスを仕込む。
4:組織が頻繁に利用するウェブサイトを改ざんしウイルスを仕込む。
5:大量のスパムメールを不特定多数に送信する。
国試第34回午後:第64問
パルスオキシメータについて正しいのはどれか。
1:動脈血酸素分圧を測定する。
2:足趾では測定できない。
3:紫外光の吸光度により判定する。
4:循環不全では動脈波の検出が難しい。
5:マニキュアの影響は受けない。
国試第34回午後:第68問
高気圧酸素治療の加圧時に生じる合併症はどれか。
a:鼓膜障害
b:腸管破裂
c:皮下気腫
d:肺の過膨張症候群
e:副鼻腔スクイーズ
1. a b 2. a e 3. b c 4. c d 5. d e
国試第34回午後:第69問
膜型人工肺について正しいのはどれか。
1:シリコーンの気体透過係数はポリプロピレンより大きい。
2:シリコーンを用いた多孔質膜が用いられている。
3:親水性の膜が用いられている。
4:内部灌流型が多数を占める。
5:ウェットラングは微小孔からの血漿漏出により生じる。
国試第34回午後:第70問
人工心肺を用いた体外循環中の電解質、内分泌系の変動で正しいのはどれか。
a:血中ナトリウム濃度は低下する。
b:血中カリウム濃度は低下する。
c:赤血球液の使用で血中カルシウム濃度は上昇する。
d:インスリンの過剰分泌により低血糖になりやすい。
e:バソプレシンは増加する。
1. a b c 2. a b e 3. a d e 4. b c d 5. c d e
国試第34回午後:第71問
人工心肺を用いた体外循環中の溶血について正しいのはどれか。
1:膜型肺より気泡型肺の方が溶血は少ない。
2:遠心ポンプよりローラポンプの方が溶血は少ない。
3:高度溶血例ではヘパリンを追加する。
4:細い送血カニューレを用いると溶血は少なくなる。
5:血中カリウム濃度が上昇した場合、高度溶血を疑う。
国試第34回午後:第72問
人工心肺を用いた体外循環で正しいのはどれか。
1:開始時には、まず脱血カニューレ、続いて送血カニューレを挿入する。
2:大動脈遮断時には、一時的に送血流量を増加させる。
3:大動脈遮断解除時には、一時的に送血流量を増加させる。
4:遠心ポンプを用いる場合、復温時には、同一回転数でも流量が増加する。
5:人工心肺停止時には、脱血側回路をクランプしてから回転を止める。
国試第34回午後:第73問
人工心肺を用いた体外循環中の血液凝固系管理で正しいのはどれか。
1:ACT(活性化凝固時間)を 200 秒以下に維持する。
2:全回路ヘパリンコーティング人工心肺では充填時のヘパリン量を半減できる。
3:プロタミン投与によって血圧は上昇する。
4:プロタミンには軽度の抗凝血作用があるのでヘパリン中和時の過量投与は避 ける。
5:プロタミン投与後も術野出血が続く場合は吸引ポンプを回し回収を続ける。
国試第34回午後:第74問
人工心肺を用いた体外循環中の安全管理で正しいのはどれか。
1:レベルセンサには磁気センサが用いられている。
2:レベルセンサはエアトラップ(バブルトラップ)に取り付ける。
3:フィルタのサイズは動脈フィルタの方がバブルトラップより目が細かい。
4:閉鎖回路では気泡流入の可能性はない。
5:エアブロックとは送血回路が空気で満たされ送血が止まることをいう。
臨床工学技士国家試験第1回
臨床工学技士国家試験第2回
臨床工学技士国家試験第3回
臨床工学技士国家試験第4回
臨床工学技士国家試験第5回
臨床工学技士国家試験第6回
臨床工学技士国家試験第7回
臨床工学技士国家試験第8回
臨床工学技士国家試験第9回
臨床工学技士国家試験第10回
臨床工学技士国家試験第11回
臨床工学技士国家試験第12回
臨床工学技士国家試験第13回
臨床工学技士国家試験第14回
臨床工学技士国家試験第15回
臨床工学技士国家試験第16回
臨床工学技士国家試験第17回
臨床工学技士国家試験第18回
臨床工学技士国家試験第19回
臨床工学技士国家試験第20回
臨床工学技士国家試験第21回
臨床工学技士国家試験第22回
臨床工学技士国家試験第23回
臨床工学技士国家試験第24回
臨床工学技士国家試験第25回
臨床工学技士国家試験第26回
臨床工学技士国家試験第27回
臨床工学技士国家試験第28回
臨床工学技士国家試験第29回
臨床工学技士国家試験第30回
臨床工学技士国家試験第31回
臨床工学技士国家試験第32回
臨床工学技士国家試験第33回
臨床工学技士国家試験第34回
臨床工学技士国家試験第35回
臨床工学技士国家試験第36回
臨床工学技士国家試験第37回
臨床工学技士国家試験第38回