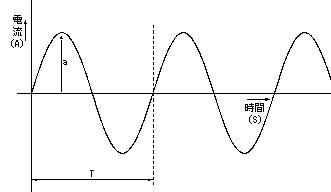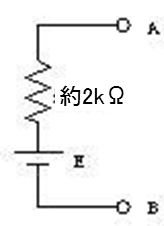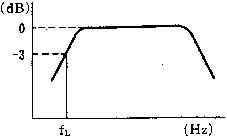第1回午前の過去問
国試第1回午前:第1問
医療従事者のとるべき態度について適切でないのはどれか。
1:業務中に知り得た患者の秘密はその死後といえども他人に漏らさない。
2:患者に痛みや苦痛をできるだけ与えないように心掛けること。
3:患者の社会的立場や家庭環境を十分に考慮して患者に接する。
4:医療は患者に施し与えるものであるから、医療従事者が患者と対等の立場をとることはできる限りさける。
5:患者の不安に満ちた、とかく弱くなりがちな心を励まし助けていく愛情と心くばりをもって業務を行う。
国試第1回午前:第7問
ネフローゼ症候群にみられる浮腫の一次的原因はどれか。
1:毛細血管の透過性の亢進
2:毛細血管圧の上昇
3:リンパ管の閉塞
4:低蛋白血症
5:高コレステロール血症
国試第1回午前:第8問
退行性病変はどれか。
1:うっ血肝
2:動脈管開存症
3:肺膿瘍
4:アルツハイマー病
5:胆道癌
国試第1回午前:第9問
悪性上皮性腫瘍はどれか。
a:絨毛上皮腫
b:大腸乳頭腫
c:リンパ性白血病
d:唾液腺混合腫瘍
e:肺腺癌
1. a b 2. a e 3. b c 4. c d 5. d e
国試第1回午前:第12問
正しいのはどれか。
a:平成30年簡易生命表によると、日本人の0歳時の平均寿命は80歳を超えていない。
b:平成30年の我が国の死因別死亡率は高い順に1悪性新生物、2心疾患、3脳血管疾患である。
c:我が国の疾病構造は急性感染症、慢性感染症、次に成人病型へと変化してきた。
d:人口構造が高齢化すると包括的医療の重要性が増す。
e:成人病の予防に食生活の注意は重要でない。
1. a b 2. a e 3. b c 4. c d 5. d e
国試第1回午前:第13問
正しいのはどれか。
a:コレラは三類感染症である。
b:インフルエンザは届出伝染病である。
c:病院内で緑膿菌感染が発見されたら、保険所に届け出なければならない。
d:病院内で血液に接触する可能性のある従事者にはB型肝炎ワクチン接種が法律により義務づけられている。
e:いわゆるAIDSウイルスは、性的接触がなければ感染しない。
1. a b 2. a e 3. b c 4. c d 5. d e
国試第1回午前:第14問
保険所業務でないのはどれか。
1:人工動態統計に関すること。
2:栄養改善に関すること。
3:大気汚染防止に関すること。
4:精神衛生に関すること。
5:歯科衛生に関すること。
国試第1回午前:第15問
臨床工学技士の取扱う生命維持管理装置でないのはどれか。
1:直流除細動装置
2:血液透析装置
3:人工呼吸器
4:超音波診断装置
5:体外式心臓ペースメーカ
国試第1回午前:第17問
正しいのはどれか。
a:口-口人工呼吸が有効に行えない原因の多くは気道確保が不十分のためである。
b:ハイムリック法は喉頭や気管内の異物を除去する方法である。
c:心マッサージは肋骨を骨折しないように、柔らかいベッドの上で行う。
d:一人で蘇生術を行うときは心マッサージ60回と人工呼吸10回を交互に行う。
e:頚動脈の脈拍触知は心マッサージの効果を知る指標になる。
1. a b c 2. a b e 3. a d e 4. b c d 5. c d e
国試第1回午前:第18問
ICUに常備すべき器具、装置はどれか。
a:救急蘇生用具
b:人工呼吸器
c:除細動器
d:超音波吸引装置(超音波メス)
e:コンピュータ断層撮影(CT)装置
1. a b c 2. a b e 3. a d e 4. b c d 5. c d e
国試第1回午前:第32問
長期透析患者によくみられるのはどれか。
a:赤血球増多症
b:貧血
c:高血圧
d:掻痒感
e:四肢麻痺
1. a b c 2. a b e 3. a d e 4. b c d 5. c d e
国試第1回午前:第33問
尿路感染を起こしやすいのはどれか。
a:新婚時女性
b:糖尿病
c:痛風
d:急性糸球体腎炎
e:急性肝炎
1. a b 2. a e 3. b c 4. c d 5. d e
国試第1回午前:第35問
ネフローゼ症候群で、まだ治療が行われていない時期にみられる所見はどれか。
1:アルブミン血症
2:高ガンマグロブリン血症
3:高コレステロール血症
4:高アミラーゼ血症
5:高尿酸血症
国試第1回午前:第40問
出血傾向を示すのはどれか。
a:ビタミンA欠乏症
b:ビタミンB1欠乏症
c:ビタミンC欠乏症
d:ビタミンK欠乏症
e:ビタミンD欠乏症
1. a b 2. a e 3. b c 4. c d 5. d e
国試第1回午前:第41問
血小板について正しいのはどれか。
a:血小板数20万/μL以下を血小板減少症という。
b:再生不良性貧血では血小板は減少しない。
c:血管内血液凝固症候群(DIC)では血小板は減少する。
d:血小板の産生の低下した人では血小板輸血が行われる。
e:血小板は血液回路内面に粘着する。
1. a b c 2. a b e 3. a d e 4. b c d 5. c d e
国試第1回午前:第42問
正しいのはどれか。
a:同じ薬を長期間使用すると効果が弱くなることを耐性発現という。
b:薬効を公正に評価する方法として二重盲検法がある。
c:解熱鎮痛薬で異常反応を示す人は他の薬にも過敏症を起こしやすい。
d:抗腫瘍薬を連用すると菌交代がみられる。
e:母親の服用した薬が授乳で乳児に移行することはない。
1. a b c 2. a b e 3. a d e 4. b c d 5. c d e
国試第1回午前:第43問
中枢神経系用薬でないのはどれか。
1:サクシニルコリン
2:ハロセン
3:バルビツレイト
4:モルヒネ
5:ベンゾジアゼパム
国試第1回午前:第45問
血圧を下げる作用があるのはどれか。
a:アルドステロン
b:ノルアドレナリン(ノルエピネフリン)
c:インスリン
d:カルシウム拮抗薬
e:β遮断薬
1. a b 2. a e 3. b c 4. c d 5. d e
国試第1回午前:第54問
熱容量と比熱について誤っているのはどれか。
1:1gの物体の温度を1°C上昇させるのに必要な熱量を比熱という。
2:体積と比熱が等しく密度の異なる二つの物体では、密度の大きい物体の方が熱容量は大きい。
3:熱容量が等しく温度の異なる二つの物体を接触させると、熱平衡に達したとき、この二物体はそれぞれの最初の温度の平均の温度となる。
4:温度の等しい二つの物体を接触させると、比熱の大きい物体から比熱の小さい物体に熱が移動する。
5:一定の質量の気体の熱容量は、圧力や体積によって異なる。
国試第1回午前:第68問
低周波電流の生体影響の限界電流値として誤っている組合せはどれか。
a:体内から心臓に流すと心室細動が起こる。・・・・・1μA
b:体内から心臓に流すと心室細動が起こる。・・・・・100μA
c:体外から流すと電流刺激を感じる。・・・・・・・・・・・1mA
d:体外から流すと不随意運動を生ずる。・・・・・・・・10mA
e:体外から流すと心室細動を生じる。・・・・・・・・・・10A
1. a b 2. a e 3. b c 4. c d 5. d e
国試第1回午前:第81問
正しいのはどれか。
a:電磁波の生体内での吸収は導電率できまる。
b:可視光線の吸収スペクトラムは血液の酸素飽和度では変化しない。
c:エックス線の減衰は原子の密度できまり、原子の種類には影響されない。
d:RIを用いた生体の計測では、臓器の形はわからない。
e:超音波エコーによって密度および硬さの異なる組織の境界面がわかる。
1. a b 2. a e 3. b c 4. c d 5. d e
国試第1回午前:第82問
動脈血の酸素飽和度を連続測定するパルスオキシメータはどの方法を用いているか。
1:特定周波数の電流に対する電気インピーダンスを利用
2:磁場を加え、核磁気共鳴を利用
3:微弱なエックス線の吸収率を利用
4:超音波に対する音響インピーダンスを利用
5:特定波長の光の吸収率を利用
国試第1回午前:第83問
超音波ドップラ血流計について正しいのはどれか。
a:無侵襲的な測定法である。
b:血液によって散乱される超音波を利用している。
c:血流によって生じる血管壁の運動を利用している。
d:血流量を直接測定できる。
e:肺組織の血流測定は困難である。
1. a b c 2. a b e 3. a d e 4. b c d 5. c d e
国試第1回午前:第86問
侵襲のない血流測定機器、方法はどれか。
1:色素希釈法
2:熱希釈法
3:電磁血流計
4:超音波ドップラ法
5:サーミスタ血流計
臨床工学技士国家試験第1回
臨床工学技士国家試験第2回
臨床工学技士国家試験第3回
臨床工学技士国家試験第4回
臨床工学技士国家試験第5回
臨床工学技士国家試験第6回
臨床工学技士国家試験第7回
臨床工学技士国家試験第8回
臨床工学技士国家試験第9回
臨床工学技士国家試験第10回
臨床工学技士国家試験第11回
臨床工学技士国家試験第12回
臨床工学技士国家試験第13回
臨床工学技士国家試験第14回
臨床工学技士国家試験第15回
臨床工学技士国家試験第16回
臨床工学技士国家試験第17回
臨床工学技士国家試験第18回
臨床工学技士国家試験第19回
臨床工学技士国家試験第20回
臨床工学技士国家試験第21回
臨床工学技士国家試験第22回
臨床工学技士国家試験第23回
臨床工学技士国家試験第24回
臨床工学技士国家試験第25回
臨床工学技士国家試験第26回
臨床工学技士国家試験第27回
臨床工学技士国家試験第28回
臨床工学技士国家試験第29回
臨床工学技士国家試験第30回
臨床工学技士国家試験第31回
臨床工学技士国家試験第32回
臨床工学技士国家試験第33回
臨床工学技士国家試験第34回
臨床工学技士国家試験第35回
臨床工学技士国家試験第36回
臨床工学技士国家試験第37回
臨床工学技士国家試験第38回