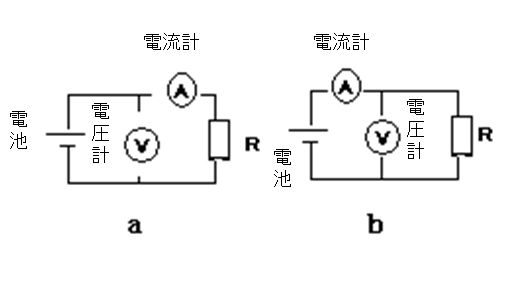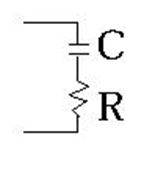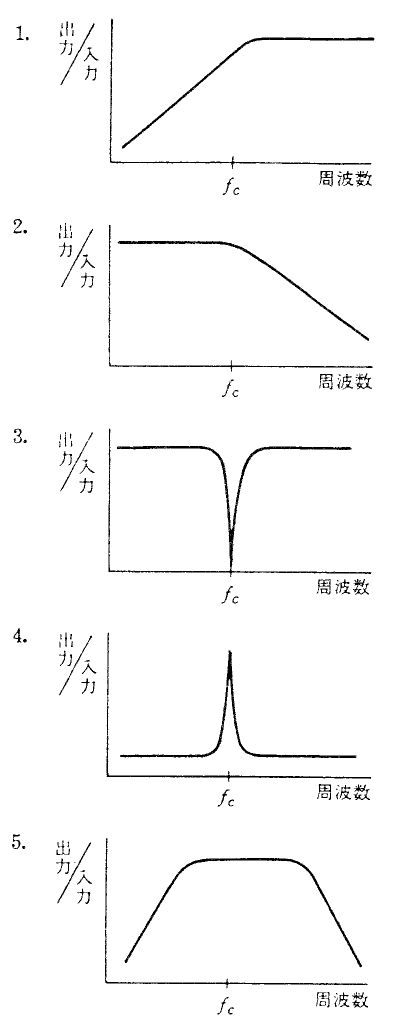第3回午前の過去問
国試第3回午前:第1問
臨床工学技士の職務について誤っているのはどれか。
1:ME機器の性能の十分な活用と安全を図ることが職務である。
2:医療行為には医師の指示が必要であるが、業務上のデータや状況は医師の求めがあったときにのみ報告すべきである。
3:業務上の医療過誤に対しては直接の責任を負わなければならない。
4:高度に専門的な職種であるが、業務に当たって看護婦や臨床検査技師など他の医療関係者と密接な連携をとるべきである。
5:患者に関する秘密尊重をうたった世界医師会のジュネーブ宣言を守らなければならない。
国試第3回午前:第2問
正しいのはどれか。
a:医師の誤った指示で臨床工学技士が装置を操作したため発生した事故に対し、臨床工学技士は法的責任を免れる。
b:看護婦が生命維持管理装置を操作することは、臨床工学技士法に触れる。
c:保健婦が人工呼吸器を操作することは臨床工学技士法に触れる。
d:臨床工学技士が機械の操作を誤って患者に被害を与えた場合、民事上の責任を問われることがある。
e:故意でなくても、誤って患者に被害を与えた場合には、刑事上の責任を問われることがある。
1. a b 2. a e 3. b c 4. c d 5. d e
国試第3回午前:第9問
炎症性疾患はどれか。
a:結核
b:心筋症
c:尿毒症
d:脂肪肝
e:真菌症
1. a b 2. a e 3. b c 4. c d 5. d e
国試第3回午前:第11問
悪性腫瘍の特徴はどれか。
a:膨張性に発育する傾向が強い。
b:腫瘍部位の境界が一般に不鮮明である。
c:腫瘍の進行に伴い、悪液質がみられる。
d:腫瘍の初発部位から離れた部位に細胞が運ばれ発育する。
e:腫瘍の摘出手術後の再発はまれである。
1. a b c 2. a b e 3. a d e 4. b c d 5. c d e
国試第3回午前:第12問
正しいのはどれか。
a:人口動態の把握は保険所の業務の1つである。
b:病原体は宿主に入ると必ず発症する。
c:コレラは届出伝染病である。
d:食中毒は法的には届出の義務がない。
e:臨床工学技士の資格は、国家試験に基づく厚生大臣免許による。
1. a b 2. a e 3. b c 4. c d 5. d e
国試第3回午前:第13問
受身(退行性)の病変はどれか。
a:壊死
b:再生
c:浮腫
d:塞栓
e:萎縮
1. a b 2. a e 3. b c 4. c d 5. d e
国試第3回午前:第15問
ワクチン接種が行われるのはどれか。
a:猩紅熱
b:破傷風
c:風 疹
d:結 核
e:梅 毒
1. a b c 2. a b e 3. a d e 4. b c d 5. c d e
国試第3回午前:第16問
臨床工学技士が行ってはならない業務はどれか。
1:人工心肺の血液量の調節
2:人工呼吸用マスクの患者への接続
3:気管内チューブの挿管
4:モニタ用心電計電極の患者への装着
5:血液浄化装置の穿刺針の内シャントへの接続
国試第3回午前:第19問
正しいのはどれか。
a:長期にわたる連用で薬の効果が薄れるとき耐性発現という。
b:母乳に排泄される薬の量は極めて少ない。
c:薬物による胎児奇形発現の危険性は妊娠5~6ヶ月のころが最も高い。
d:抗生剤を長期連用しても菌交代は生じない。
e:脱水状態や低蛋白では薬物が過量になりやすい。
1. a b 2. a e 3. b c 4. c d 5. d e
国試第3回午前:第27問
急性腎不全の原因となるのはどれか。
a:DIC
b:甲状腺機能亢進症
c:脳腫瘍
d:カナマイシン
e:心原性ショック
1. a b c 2. a b e 3. a d e 4. b c d 5. c d e
国試第3回午前:第31問
肉眼的血尿の原因となるのはどれか。
a:リポイドネフローゼ
b:糖尿病性腎症
c:急性膀胱炎
d:腎 癌
e:IgA腎症
1. a b c 2. a b e 3. a d e 4. b c d 5. c d e
国試第3回午前:第34問
正しいのはどれか。
a:ウイルムス腫瘍は小児に多い。
b:尿管結石は腎内で形成され下降したものである。
c:馬蹄腎は嚢胞腎の特殊な例である。
d:睾丸腫瘍は良性のことが多く手術で根治できる。
e:不妊の原因は男性側にもある。
1. a b c 2. a b e 3. a d e 4. b c d 5. c d e
国試第3回午前:第37問
循環器用薬はどれか。
a:ドパミン
b:Ca拮抗薬
c:硝酸イソソルビド
d:セロトニン
e:ハロペリドール
1. a b c 2. a b e 3. a d e 4. b c d 5. c d e
国試第3回午前:第41問
正しいのはどれか。
a:グラム陽性菌と陰性菌は、色素による染まり方の差で区別される。
b:好気性菌と嫌気性菌は、発育に酸素を必要とするか否かで区別される。
c:ひよりみ感染とは、ある限られた気温と湿度の下でのみ感染を起こし得る菌の感染をいう。
d:抗酸菌とは、滅菌にホルムアルデヒドが効かない菌をいう。
e:グラム陰性桿菌は病院内感染を起こしやすい微生物の一つである。
1. a b c 2. a b e 3. a d e 4. b c d 5. c d e
国試第3回午前:第46問
慢性腎不全の主要な原因はどれか。
a:妊娠中毒症
b:慢性糸球体腎炎
c:糖尿病
d:痛風
e:尿管結石
1. a b 2. a e 3. b c 4. c d 5. d e
国試第3回午前:第67問
生体物性の一般的特徴とその例との組合せで誤っているのはどれか。
1:異方性・・・・・・・・・・・・筋組織の力学的特性
2:非線形性・・・・・・・・・・細胞膜の電気的特性
3:周波数依存性・・・・・・組織の電気定数特性
4:温度依存性・・・・・・・・生化学反応の特性
5:粘弾性・・・・・・・・・・・・組織の塑性変形特性
国試第3回午前:第69問
誤っているのはどれか。
1:神経、骨格筋、心筋などは電流によって刺激されると興奮する。
2:高周波電流では周波数が高くなるほど刺激作用は減る。
3:体表面から低周波電流を流した場合、10mA程度で心室細動が生じる。
4:体内から心臓に低周波電流を流した場合、100μA程度で心室細動が生じる。
5:高周波電流の加熱作用は治療にも用いられる。
国試第3回午前:第70問
誤っているのはどれか。
1:大動脈中の流れは常に層流である。
2:レイノルズ数が約2,000を超えると層流から乱流へ変わる。
3:パアズイユの流れでは、流量は管径、管長、両端での圧力差に依存する。
4:生体組織は粘性と弾性をあわせもる。
5:生体組織の伸びの弾性はヤング率で表される。
国試第3回午前:第73問
ある距離を同じ巻尺で何回も繰り返し測定し、その分布を調べたら正規分布になった。その平均値は10.5m、標準偏差は0.5mであった。また正確な距離は10.0mであった。正しいのはどれか。
a:測定をさらに繰り返すと、平均値は正確な値と一致する。
b:標準偏差は偶然誤差の大きさを示す。
c:平均値と正確な値との差は系統誤差の大きさを示す。
d:平均値と標準偏差から正確な値が推測できる。
e:測定値は10.0mと11.0mの範囲に全部入っている。
1. a b 2. a e 3. b c 4. c d 5. d e
国試第3回午前:第80問
心音図の測定に関係のないのはどれか。
a:静電シールド
b:フランク(Frank)誘導
c:マイクロホン
d:フィルタ
e:磁オシログラフ
1. a b 2. a e 3. b c 4. c d 5. d e
国試第3回午前:第81問
光→電気変換器を使用するのはどれか。
1:脳波計
2:筋電計
3:指先容積脈波計
4:pHメータ
5:眼振計
国試第3回午前:第84問
超音波検査で誤っているのはどれか。
a:ドップラは運動している物体から反射される超音波の周波数が入射超音波周波数と異なることを利用する。
b:Mモードは反射波を生じる界面の時間的動きを二次元的に表示する。
c:Bモードは反射波を基線上のスパイクとして表示する。
d:音響インピーダンスは密度と音の吸収率の積で表される。
e:超音波エコー断層法に使用される超音波の波長は0.15~1.5mmである。
1. a b 2. a e 3. b c 4. c d 5. d e
国試第3回午前:第85問
放射性同位元素(RI)による画像検査で誤っているのはどれか。
a:エミッションCTの解像力はエックス線CTよりよい。
b:RI画像検査で主に用いられる放射線はβ線である。
c:ポジトロンCTにはN,O,Cなど生理的に存在する元素の同位体がしばしば用いられる。
d:組織の虚血を調べることができる。
e:Iは甲状腺検査に使用される。
1. a b 2. a e 3. b c 4. c d 5. d e
国試第3回午前:第89問
カフ式非観血血圧測定について正しいのはどれか。
a:カフはできるだけ緩く巻く。
b:カフ圧はできるだけゆっくり上昇させる。
c:カフの幅は測定に影響しない。
d:カフを巻く腕はほぼ心臓の高さになるようにする。
e:カフの脱気速度は測定に影響する。
1. a b 2. a e 3. b c 4. c d 5. d e
国試第3回午前:第90問
誤っているのはどれか。
1:電磁血流計は電磁誘導を利用した計測器である。
2:超音波ドップラ血流計は無侵襲計測器である。
3:レーザドップラ血流計は赤血球からの散乱光を利用した計測器である。
4:色素希釈法は心拍出量計測に利用される。
5:熱希釈法は体温変化を利用した血流計測法である。
臨床工学技士国家試験第1回
臨床工学技士国家試験第2回
臨床工学技士国家試験第3回
臨床工学技士国家試験第4回
臨床工学技士国家試験第5回
臨床工学技士国家試験第6回
臨床工学技士国家試験第7回
臨床工学技士国家試験第8回
臨床工学技士国家試験第9回
臨床工学技士国家試験第10回
臨床工学技士国家試験第11回
臨床工学技士国家試験第12回
臨床工学技士国家試験第13回
臨床工学技士国家試験第14回
臨床工学技士国家試験第15回
臨床工学技士国家試験第16回
臨床工学技士国家試験第17回
臨床工学技士国家試験第18回
臨床工学技士国家試験第19回
臨床工学技士国家試験第20回
臨床工学技士国家試験第21回
臨床工学技士国家試験第22回
臨床工学技士国家試験第23回
臨床工学技士国家試験第24回
臨床工学技士国家試験第25回
臨床工学技士国家試験第26回
臨床工学技士国家試験第27回
臨床工学技士国家試験第28回
臨床工学技士国家試験第29回
臨床工学技士国家試験第30回
臨床工学技士国家試験第31回
臨床工学技士国家試験第32回
臨床工学技士国家試験第33回
臨床工学技士国家試験第34回
臨床工学技士国家試験第35回
臨床工学技士国家試験第36回
臨床工学技士国家試験第37回
臨床工学技士国家試験第38回