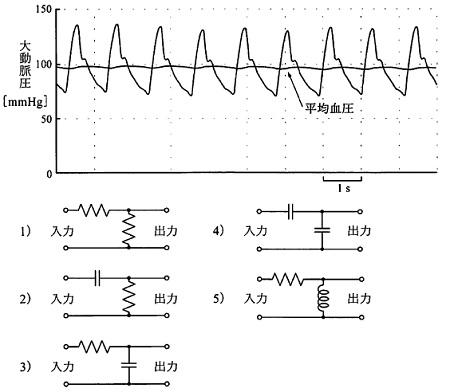臨床工学技士問題表示
臨床工学技士国家試験
解説
観血式血圧測定系(カテーテル−フラッシュ液−チューブ−トランスデューサ)は力学的に「自然周波数」と「減衰比」で応答が決まる系である。波形ダンピング(過減衰・減衰過大)は、圧力伝達経路のコンプライアンス増大や流路抵抗増大により高周波成分(立ち上がり、切痕など)が失われることで起こり、典型的には収縮期が低め、拡張期が高めに出て脈圧が小さく見える。具体的原因には、回路内の気泡混入(コンプライアンス増大)、カテーテル先端での血栓形成や先当り(流路抵抗増大・部分閉塞)がある。一方、ゼロ点調整不良やトランスデューサの設置高さの変更は静水圧基準のズレを生み測定値全体がオフセットするだけで、波形の減衰(ダンピング)そのものの原因ではない。
選択肢別解説
正しい。回路内に気泡が混入すると液柱のコンプライアンスが増加し、系の自然周波数低下と減衰増大が生じる。結果として高周波成分が削られ、立ち上がりが鈍く脈圧が小さく見える(ダンピング)。
正しい。カテーテル先端で血栓が形成されると内腔が狭窄・部分閉塞して流路抵抗が増大する。圧力波の伝達が妨げられ、特に高周波成分が減衰し、脈圧が小さくなる(ダンピング)。
正しい。カテーテル先端が血管壁に当たる(先当り)と先端開口がふさがれ、実質的に部分閉塞となって流路抵抗が増大する。これにより圧力波が減衰し、波形が鈍り脈圧が小さくなる(ダンピング)。
誤り。ゼロ点調整不良は静水圧基準の設定ミスによるオフセット誤差を生じさせる要因で、波形の減衰(ダンピング)を引き起こすものではない。波形形状は保たれるが全体が上下にずれる。
誤り。血圧トランスデューサの設置高さの変更は静水圧差による基線(オフセット)のズレを生じる。右房基準より高ければ低く、低ければ高く測定されるが、波形自体の減衰(ダンピング)の原因ではない。
解説を表示するにはログインが必要です。ログインすると無料枠(1日5問)をご利用いただけます。
無料プランでは解説を1日5問まで表示できます。解説を表示すると残り回数が消費されます。
今日: 回 | 残り 回
本日の無料枠を使い切りました。プレミアム登録で無制限にご利用いただけます。
解説
本問は超音波ドプラ法の基礎。反射体(血球)がプローブに近づくと受信周波数は発信周波数より高くなる(正のドプラシフト)。ドプラ周波数は $f_d = \frac{2 f_0 v \cos\theta}{c}$ で与えられる。連続波(CW)ドプラは送受信を連続で行うため距離分解能がなく、特定深さの血流だけを選んで計測することはできない。一方、パルスドプラは距離分解能を持つが、最大検出可能ドプラ周波数はナイキスト周波数 $PRF/2$ に制限され、これを超えるとエイリアシング(折り返し)が生じる。また、最大計測深度は反射波が次パルス送信までに戻る必要から $PRF \le \frac{c}{2 d_{\max}}$ に制約され、PRFを上げるほど $d_{\max}$ は浅くなる。PRFは通常数kHzオーダであり、MHzは搬送波(送信超音波)の周波数帯である。以上より正しいのは1。
選択肢別解説
正しい。血流がプローブに向かって近づくとドプラシフト $f_d$ は正となり、受信周波数は発信周波数より高くなる。式は $f_d = \frac{2 f_0 v \cos\theta}{c}$。
誤り。連続波ドプラ法(CW)は距離分解能を持たず、ビーム内の全ての散乱体の速度成分を重ね合わせて検出するため、特定深さ(特定部位)の血流速だけを識別できない。
誤り。エイリアシングは高いドプラ周波数(=高い血流速や低い送受角、低いPRF設定など)で生じ、条件は $|f_d| > PRF/2$。血流速が小さいときには起こりにくい。
誤り。反射波が戻るまで次パルスを待つ必要があり、$PRF \le \frac{c}{2 d_{\max}}$。したがってPRFが高いほど許容される最大計測深度 $d_{\max}$ は浅くなる。設問は関係を逆に述べている。
誤り。パルスドプラのパルス繰り返し周波数(PRF)は通常数kHzオーダで、例えば $d_{\max}=15\,\mathrm{cm}$、$c\approx1540\,\mathrm{m/s}$ なら $PRF \lesssim \frac{1540}{2\times0.15} \approx 5.1\,\mathrm{kHz}$。5 MHzは超音波搬送波の周波数帯であり、PRFではない。
解説を表示するにはログインが必要です。ログインすると無料枠(1日5問)をご利用いただけます。
無料プランでは解説を1日5問まで表示できます。解説を表示すると残り回数が消費されます。
今日: 回 | 残り 回
本日の無料枠を使い切りました。プレミアム登録で無制限にご利用いただけます。
解説
超音波ドプラ血流計のドプラシフトは、反射体(赤血球)が動く速度と超音波ビーム方向の成分に比例し、$f_d = \frac{2 f_0 v \cos \theta}{c}$ で与えられる。したがって、血流がプローブへ近づくと $\cos \theta > 0$ かつ $v>0$ より $f_d>0$ となり受信周波数は送信周波数より高くなる。ビームと血流が直交($\theta=90^\circ$)では $\cos 90^\circ=0$ のためシフトは生じない。パルスドプラ法では観測できる最大ドプラ周波数はナイキスト周波数 $f_{\text{Nyq}}=f_{PRF}/2$ に制限され、$|f_d|>f_{PRF}/2$ でエイリアシング(周波数折り返し)が起こるため、流速が速いほど発生しやすい。パルス繰り返し周波数 $f_{PRF}$ は搬送波(送信周波数 $f_0$)とは独立のパラメータで、深さ分解能や最大計測深度とトレードオフ関係にある。最大計測深度は $D_{\max}=\frac{c}{2 f_{PRF}}$ で、$f_{PRF}$ を高くすると浅くなる。以上より、正しい肢は2と3である。
選択肢別解説
誤り。血流がプローブに向かって近づくとドプラシフトは正($f_d>0$)となり、受信周波数は送信周波数より高くなる($f_{rec}=f_0+f_d$)。式 $f_d=\frac{2 f_0 v \cos \theta}{c}$ からも、$v>0$ かつ $\cos \theta>0$ のとき $f_d$ は増加する。
正しい。ドプラシフトは角度の余弦に比例し、$\theta=90^\circ$ では $\cos 90^\circ=0$ のためドプラシフトはゼロとなり観測されない。
正しい。血流速度が速くなると $|f_d|$ が増大し、ナイキスト周波数 $f_{PRF}/2$ を超えるとエイリアシング(周波数折り返し)が発生するため、速い流れほど起こりやすい。
誤り。パルス繰り返し周波数 $f_{PRF}$ はドプラ信号($f_d$)の標本化に関係し、$f_{PRF}\ge 2 f_{d,\max}$ が目安である。搬送波である超音波の振動周波数 $f_0$(通常 MHz 帯)とは別の量で、$f_{PRF}$ を $2 f_0$ 以上にする必要はない。
誤り。最大計測深度は $D_{\max}=\frac{c}{2 f_{PRF}}$ で表され、$f_{PRF}$ を高くすると $D_{\max}$ は小さくなる(浅くなる)。深部を測るには $f_{PRF}$ を下げる必要がある。
解説を表示するにはログインが必要です。ログインすると無料枠(1日5問)をご利用いただけます。
無料プランでは解説を1日5問まで表示できます。解説を表示すると残り回数が消費されます。
今日: 回 | 残り 回
本日の無料枠を使い切りました。プレミアム登録で無制限にご利用いただけます。
解説
血圧はおおむね動脈圧 ≈ 心拍出量と末梢血管抵抗の積で表される($BP = CO \times TPR$)。したがって、交感神経緊張の亢進は心拍数・収縮力増強(CO↑)と末梢血管収縮(TPR↑)を介して血圧を上昇させ、心拍出量の増加自体も血圧上昇要因である。また遺伝的素因は本態性高血圧のリスクを高め、交感神経・RAAS・腎ナトリウム取扱いなどの調節系の反応性に影響しうるため、血圧上昇に関与しうる。一方、血管拡張はTPRを低下させ、腎からのナトリウム排泄増加は細胞外液量・循環血液量を減少させて前負荷・COを下げる方向に働くため、いずれも血圧上昇の機序としては誤りである。
選択肢別解説
交感神経の緊張は心拍数・心収縮力の増加(CO↑)および末梢血管収縮(TPR↑)をもたらし、$BP = CO \times TPR$ の関係から血圧上昇の機序として正しい。
心拍出量(CO)の増加は、$BP = CO \times TPR$ により血圧を直接上昇させるため、血圧上昇の機序として正しい。
遺伝的素因は本態性高血圧の発症リスクを高め、交感神経系やRAAS、腎のナトリウムハンドリングなど血圧調節機構の反応性に影響しうる要因であり、血圧上昇に関与する因子として妥当である(誤りではない)。
血管拡張は末梢血管抵抗(TPR)を低下させるため、$BP = CO \times TPR$ の観点から血圧は低下方向に働く。よって「血圧上昇の機序」としては誤りである。
腎臓からのナトリウム排泄増加は細胞外液量・循環血液量を減少させ、静脈還流・前負荷と心拍出量(CO)を低下させるため血圧は下がる方向に働く。したがって血圧上昇の機序としては誤りである。
解説を表示するにはログインが必要です。ログインすると無料枠(1日5問)をご利用いただけます。
無料プランでは解説を1日5問まで表示できます。解説を表示すると残り回数が消費されます。
今日: 回 | 残り 回
本日の無料枠を使い切りました。プレミアム登録で無制限にご利用いただけます。
解説
本問は水平な円管内でのベルヌーイの関係を前提に、静圧p・動圧qと総圧(全圧)P_tの関係を問う。水平で位置エネルギー差がないため $\rho g h=0$ とみなせば、総圧は $P_t=p+\frac{\rho v^2}{2}$ で一定(外部とのエネルギー授受・損失を無視)となる。動圧 $q=\frac{\rho v^2}{2}$ は流速vの2乗と密度$\rho$に比例するので、vを2倍にするとqは4倍、$\rho$を2倍にするとqは2倍になる。よって「流速が2倍になると動圧は2倍」は誤りで、他の選択肢は正しい。
選択肢別解説
誤り。動圧は $q=\frac{\rho v^2}{2}$ で、流速vの2乗に比例する。vを2倍にすると $q$ は4倍になるため、「2倍になる」は不適切。
正しい。動圧は $q=\frac{\rho v^2}{2}$ で密度$\rho$に比例するので、$\rho$が2倍になればqも2倍になる。
正しい。水平管では位置エネルギー項 $\rho g h=0$ で、総圧(全圧)は $P_t=p+\frac{\rho v^2}{2}$ となり、静圧と動圧の和に等しい。
正しい。損失や外部仕事がなければ総圧 $P_t$ は一定なので、動圧 $\frac{\rho v^2}{2}$ が下がれば、差し引きで静圧pは上がる(ベルヌーイ効果)。
正しい。流速 $v=0$ では動圧 $\frac{\rho v^2}{2}=0$ となるため、総圧は静圧に等しくなる($P_t=p$)。
解説を表示するにはログインが必要です。ログインすると無料枠(1日5問)をご利用いただけます。
無料プランでは解説を1日5問まで表示できます。解説を表示すると残り回数が消費されます。
今日: 回 | 残り 回
本日の無料枠を使い切りました。プレミアム登録で無制限にご利用いただけます。
解説
血液は非ニュートン流体で、赤血球の変形・配向や凝集の程度、血球濃度(ヘマトクリット)、温度、せん断速度などで見かけ粘性が変化する。粘性を増加させる要因は、赤血球が多くなる(ヘマトクリット上昇)ことと、低せん断下で生じる赤血球の連銭(ルーロ)形成である。逆に、体温上昇は一般に粘性を低下させ、せん断速度の増加は血液のずり薄化(shear-thinning)により粘性を下げる。さらに、集軸効果によって血管壁近傍に血漿層ができると、流れ系としての見かけ粘性は低下する。以上より、粘性率を増加させるのは「ヘマトクリット値の上昇」と「連銭形成」である。
選択肢別解説
体温が上昇すると液体の粘性は一般に低下し、血液でも血漿粘度の低下や赤血球変形能の改善により見かけ粘性は下がる。よって粘性率は増加しない。
血液は非ニュートン流体で、せん断速度が増加すると赤血球が配向・変形し、ずり薄化により見かけ粘性は低下する。したがって粘性率は増加しない。
ヘマトクリット値(血球容積比)が上昇すると、懸濁粒子数の増加により流動抵抗が増し、見かけ粘性は上昇する。よって粘性率は増加する(正しい)。
低せん断域で起こる赤血球の連銭(ルーロ)形成は、赤血球同士の凝集により流動抵抗を増加させ、見かけ粘性を上昇させる。したがって粘性率は増加する(正しい)。
集軸効果では赤血球が流れの中心へ移動し、血管壁近傍に血漿のみの層(セルフリー層)が形成されるため、全体としての見かけ粘性は低下する。よって粘性率は増加しない。
解説を表示するにはログインが必要です。ログインすると無料枠(1日5問)をご利用いただけます。
無料プランでは解説を1日5問まで表示できます。解説を表示すると残り回数が消費されます。
今日: 回 | 残り 回
本日の無料枠を使い切りました。プレミアム登録で無制限にご利用いただけます。
解説
高血圧の診断は、原則として診察室血圧で収縮期140 mmHg以上または拡張期90 mmHg以上のいずれかを満たすかどうかで判定する(家庭血圧や24時間自由行動下血圧でも同様にSBP/DBPの基準がある)。診断は血圧が変動しやすいことから、日内・日差や白衣現象を考慮し、複数回・複数日・異なる環境での測定結果を総合して行う。治療は原則、生活習慣の修正(食塩制限[目安6 g/日未満]、減量、有酸素運動、節酒、禁煙など)をまず行い、重症度や総合的心血管リスクにより薬物療法を追加・開始する。本態性高血圧は高血圧の大部分(90%前後)を占めるが、若年者や経過・所見から疑う場合は腎実質性・腎血管性、内分泌性(原発性アルドステロン症、褐色細胞腫、クッシング、甲状腺機能異常等)、大動脈縮窄などの二次性高血圧を念頭に精査する。以上から、若年者高血圧で基礎疾患の存在を考慮するという選択肢が正しい。
選択肢別解説
$誤り。高血圧の診断は平均動脈圧(MAP)や「平均血圧」の値で決めるのではなく、収縮期血圧(SBP)と拡張期血圧(DBP)の閾値で判定する(診察室でSBP\ge 140 mmHgまたはDBP\ge 90 mmHgなど)。家庭血圧 \cdot ABPMでも基準はSBP/DBPで規定されており、MAPで診断を下すことは一般的でない。$
誤り。血圧は変動が大きく、白衣高血圧や仮面高血圧もあるため、1回の測定で診断は確定しない。複数回・複数日にわたる測定(診察室、家庭血圧、必要に応じABPM)を総合して診断する。
誤り。初期対応は生活習慣の修正(食塩制限、体重管理、運動、節酒、禁煙等)を基本とし、重症度・合併症・総リスクに応じて薬物療法を併用・開始する。重症高血圧や高リスクでは早期に薬物療法を要するが、「まず薬物治療を開始する」と一般化するのは不適切。
誤り。本態性(一次性)高血圧は高血圧患者の大多数を占め、概ね90%前後とされる。「約半数」という記載は過小評価で不正確。
正しい。若年者の高血圧では二次性高血圧の可能性(腎実質性・腎血管性、原発性アルドステロン症、褐色細胞腫、クッシング症候群、甲状腺疾患、大動脈縮窄など)を考慮し、原因検索を行うことが重要である。
解説を表示するにはログインが必要です。ログインすると無料枠(1日5問)をご利用いただけます。
無料プランでは解説を1日5問まで表示できます。解説を表示すると残り回数が消費されます。
今日: 回 | 残り 回
本日の無料枠を使い切りました。プレミアム登録で無制限にご利用いただけます。
解説
弾性域ではフックの法則によりひずみは応力に比例し、その比例係数の逆数がヤング率である($\varepsilon = \sigma / E$)。したがってヤング率が大きいほど同じ応力で生じるひずみは小さく、選択肢1は誤り。生体軟組織は水分に富み体積変化しにくいため非圧縮近似($\nu \approx 0.5$)がよく用いられる。筋は粘弾性体で、荷重・除荷で応力–ひずみ曲線が一致せずヒステリシスを示す。筋は腱より剛性が低く、同一引張応力でより大きく変形する。血液の動的粘度は水より大きいが依然として小さく、軟組織の実効粘性(粘弾性モデルで表す粘性要素)より一般に小さいと考えられ、選択肢5は正しい。
選択肢別解説
誤り。ヤング率 $E$ は応力–ひずみ曲線の傾きで、$\varepsilon = \sigma / E$。したがって $E$ が大きい(硬い)ほど、同じ応力 $\sigma$ に対して生じるひずみ $\varepsilon$ は小さい。選択肢は「ひずみが大きい」としており逆の記述。
正しい。生体軟組織は水分が多く体積変化が極めて小さいため、非圧縮体近似が成り立ち、ポアソン比は理論上の非圧縮値 $\nu=0.5$ に近い(実測でも概ね 0.45〜0.5 程度)。
正しい。筋組織は粘弾性体であり、荷重と除荷で応力–ひずみ関係が一致せずエネルギー損失を伴うヒステリシスループが現れる。これは粘性成分による時間依存(履歴依存)性に起因する。
正しい。腱はコラーゲン線維が緻密で高い剛性を示すのに対し、筋はよりコンプライアンスが高い。よって同一の引張応力に対して筋の方がひずみ(変形割合)が大きい。
正しい。血液の動的粘度は数 mPa\,s 程度(せん断速度依存の非ニュートン性あり)で、粘弾性体として記述される生体軟組織の実効粘性パラメータは一般にこれより大きく見積もられる。よって「血液の粘性係数は生体軟組織に比べて小さい」は適切。ただし比較はモデル依存であることに留意する。
解説を表示するにはログインが必要です。ログインすると無料枠(1日5問)をご利用いただけます。
無料プランでは解説を1日5問まで表示できます。解説を表示すると残り回数が消費されます。
今日: 回 | 残り 回
本日の無料枠を使い切りました。プレミアム登録で無制限にご利用いただけます。
解説
観血式血圧計の測定系は、カテーテル・延長チューブ・フラッシュ装置・トランスデューサからなる力学系であり、固有振動数と減衰(ダンピング)の影響を強く受ける。誤差を増やす要因は、圧力伝達を阻害したり静水圧差やゼロ点ドリフトを生じさせるもの(凝固、気泡、トランスデューサ高さずれ、ウォームアップ不足など)である。一方、カテーテルを短く硬くすることは系のコンプライアンスを下げ固有振動数を高め、波形歪みやオーバー/アンダーシュートを抑えるため、測定誤差を減少させる。したがって「短くて硬い材質のカテーテルの使用」は“誤差を増加させない要因”に該当する。
選択肢別解説
カテーテル内で血液が凝固すると内腔が狭窄・閉塞し、圧力伝達が遅延・減衰(過減衰)して収縮期血圧は低め、拡張期は高めに出るなどの系統誤差が増える。臨床では持続フラッシュやヘパリン化生食で凝固を防ぐ。よって誤差は増加する要因である。
電源投入直後はストレインゲージ式トランスデューサの温度・ゼロ点・感度が安定せず、ゼロ点ドリフトや感度変化が起こりやすい。ゼロ補正も不十分になり得るため、直後の測定開始は誤差増大につながる。
トランスデューサの高さが基準(右心房レベル)からずれると静水圧差がそのままオフセット誤差となる。高さ差hに対し圧力差は $\Delta P=\rho g h$ で、10 cmの高さ差は約7.4~7.5 mmHgの誤差(1 cmH2O$\approx$0.74 mmHg)を生む。よって誤差増大要因である。
短くて硬いカテーテルはコンプライアンスを下げ固有振動数を高め、適正な減衰比の下で波形の歪みや共振・オーバーシュートを抑えられるため、測定誤差を減少させる要因である。設問は「誤差を増加させない要因」を問うため本肢が該当する。
カテーテル内への気泡混入は系のコンプライアンスを増大させ、固有振動数を低下させるとともに減衰特性を変化させ、波形の振幅低下や位相遅れなどの歪みを招く。結果として収縮期低め・拡張期高めなどの誤差が増加する。
解説を表示するにはログインが必要です。ログインすると無料枠(1日5問)をご利用いただけます。
無料プランでは解説を1日5問まで表示できます。解説を表示すると残り回数が消費されます。
今日: 回 | 残り 回
本日の無料枠を使い切りました。プレミアム登録で無制限にご利用いただけます。