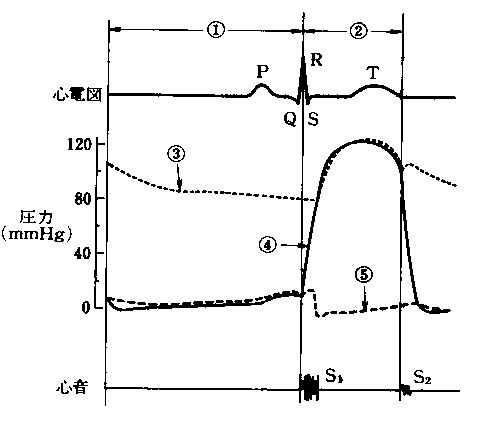臨床工学技士問題表示
臨床工学技士国家試験
解説
超音波画像計測では、生体軟部組織中の音速は代表値として約1,540 m/s(おおむね1,500〜1,560 m/s)が用いられ、これを前提に往復時間から距離を算出する。超音波は周波数が高いほど吸収・散乱による減衰が大きく、到達深度は浅くなる一方で距離分解能は向上する。画像化の基本原理は、音響インピーダンス(密度×音速)が異なる組織境界で生じる反射エコーを利用する点にある。臨床的には、心エコーで心室壁厚などの形態計測が可能であり、また血管内エコー(IVUS)により血管内腔から断面像を取得して血管壁やプラークの評価ができる。
選択肢別解説
誤り。生体軟部組織中の音速は約1,540 m/sが代表値であり、約340 m/sは空気中の音速である。超音波診断装置はこの代表値を用いて距離(深さ)を計算するため、340 m/sとする記述は不正確。
誤り。超音波の減衰は周波数にほぼ比例して大きくなる。周波数が高いほど吸収・散乱が増し減衰が大きく、深部まで届きにくい(逆に分解能は向上する)。
正しい。超音波は音響インピーダンスが異なる境界で一部が反射し、その反射強度はインピーダンス差が大きいほど大きくなる。この反射エコーの時間情報から深さを求め、画像を構成する。
正しい。心エコーでは2D像やMモードを用いて、左室中隔(IVS)や後壁(PW)の厚さを拡張末期など規定のタイミングで測定できる。心室壁厚や収縮の評価に日常的に用いられる。
正しい。血管内エコー(IVUS)では、超音波トランスデューサを先端に備えたカテーテルを血管内に挿入し、内腔から血管の断面像を取得できる。これにより内膜やプラークの性状・分布を詳細に評価可能。
解説を表示するにはログインが必要です。ログインすると無料枠(1日5問)をご利用いただけます。
無料プランでは解説を1日5問まで表示できます。解説を表示すると残り回数が消費されます。
今日: 回 | 残り 回
本日の無料枠を使い切りました。プレミアム登録で無制限にご利用いただけます。
解説
パルスオキシメータは拍動性動脈血中のオキシヘモグロビンと脱酸素ヘモグロビンの吸光度差からSpO₂を算出する。酸素解離曲線は高体温やアシドーシスで右方移動し、同一のPaO₂でもSaO₂(=SpO₂に相当する実際の飽和度)は低下する。色素(インドシアニングリーンなど)は使用波長帯で吸収を持ち、測定に影響する。一酸化炭素ヘモグロビン(COHb)は2波長式ではHbO₂と識別できず、SpO₂を実際より高く表示させる誤差要因である。末梢循環不全では脈動成分が弱くなり信号対雑音比が低下するため、測定の信頼性が落ちる。
選択肢別解説
正しい。高体温はヘモグロビンの酸素親和性を低下させ、酸素解離曲線を右方移動させる。そのため同じPaO₂でもSaO₂は低くなり、SpO₂も低下しうる。
正しい。アシドーシス(pH低下)はボーア効果により酸素解離曲線を右方移動させ、同一PaO₂でのSaO₂が低下するため、SpO₂も低めに出る。
誤り。インドシアニングリーンなどの静注色素はパルスオキシメータの測定波長帯で吸収を持ち、光学的計測に干渉して一過性のSpO₂低下などの影響を与える。
誤り。一酸化炭素ヘモグロビン(COHb)はオキシヘモグロビンと類似した吸光特性を示し、2波長式では識別できないためSpO₂を実際より高く表示させる測定誤差の原因となる。
正しい。末梢循環不全や低灌流では拍動性信号が弱く、動脈成分の抽出が難しいためアーチファクトが増え、測定値の信頼性が低下する。
解説を表示するにはログインが必要です。ログインすると無料枠(1日5問)をご利用いただけます。
無料プランでは解説を1日5問まで表示できます。解説を表示すると残り回数が消費されます。
今日: 回 | 残り 回
本日の無料枠を使い切りました。プレミアム登録で無制限にご利用いただけます。
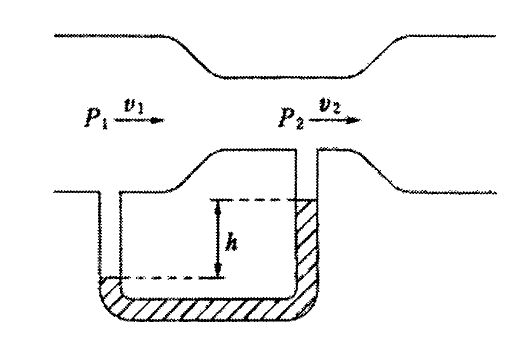
解説
本問は生体の機械的特性と粘弾性モデルの基礎理解を問う。血漿はずり速度によらず粘度がほぼ一定であるためニュートン流体として近似できる。一方、血液全体は血球の凝集・変形により非ニュートン性(主にせん断薄化)を示す。水分を多く含む軟組織は実質的にほぼ非圧縮性で、ポアソン比は0.5近傍となる。線形弾性ではフックの法則 $\sigma=E\varepsilon$ より、同じ応力下でヤング率が大きいほどひずみは小さい。粘弾性モデルでは、マックスウェルモデルはばねとダンパーの直列接続、フォークト(ケルビン–フォークト)モデルが並列接続である。組織構成では、膠原線維は剛性を高め伸展性を低下させ、エラスチンが伸びやすさに寄与する。
選択肢別解説
正しい。血漿はずり速度に対する粘度がほぼ一定で、ニュートン流体として扱える。対照的に、血液全体は血球成分の影響で非ニュートン性(せん断薄化)を示す。
誤り。水を多く含む生体軟組織は実質的に非圧縮性でポアソン比は0.5付近となる。「ほぼ1」は物理的に不適切で、線形等方弾性体では $\nu\le 0.5$ が安定条件である。
誤り。フックの法則 $\sigma=E\varepsilon$ より、同じ応力 $\sigma$ では $\varepsilon=\sigma/E$。したがってヤング率 $E$ が大きいほどひずみは小さく、変形しにくい。
誤り。マックスウェルモデルは弾性要素(ばね)と粘性要素(ダンパー)の直列接続。並列接続なのはフォークト(ケルビン–フォークト)モデルである。
誤り。膠原線維は引張剛性が高く、組織のヤング率を増加させるため伸展性(伸びやすさ)は低下する。伸展性の増大にはエラスチンの寄与が大きい。
解説を表示するにはログインが必要です。ログインすると無料枠(1日5問)をご利用いただけます。
無料プランでは解説を1日5問まで表示できます。解説を表示すると残り回数が消費されます。
今日: 回 | 残り 回
本日の無料枠を使い切りました。プレミアム登録で無制限にご利用いただけます。
解説
パルスオキシメータは赤色光と赤外光の2波長で動脈血中の酸素化ヘモグロビン割合(SpO2)を推定する。ヘモグロビンの酸素解離曲線は体温上昇やアシドーシス(pH低下)で右方移動し、同じ動脈酸素分圧(PaO2)でも酸素飽和度(SaO2/SpO2)は低下するため、これらは正しい記述となる。一方、インジゴカルミンやメチレンブルーなどの色素は測定波長の吸収に影響し測定誤差を生じるため「影響しない」は誤りである。また、CO-Hbは2波長式ではオキシヘモグロビンとして扱われやすく、実際より高めに表示されうるため「影響しない」は誤り。さらに、末梢循環不全などで拍動成分が十分に得られないと演算が不安定化し誤差や測定不能が生じるため、その指摘は正しい。
選択肢別解説
体温上昇はヘモグロビンの酸素親和性を低下させ、酸素解離曲線を右方移動させる。結果として、同じPaO2でも酸素飽和度(SaO2/SpO2)は低くなるため正しい。
アシドーシス(pH低下)はBohr効果により酸素解離曲線を右方移動させ、同じPaO2でも酸素飽和度が低下する。したがって正しい。
インジゴカルミン(いわゆるインジゴブルー)やメチレンブルー、インドシアニングリーンなどの色素は、パルスオキシメータが用いる赤色・赤外光の吸収に影響し、一過性のSpO2低下表示などの測定誤差を招く。よって「影響しない」は誤り。
CO-Hbは2波長式パルスオキシメータではオキシヘモグロビンと区別しにくく、SpO2を実際より高値に表示させる要因となる。したがって「影響しない」は誤り。
パルスオキシメータは拍動成分(動脈血の脈動)を利用するため、末梢循環不全・低灌流・重度血管収縮などで拍動検出が不良だと演算が不安定となり、誤差増大や測定不能を来す。よって正しい。
解説を表示するにはログインが必要です。ログインすると無料枠(1日5問)をご利用いただけます。
無料プランでは解説を1日5問まで表示できます。解説を表示すると残り回数が消費されます。
今日: 回 | 残り 回
本日の無料枠を使い切りました。プレミアム登録で無制限にご利用いただけます。
解説
音波は空気や水などの流体中では媒質の疎密(圧縮・膨張)が伝わる縦波であり、横波ではない。音速は媒質固有の物性(弾性と密度)により決まり、気体では $V=\sqrt{\gamma P/\rho}$(等温近似でなく断熱過程を仮定)などで表され、気体の種類に依存する。ドプラ効果は音源と観測者の相対運動によって観測周波数が変化する現象である。水中および生体軟部組織中の音速はおよそ 1500 m/s(実務上は軟部組織で約 1540 m/s を採用)で妥当である。音の強さ(音響インテンシティ)は振幅(音圧)の二乗に比例し、$I=p_{\mathrm{rms}}^2/(\rho c)$ などで表される。従って正しいのは3と4である。
選択肢別解説
誤り。空気や水などの流体中の音波は縦波(粒子の振動方向と進行方向が同じ)である。流体にはせん断復元力がないため、横波は通常伝わらない。
誤り。音速は媒質に依存し、気体では $V=\sqrt{\gamma P/\rho}$ などで表される。比熱比 $\gamma$ や密度 $\rho$ は気体の種類で異なるため、音速も異なる。
正しい。音源と観測者の相対運動により観測される周波数が変化する現象がドプラ効果である(近づくと高く、遠ざかると低くなる)。
正しい。水中の音速は約 1480~1530 m/s、生体軟部組織は実務上約 1540 m/s とされ、概ね「約 1500 m/s」で妥当である。
誤り。音の強さは振幅(音圧)の二乗に比例する。例えば $I=p_{\mathrm{rms}}^2/(\rho c)$ で表され、振幅が大きいほど強さは増大する。
解説を表示するにはログインが必要です。ログインすると無料枠(1日5問)をご利用いただけます。
無料プランでは解説を1日5問まで表示できます。解説を表示すると残り回数が消費されます。
今日: 回 | 残り 回
本日の無料枠を使い切りました。プレミアム登録で無制限にご利用いただけます。
解説
遠心ポンプは羽根車の遠心力で血液にエネルギーを与える非閉塞型ポンプで、流量は回転数だけでなく前負荷(流入量)や後負荷(回路抵抗・動脈圧)に強く依存する。したがって回転数を一定にしても流量は一定にならず、流量計で監視しながら回転数を調整する必要がある(「回転数が一定なら流量一定」は誤り)。また遠心ポンプはローラーポンプと異なりチューブを完全閉塞しない構造のため、使用前のオクルージョンテストは不要である(「オクルージョンテストを必要とする」は誤り)。一方、低流量域では前後負荷変動の影響が相対的に大きく微調整が難しい、回転停止・低回転時は動脈圧による逆流が起こり得る、血液粘性(ヘマトクリットや温度)によりポンプ特性・回路圧損が変動する、などは正しい特性である。
選択肢別解説
正しい。遠心ポンプは流量が前後負荷に依存するため、低流量域ではわずかな回路抵抗や静脈還流の変化で流量が大きく変動しやすく、安定した微調整が難しい。実運用では流量計で監視しながら回転数を細かく調整する必要がある。
正しい。遠心ポンプは非閉塞型であり、回転停止または低回転時には動脈側圧に押し戻されて回路内で逆流が生じ得る。停止前の送血ラインのクランプなど逆流防止操作が必須である。
正しい。血液粘性はヘマトクリットや温度に依存し、回路圧損やポンプのQ–H特性に影響する。粘性が高いほど同一回転数でも得られる流量は低下しやすい。
誤り。遠心ポンプの流量は回転数だけでなく後負荷(動脈圧・回路抵抗)や前負荷(静脈還流)に左右されるため、回転数一定でも流量は一定にならない。一定流量を維持するには流量計で監視し回転数を適宜調整する必要がある。
誤り。オクルージョンテストはローラーポンプでチューブの圧閉塞度を調整・確認する手技であり、非閉塞型の遠心ポンプでは実施不要である。
解説を表示するにはログインが必要です。ログインすると無料枠(1日5問)をご利用いただけます。
無料プランでは解説を1日5問まで表示できます。解説を表示すると残り回数が消費されます。
今日: 回 | 残り 回
本日の無料枠を使い切りました。プレミアム登録で無制限にご利用いただけます。
解説
循環障害の基本は、局所で形成された血栓による閉塞(血栓症)と、他部位で生じた塞栓子が血流に乗って移動し閉塞する(塞栓症)を区別することにある。動脈硬化プラーク(粥腫)の破綻はその場で血小板凝集とフィブリン形成を促し、局所の血栓性閉塞(血栓症)を起こすため、これを塞栓症と呼ぶのは誤り。虚血が強く持続し細胞壊死に至った状態は梗塞であり、側副血行が発達していると虚血が緩和され梗塞範囲は小さくなる。肺塞栓症は多くが下肢・骨盤の深部静脈血栓(DVT)由来で、粥状硬化(アテローム硬化)は内腔狭窄の代表的原因である。
選択肢別解説
誤り。動脈硬化の粥腫が破綻すると、その部位で血小板凝集と凝固が進み血栓が形成され、局所で血管内腔を閉塞する。これは血栓症であり、塞栓症(他所で生じた塞栓子が血流に乗って飛来して閉塞する現象)とは定義が異なる。
正しい。血流遮断により酸素・栄養が供給されず、不可逆的な細胞壊死に至った状態を梗塞と呼ぶ。冠動脈閉塞の心筋梗塞や脳動脈閉塞の脳梗塞が代表例である。
正しい。側副血行路が発達していると、主幹動脈閉塞時でも代替経路から血流が供給され、虚血が緩和されるため壊死(梗塞)範囲は縮小する。
正しい。肺塞栓症の主要因は下肢や骨盤内の深部静脈血栓(DVT)が遊離して肺動脈を閉塞するもので、臨床でもDVT予防・検出がPE対策の要となる。
正しい。粥状硬化(アテローム硬化)は内膜に脂質沈着と線維化を伴うプラークを形成し、内腔狭窄やプラーク破綻に伴う血栓形成の基盤となる。
解説を表示するにはログインが必要です。ログインすると無料枠(1日5問)をご利用いただけます。
無料プランでは解説を1日5問まで表示できます。解説を表示すると残り回数が消費されます。
今日: 回 | 残り 回
本日の無料枠を使い切りました。プレミアム登録で無制限にご利用いただけます。