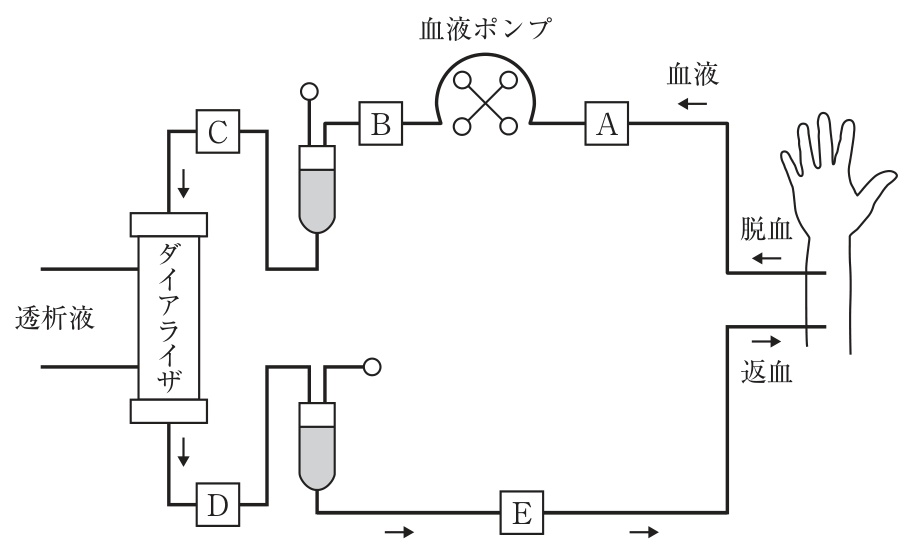臨床工学技士問題表示
臨床工学技士国家試験
解説
IABP(大動脈内バルーンパンピング)は拡張期にバルーンを拡張して大動脈拡張期圧を上げ、冠動脈灌流を増加(diastolic augmentation)させ、収縮期直前に速やかに収縮して左室の駆出に対する抵抗(後負荷)を減少(systolic unloading)させる補助循環法である。心拍出量の増加は限定的で、正常心機能と同等の心拍出量を単独で得ることはできない。人工心肺(CPB)中の非拍動流に対し、IABPの拡張・収縮に同期させることで拍動性の圧・流を付加できる。禁忌としては大動脈弁閉鎖不全や大動脈解離などの絶対禁忌に加え、出血性素因や血液凝固異常は一般に相対的禁忌とされる。合併症としては下肢虚血をはじめ、腎・腸管など主要分枝の血行障害、出血、感染などが知られている。
選択肢別解説
誤り。IABPは収縮期直前にバルーンを縮小させて左室の駆出抵抗を下げ、左室後負荷を軽減する(systolic unloading)。したがって後負荷を『増大』させる効果はない。
誤り。IABPは圧補助であり、単独で得られる心拍出量増加は限定的(一般に正常心機能の約15〜20%程度の補助)で、正常な心臓と同等の心拍出量を得ることはできない。
正しい。人工心肺の非拍動流に対し、IABPの拡張期膨張・収縮期縮小を同期させることで動脈圧波形と流量に拍動性を付加でき、拍動流(拍動性循環)を得るために用いられる。
正しい。血液凝固異常や出血性素因を有する患者では、大口径の動脈内カテーテル留置により出血合併症のリスクが高く、一般にIABPの使用は禁忌(少なくとも相対的禁忌)と扱われるため、適応は慎重に検討する。
正しい。IABPの合併症として、挿入側下肢の虚血を含む動脈主要分枝(腎動脈、腸間膜動脈、腸骨・大腿動脈など)の血行障害がある。ほかに出血、感染、塞栓、血管損傷などが知られる。
解説を表示するにはログインが必要です。ログインすると無料枠(1日5問)をご利用いただけます。
無料プランでは解説を1日5問まで表示できます。解説を表示すると残り回数が消費されます。
今日: 回 | 残り 回
本日の無料枠を使い切りました。プレミアム登録で無制限にご利用いただけます。
解説
乳児・新生児では基礎代謝量と酸素消費量が高く、体表面積当たりの必要心拍出量(=体外循環灌流量の目安)も成人より高めに設定するのが一般的である。チアノーゼ性心疾患では体循環から肺循環への側副血行路(例:大動脈肺動脈側副血行)が発達し、体外循環中に体循環側から肺へ血液が逃げやすくなるため、同じ灌流圧を保ち全身の酸素送達を確保するには非チアノーゼ性よりも総灌流量を多めに設定するのが妥当である。一方,小児開心術では正確な低流量制御と逆流対策の容易さからローラポンプが選択されることが多く、遠心ポンプの使用率は成人ほど高くない。さらに、乳児は循環血液量が小さく人工心肺回路の充填量比率が大きいため希釈が著明となり、無輸血手術は成人より困難である。灌流圧目標も乳児の生理的動脈圧に合わせて成人より低めで管理するのが一般的で、単に流量を増やしても動脈圧は大きく上がらず、必要時は血管作動薬を用いて調整する。
選択肢別解説
正しい。チアノーゼ性心疾患では体循環から肺循環への側副血行路が発達し、体外循環中に系統血圧が下がりやすく全身灌流が不足しやすい。側副血行への“逃げ”を見越して、非チアノーゼ性より総灌流量を多めに設定して全身の酸素送達を確保する。
誤り。乳児は酸素消費量が高く、体表面積当たりの必要灌流量(流量指数)は成人より高めに設定するのが一般的である。従って少なく設定するのは不適切。
誤り。小児開心術では、きわめて低い流量域での安定性・正確な拍動量管理・逆流防止の容易さなどの理由からローラポンプが多用され、遠心ポンプの使用率は成人ほど高くない。遠心ポンプは低流量域での安定性や後負荷依存性、逆流対策などに留意を要する。
誤り。乳児は循環血液量が少なく、人工心肺回路の充填量が相対的に大きくなるため希釈が顕著でHb低下を招きやすい。これにより無輸血手術(無輸血充填)は成人より難易度が高い。血液管理や低体温・低流量戦略など多くの配慮が必要。
誤り。乳児の目標灌流圧は生理的な動脈圧水準に合わせ成人より低めに管理するのが一般的である。流量を増やしても動脈圧は大きく上がらず、圧を上げたい場合は血管収縮薬などで対応する。
解説を表示するにはログインが必要です。ログインすると無料枠(1日5問)をご利用いただけます。
無料プランでは解説を1日5問まで表示できます。解説を表示すると残り回数が消費されます。
今日: 回 | 残り 回
本日の無料枠を使い切りました。プレミアム登録で無制限にご利用いただけます。
解説
体外循環での血液希釈は、ヘマトクリットと血漿タンパクを下げて血液粘度を低下させることで、回路内・微小循環の流れを改善し、ポンプ・酸素ator・狭窄部でのせん断応力を減らす。その結果、機械的損傷に伴う溶血が抑えられる点が主な利点である。一方で、赤血球と血漿タンパクの希釈により酸素運搬能と膠質浸透圧は低下し、浮腫や組織酸素供給の不利を招き得るため、適正な希釈範囲の管理が重要となる。代謝面では、流れの改善により組織低灌流が是正されれば代謝性アシドーシスの改善方向に働くが、代謝性アルカローシスの軽減という直接的効果は期待されない。
選択肢別解説
正しい。血液希釈によりヘマトクリットが低下すると血液粘度が下がり、回路・末梢でのせん断応力が減少する。これにより機械的溶血(ポンプ、酸素ator、狭小部通過時の赤血球損傷)が軽減される。適正範囲での希釈管理が前提である。
誤り。血液希釈はヘマトクリット低下を通じて血液粘度を低下させる。よって粘性の『増加』は利点ではなく、実際には減少が得られる。
誤り。赤血球・ヘモグロビンの希釈により動脈血酸素含量(CaO2)は低下し、血液自体の酸素運搬能は低下する。体外循環ではポンプ流量で酸素供給量(DO2)を補い得るが、『運搬能の増加』とはいえない。
誤り。血漿タンパクが希釈されるため膠質浸透圧は低下し、組織間質への水移動が増えて浮腫のリスクとなる。上昇は起こらない(コロイド製剤で補填しない限り)。
誤り。血液希釈の主効果は流動性改善であり、低灌流の是正によって代謝性アシドーシスが改善し得る。一方、代謝性アルカローシスの軽減を直接もたらす根拠はない。
解説を表示するにはログインが必要です。ログインすると無料枠(1日5問)をご利用いただけます。
無料プランでは解説を1日5問まで表示できます。解説を表示すると残り回数が消費されます。
今日: 回 | 残り 回
本日の無料枠を使い切りました。プレミアム登録で無制限にご利用いただけます。
解説
フィンガポンプはペリスタルティック(蠕動)方式で、並列配置されたフィンガがチューブを順に圧迫して送液するため、選択肢1は正しい。滴下センサは一般に赤外光(IR)で滴下を検出するため、可視光を用いるとする選択肢2は不適切。シリンジポンプでもシリンジの固定不良やクランプ開放など条件が整うと落差により薬液が流出するフリーフローが起こり得るため、発生しないと断定する選択肢3は誤り。微少流量や高精度が求められる投与は脈動が小さく制御精度の高いシリンジポンプが適しており、フィンガポンプが適するという選択肢4は誤り。PVC(塩化ビニル)への吸着性が問題となる薬剤(例:ニトログリセリン、インスリンなど)ではチューブへの吸着を回避しやすいシリンジポンプの使用が推奨されるため、選択肢5は正しい。
選択肢別解説
正しい。フィンガポンプはペリスタルティック方式で、複数のフィンガがチューブを上流から下流へ順次圧迫して薬液を送り出す。チューブ内腔の変形で送液するため、薬液はポンプ機構に直接触れない。
誤り。滴下センサは一般に赤外LEDとフォトセンサを用いて滴の通過を検出する。可視光より外乱の影響を受けにくい赤外光が用いられるのが標準的であり、「可視光線が用いられる」との断定は不正確。
誤り。フリーフロー(ポンプ停止中に落差で薬液が流出する現象)は、シリンジの固定不良やアンチフリーフロー機構未作動、ストッパ外し・クランプ開放などでシリンジポンプでも起こり得る。多くの機種は防止機構を備えるが、発生しないと断言はできない。
誤り。フィンガポンプは構造上の脈動とチューブ弾性の影響で微少流量域の精度が劣り、一般に定常精度は±5〜10%程度(機種・条件に依存)。シリンジポンプはピストン駆動で微少流量の制御に優れ、±2〜3%程度の精度が期待でき、微量投与に適する。
正しい。PVC(塩化ビニル)製輸液ラインにはニトログリセリンやインスリンなどの吸着が生じやすい。シリンジ(多くはガラスやPP/PC)を用いるシリンジポンプは吸着影響を低減しやすく、これら薬剤の投与に適する(臨床では非PVCラインの使用も併用される)。
解説を表示するにはログインが必要です。ログインすると無料枠(1日5問)をご利用いただけます。
無料プランでは解説を1日5問まで表示できます。解説を表示すると残り回数が消費されます。
今日: 回 | 残り 回
本日の無料枠を使い切りました。プレミアム登録で無制限にご利用いただけます。