臨床工学技士問題表示
臨床工学技士国家試験
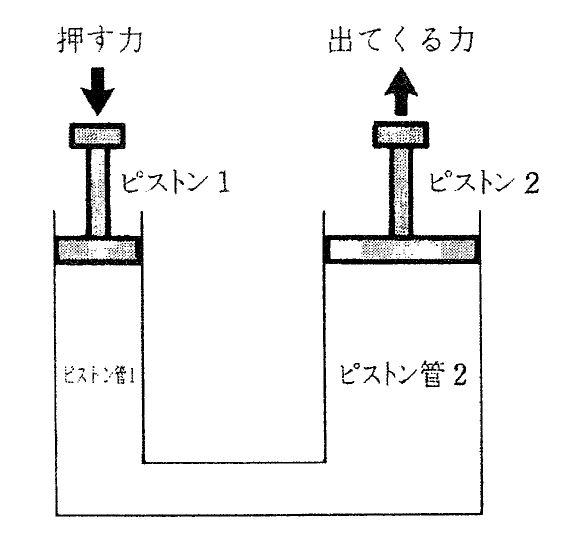
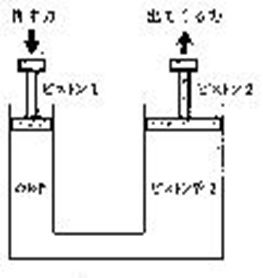
解説
超音波は可聴音より高周波で、軟部組織中では縦波(疎密波)として伝搬する。指向性は周波数が高いほど高くなり、ビームは狭くなる。反射は主として音響インピーダンス差で決まり、生体内の組織境界(例:筋−脂肪、軟部−骨、組織−空気)で顕著に起こる。音速は媒質の弾性率と密度に依存し、空気(約331〜346 m/s)よりも水や軟部組織・筋(約1540〜1580 m/s)の方が大きい。減衰は生体軟部組織で周波数にほぼ比例(おおむね0.5〜1 dB/cm/MHz)し、高周波ほど減衰が大きく深達性は低下する一方、分解能は向上する。以上より、正しいのは「空気に比べて筋組織での音速が大きい」と「周波数が高いほど減衰しやすい」である。
選択肢別解説
誤り。生体の軟部組織(液体に近い性質)中での超音波は縦波(疎密波)として伝搬する。横波(せん断波)は軟部組織ではほぼ伝搬しない(骨など固体では横波が生じ得るが、本設問の「生体中」一般には当てはまらない)。
誤り。指向性は周波数が高いほど高くなる。ビーム幅はおおむね波長に比例して狭くなり(ビーム幅 ∝ λ/D)、超音波(高周波)は可聴音より指向性が高い。
誤り。反射は主として音響インピーダンス差で決まり、組織境界でしばしば強く起こる。反射係数は $R=((Z_2-Z_1)/(Z_2+Z_1))^2$ で表され、例えば空気と組織の境界では大きなインピーダンス差により強い反射となる。可聴音より反射しにくいとはいえない。
正しい。空気中の音速は約331〜346 m/s(条件に依存)に対し、筋組織は約1580 m/s、軟部組織では約1540 m/sであり、生体組織の方が大きい。
正しい。生体軟部組織における減衰係数は周波数にほぼ比例し(代表値で約0.5〜1 dB/cm/MHz)、周波数が高いほど減衰しやすい。そのため高周波は分解能が高いが深部への到達性は低下する。
解説を表示するにはログインが必要です。ログインすると無料枠(1日5問)をご利用いただけます。
無料プランでは解説を1日5問まで表示できます。解説を表示すると残り回数が消費されます。
今日: 回 | 残り 回
本日の無料枠を使い切りました。プレミアム登録で無制限にご利用いただけます。
解説
生体内の物質移動には、拡散、濾過、浸透(浸透圧に伴う水移動)、能動輸送などがある。肺胞—毛細血管間のガス(O2・CO2)交換は分圧勾配に基づく単純拡散で説明でき、Fickの法則 $J=-D\,\frac{dC}{dx}$ の関係に従う。細胞膜ではNa\+/K\+-ATPアーゼがATPエネルギーを用いてNa\+を外へ、K\+を内へ輸送する能動輸送を担う。腎糸球体ではサイズ・電荷選択性をもつ濾過障壁により、グルコースのような低分子は自由濾過され、その後近位尿細管で再吸収される。一方、血漿タンパク質は毛細血管壁をほとんど透過せず、むしろ血漿側の膠質浸透圧を形成して水の移動を規定するため、「血漿タンパクが浸透圧によって移動する」という記述は誤りである(誤っている選択肢は4)。
選択肢別解説
正しい。酸素は肺胞気と毛細血管血との分圧差に従って肺胞—毛細血管膜を単純拡散で通過する。肺胞壁は薄く表面積も大きいため、Fickの法則 $J=-D\,\frac{dC}{dx}$ に従う拡散が効率よく起こる。
正しい。二酸化炭素も分圧勾配に基づく単純拡散で肺胞—血液間を移動する。CO2は血中で重炭酸イオンとして存在する割合が高いが、ガス交換の場面ではCO2分子として拡散により放出・取り込みが行われる。CO2はO2より拡散能が高い。
正しい。細胞内のNa\+はNa\+/K\+-ATPアーゼによりATPを消費して濃度勾配に逆らって細胞外へ汲み出される(3Na\+排出/2K\+取り込み)。これは典型的な一次性能動輸送である。
誤り。浸透圧(膠質浸透圧)は主に血漿タンパク質が血漿側に保持されることで生じ、水の移動を規定する。血漿タンパク質自体は毛細血管壁をほとんど透過せず、「浸透圧によって毛細血管壁を移動する」という表現は不適切である。
正しい。グルコース(分子量約180)は糸球体で自由濾過される低分子であり、その後、近位尿細管で再吸収される。糸球体濾過障壁はサイズ・電荷選択性によりアルブミンなどの高分子タンパク質を主として通さない。
解説を表示するにはログインが必要です。ログインすると無料枠(1日5問)をご利用いただけます。
無料プランでは解説を1日5問まで表示できます。解説を表示すると残り回数が消費されます。
今日: 回 | 残り 回
本日の無料枠を使い切りました。プレミアム登録で無制限にご利用いただけます。