臨床工学技士問題表示
臨床工学技士国家試験
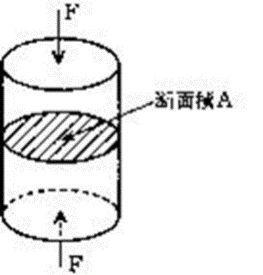
解説
$生体組織の電気特性は、主に細胞膜がコンデンサとして振る舞うことに依存する。低周波では細胞膜のリアクタンスが大きく、電流は主に細胞外を流れるが、周波数が上がると膜リアクタンスが低下して細胞内にも電流が流れやすくなるため、見かけの導電率は一般に増加する。したがって「周波数の増加とともに導電率は低下する」は誤りであり、これが正答である。骨格筋は繊維配向に沿った軸方向と横方向で電気特性が異なるため大きな異方性を示す。血液は電解質を多く含むため臓器実質(例:肝)より導電率が高い。細胞膜の比容量はおおむね 1 μF/cm^2 程度であり、周波数が高い電流ほど神経 \cdot 筋の興奮は起こりにくく、電気的感受性は低下する。$
選択肢別解説
正しい。骨格筋は筋線維が一方向に配列した構造を持ち、電流の流れる方向(筋線維と平行か垂直か)で抵抗・インピーダンスが大きく異なるため、電気的異方性が大きい。
正しい。血液は電解質を多く含む導電性の高い体液であり、実質臓器である肝臓よりも一般に導電率が高い。肝臓では細胞膜が多数存在し低周波域でインピーダンスが増すため、血液より導電率は低くなる。
誤り。周波数が増加すると細胞膜の容量性リアクタンスが低下し、電流は細胞内にも流れやすくなる。その結果、組織全体の見かけの導電率は増加するのが一般的であり、低下するわけではない。
$正しい。細胞膜の単位面積当たりの電気容量(比容量)はおおよそ 1 \mu\t\text{F}/\t\text{cm}^2 程度とされる。これは脂質二重層膜の容量性に由来する代表的な値である。$
正しい。神経・筋の興奮は膜の時間定数に依存し、高周波電流では膜電位が十分に変化しにくい。そのため周波数が高いほど電気刺激に対する感受性(興奮しやすさ)は低下する。高周波領域では知覚や筋収縮が生じにくいことが知られている。
解説を表示するにはログインが必要です。ログインすると無料枠(1日5問)をご利用いただけます。
無料プランでは解説を1日5問まで表示できます。解説を表示すると残り回数が消費されます。
今日: 回 | 残り 回
本日の無料枠を使い切りました。プレミアム登録で無制限にご利用いただけます。
解説
中空糸多孔質膜型人工肺では、初期は疎水性の多孔質膜(例:ポリプロピレン)が用いられ、膜孔内に気液界面が保持されることでガス交換が行われる。血漿蛋白が膜表面に吸着すると表面は親水化し、孔が濡れてプラズマリークの原因となるため「疎水性になる」は誤り。外部灌流型では血液が中空糸の外側(シェル側)を、ガスが中空糸内腔を通る。シェル側は実効流路断面積が大きく、内部灌流型に比べて圧力損失が小さい。また繊維束外側の流れは流路が複雑で乱流・擬似乱流成分が生じやすく、層流化しやすいとはいえない。多孔質膜では膜が気液界面を保持する形で血液とガスが孔内界面で接する概念であり、「直接接触しない」という一般的な“非接触(混合なし)”の表現とは区別される点に注意する。以上より正しいのは3と4。
選択肢別解説
誤り。疎水性多孔質膜に血漿蛋白が吸着すると表面は親水化し、孔が濡れやすくなってプラズマリークのリスクが増す。「疎水性になる」は逆である。
誤り。多孔質膜型では膜孔内に気液界面が保持され、血液は膜材とは隔てられるが、孔内の気液界面でガスと血液が接する概念である(非多孔質膜のような固体膜越しの溶解拡散とは異なる)。したがって「直接接触しない」という記述は本設問の多孔質膜の概念と合致しない。
正しい。外部灌流型は血液が中空糸の外側(シェル側)を流れるため有効流路断面積が大きく、内部灌流型(血液が中空糸内腔を流れる)に比べ圧力損失が小さくなりやすい。
正しい。外部灌流型の流路配置は、血液が中空糸の外側、ガスが中空糸の内側(内腔)を通る。
誤り。外部灌流型では繊維束外側の流路が複雑で、乱流・擾乱が生じやすく混合が促進される傾向がある。内部灌流型より層流になりやすいとはいえない。
解説を表示するにはログインが必要です。ログインすると無料枠(1日5問)をご利用いただけます。
無料プランでは解説を1日5問まで表示できます。解説を表示すると残り回数が消費されます。
今日: 回 | 残り 回
本日の無料枠を使い切りました。プレミアム登録で無制限にご利用いただけます。