臨床工学技士問題表示
臨床工学技士国家試験
解説
超音波が2つの媒質の境界に垂直入射する場合、振幅の反射係数は $S = \left|\frac{Z_1 - Z_2}{Z_1 + Z_2}\right|$ で与えられる。ここで筋肉と血液の特性音響インピーダンスをそれぞれ $Z_1 = 1.7 \times 10^6$、$Z_2 = 1.6 \times 10^6\ \mathrm{kg\,m^{-2}\,s^{-1}}$ とすると、$S = \frac{1.7 - 1.6}{1.7 + 1.6} = \frac{0.1}{3.3} \approx 0.0303$ であり、およそ 0.03 となる。筋肉と血液は音響インピーダンスが近いため、反射は小さい(透過が大きい)のが特徴である。
選択肢別解説
0.01は小さすぎる。計算では $S = \left|\frac{1.7-1.6}{1.7+1.6}\right| = \frac{0.1}{3.3} \approx 0.0303$ であり、約0.03が妥当。
正しい。振幅反射係数は $S = \left|\frac{Z_1 - Z_2}{Z_1 + Z_2}\right|$ により $\frac{0.1}{3.3} \approx 0.0303$ となり、選択肢 0.03 が最も近い。
0.06は過大である。計算結果は $\approx 0.0303$ で約0.03に一致する。
0.08は過大である。計算式 $\left|\frac{Z_1 - Z_2}{Z_1 + Z_2}\right|$ からは約0.03となる。
0.09は過大である。与えられた音響インピーダンスから計算すると反射係数は約0.03である。
解説を表示するにはログインが必要です。ログインすると無料枠(1日5問)をご利用いただけます。
無料プランでは解説を1日5問まで表示できます。解説を表示すると残り回数が消費されます。
今日: 回 | 残り 回
本日の無料枠を使い切りました。プレミアム登録で無制限にご利用いただけます。
解説
遠心ポンプは非閉塞型・後負荷依存の連続流ポンプで、回転数が同じでも前負荷・後負荷(回路抵抗やカニューレ抵抗)の変化で流量が大きく変わる。そのため流量は回転数だけで精密制御せず、流量計で実測管理する。一方、正圧・陰圧の発生能力はローラポンプ(容積移送型)に比べて限定され、送血側が閉塞しても危険な高圧が生じにくく回路破裂リスクは低い。吸引側でも前負荷が低下すると流量が低下する方向に働くため、過度の陰圧は生じにくい。また停止時には非閉塞構造のため逆流が起こり得るので鉗子や逆流防止の対策が必要。血液への機械的ストレスもローラポンプより小さく、溶血は少ない。以上より、設問では3と4が正しい。
選択肢別解説
誤り。遠心ポンプは前負荷・後負荷依存性が高く、同一回転数でも回路抵抗や貯血槽液面で流量が大きく変動する。回転数だけで容易・正確に流量制御はできず、血流計による監視が必須である。
誤り。遠心ポンプは非閉塞型であり、停止時や低回転時には圧力差・高低差により逆流が生じ得る。運用上は送血・脱血ラインの鉗子や逆流防止弁で対策する。
正しい。遠心ポンプは送血側が閉塞しても高い閉塞圧を発生しにくく、ローラポンプのように危険な高圧で回路破裂に至るリスクは低い(ゼロではないが著しく小さい)。
正しい。入口側(前負荷)が不足・狭窄になると遠心ポンプは流量が低下する方向に働き、ローラポンプのような強い吸引がかかりにくい。したがって過度の陰圧(サクション)は生じにくい。
誤り。遠心ポンプはローラポンプに比べ血液へのせん断・圧迫ストレスが小さく、一般に溶血は少ない。
解説を表示するにはログインが必要です。ログインすると無料枠(1日5問)をご利用いただけます。
無料プランでは解説を1日5問まで表示できます。解説を表示すると残り回数が消費されます。
今日: 回 | 残り 回
本日の無料枠を使い切りました。プレミアム登録で無制限にご利用いただけます。
解説
遠心ポンプは非閉塞性の回転流ポンプで、流量は回転数だけでなく回路抵抗や血液粘度などの後負荷に依存する。したがって同じ回転数でも後負荷が変われば流量は変動する。非閉塞性ゆえにポンプ停止や低回転、または患者側圧がポンプ発生圧を上回る条件では逆流が起こり得るため、運用上は逆流防止弁やクランプで安全対策を行う。ローラポンプに比べ、圧閉による強い機械的ストレスがないため血液損傷(溶血)は一般に軽度とされる。一方、空気を巻き込むと脱プライミング(de-prime)を起こして送血が低下・停止するため、空気混入が多い吸引回路用途には適さず、またチューブ圧閉度の調整は不要である。以上より、正しいのは3、4、5である。
選択肢別解説
誤り。遠心ポンプは空気混入に弱く、空気を吸引すると脱プライミング(de-prime)で送血が低下・停止する。吸引回路は気泡混入が避けられないため、通常はローラポンプが用いられ、遠心ポンプは適さない。
誤り。チューブ圧閉度の調節が必要なのはローラポンプである。遠心ポンプは非閉塞性で、チューブを圧閉して送液する機構ではないため圧閉度調整は不要。
正しい。遠心ポンプは非閉塞性で、ポンプ発生圧が患者側の後負荷より低い場合や低回転・停止時には血液が逆流し得る。実臨床では逆流防止弁やラインクランプで対策する。
正しい。遠心ポンプはローラポンプのような圧閉による強い機械的ストレスが少なく、一般に血液損傷(溶血)はローラポンプより軽度とされる。高回転・高せん断での過度運転は別だが、通常運用での比較では遠心ポンプが有利。
正しい。遠心ポンプは後負荷依存性の流量特性を示し、同じ回転数でも回路抵抗や末梢血管抵抗、血液粘度が変わると流量が変化する。後負荷増大で流量は低下する。
解説を表示するにはログインが必要です。ログインすると無料枠(1日5問)をご利用いただけます。
無料プランでは解説を1日5問まで表示できます。解説を表示すると残り回数が消費されます。
今日: 回 | 残り 回
本日の無料枠を使い切りました。プレミアム登録で無制限にご利用いただけます。
解説
誤りは「残気量はスパイロメータで測定できる。」である。スパイロメータは口腔から出入りする換気による“変化分”のみを捉えるため、最大呼出後にも肺内に残る残気量(RV)は直接測れない。RVを含む機能的残気量(FRC)や全肺気量(TLC)の測定にはヘリウム希釈法、窒素洗い出し法、体プレチスモグラフなどの方法を用いる。一方、胸腔内圧は生理的には大気圧に対して陰圧(安静時でおおむね−5 cmH2O前後、呼吸相で変動)であり、成人の解剖学的死腔は約150 mL(目安として体重1 kgあたり約2 mL)で妥当。肺の栄養血管は気管支動脈で、ガス交換を担う機能血管である肺動脈とは役割が異なる。ヘモグロビンの酸素解離曲線はpH低下(酸性化)で右方偏位し、組織での酸素放出が促進される(Bohr効果)。
選択肢別解説
正しい。胸腔(胸膜腔)内圧は通常、大気圧に対して陰圧で維持され、肺の虚脱を防ぎ胸壁と肺の弾性のバランスを保つ。安静呼吸では概ね−2〜−8 cmH2O程度で呼吸相により変動する。強い努力呼出など一部状況で一過性に陽圧となり得るが、生理的記述としては「陰圧」で妥当。
正しい。解剖学的死腔は導管気道(鼻腔〜終末細気管支など)でガス交換に寄与しない容積を指し、成人で約150 mLが一般的な目安(体重換算で約2〜2.2 mL/kg)。
誤り。スパイロメータは呼吸に伴う肺気量の変化のみを測定するため、最大呼出後も肺に残る残気量(RV)は直接測定できない。RVやそれを含むFRC・TLCの評価にはヘリウム希釈法、窒素洗い出し法、体プレチスモグラフなどの方法を用いる。
正しい。肺には二重の血管系があり、ガス交換を担う機能血管は肺動脈、肺実質や気道壁へ酸素と栄養を供給する栄養血管は気管支動脈である。
正しい。pH低下(またはPCO₂上昇、温度上昇、2,3-BPG増加)はヘモグロビンの酸素解離曲線を右方へ偏位させ(Bohr効果)、同一PO₂での飽和度が低下し、組織での酸素放出が促進される。
解説を表示するにはログインが必要です。ログインすると無料枠(1日5問)をご利用いただけます。
無料プランでは解説を1日5問まで表示できます。解説を表示すると残り回数が消費されます。
今日: 回 | 残り 回
本日の無料枠を使い切りました。プレミアム登録で無制限にご利用いただけます。
解説
観血式血圧測定では、カテーテル—延長チューブ—トランスデューサから成る流体-電気変換系の動特性を適正に保つことが重要である。加圧バッグは約300 mmHgに加圧し、フラッシュデバイス(連続フラッシュ機構)によりヘパリン加生理食塩液を1〜3 mL/h程度で持続注入して血液逆流と凝固を防ぐ。ゼロ校正はトランスデューサを右房の高さにレベリングし、大気圧(0 mmHg)を基準に実施する。チューブ内の気泡は系のダンピングを増大させ、収縮期圧は低め、拡張期圧は高めに歪む一方、平均血圧(静的成分)は原理上ほぼ維持される。以上より、フラッシュデバイスの持続注入機能に関する記述のみ正しい。
選択肢別解説
誤り。チューブ内の気泡はダンピングを増大させ、収縮期圧は低く、拡張期圧は高く測定されやすい。しかし平均血圧(静的圧成分)は原理上ほぼ不変であり、下がるとはいえない。
誤り。カテーテル内はヘパリン加生理食塩液で満たし、気泡を除去する。蒸留水は低浸透圧で溶血や血管内刺激のリスクがあり使用しない。
誤り。加圧バッグは逆流防止と持続フラッシュ確保のため通常約300 mmHgに設定する。収縮期血圧と等しくはしない。
誤り。ゼロ校正は大気開放を0 mmHg基準として行い、トランスデューサの高さを右房レベルに合わせる。中心静脈圧そのものを基準値として用いるわけではない。
正しい。フラッシュデバイスは加圧バッグ内のヘパリン加生理食塩液を少量(通常1〜3 mL/h)で自動持続注入し、カテーテル先端の血液停滞と凝固を防ぐ機能をもつ(手動の高速フラッシュ機能も併載される)。
解説を表示するにはログインが必要です。ログインすると無料枠(1日5問)をご利用いただけます。
無料プランでは解説を1日5問まで表示できます。解説を表示すると残り回数が消費されます。
今日: 回 | 残り 回
本日の無料枠を使い切りました。プレミアム登録で無制限にご利用いただけます。
解説
膜型人工肺では、ガスと血液が膜を介して間接接触するため、気泡型に比べ溶血や蛋白変性が少ない。ガス交換機序は膜構造に依存し、均質膜(非多孔質:シリコーンなど)はガスが膜に溶解し拡散(溶解−拡散機構)で透過する。一方、多孔質膜(ポリプロピレン中空糸など)は微小孔を介した拡散が主体で、長時間使用や加湿条件で膜孔が濡れる“wet lung(膜濡れ)”が起きやすく、ガス交換性能が低下する。中空糸膜型の流路構造は、外部灌流型が「血液:中空糸外側、ガス:中空糸内側」、内部灌流型が「血液:中空糸内側、ガス:中空糸外側」。内部灌流型の中空糸内は細径・低レイノルズ数条件となるため血流は通常層流であり、乱流を前提とする記述は誤りである。
選択肢別解説
正しい。膜型人工肺はガスが血液へ直接気泡として接触しないため、気泡型人工肺に比べて機械的刺激や気液界面による血球・蛋白へのダメージが小さく、溶血は少ない。
正しい。均質膜(非多孔質膜:シリコーン等)は孔を持たず、酸素・二酸化炭素は膜に溶解して濃度勾配に従って拡散する(溶解−拡散機構)。
正しい。多孔質膜では長時間の体外循環や加湿条件で膜孔が濡れる“wet lung(膜濡れ)”が生じ、拡散経路が水で満たされてガス透過が低下し、性能劣化を招く。
正しい。外部灌流型中空糸膜では血液は中空糸外側(外側)を流れ、ガスは中空糸内腔を流れる設計である。
誤り。内部灌流型では血液は中空糸内腔を流れるが、糸径が小さく実運転条件でのレイノルズ数は低いため血流は通常層流となる。乱流を前提とする説明は不適切。
解説を表示するにはログインが必要です。ログインすると無料枠(1日5問)をご利用いただけます。
無料プランでは解説を1日5問まで表示できます。解説を表示すると残り回数が消費されます。
今日: 回 | 残り 回
本日の無料枠を使い切りました。プレミアム登録で無制限にご利用いただけます。
解説
体外循環では回路充填液(晶質液や人工膠質液)で血液が希釈され、ヘマトクリットが低下する。これにより血液粘性は低下し、ポンプや回路でのせん断応力が小さくなるため溶血は軽減される。一方、酸素運搬能は主にヘモグロビンに依存するため希釈で低下する。希釈を許容することで同種血輸血の必要量は減らせる。また血漿タンパクの希釈で膠質浸透圧は低下し、長時間では浮腫リスクとなる。以上より、正しいのは「輸血量の減少」と「溶血の軽減」である。
選択肢別解説
血液希釈によりヘマトクリットが下がると血液粘性は低下する。したがって「増加」は誤り。
酸素運搬能はヘモグロビン濃度に依存し、希釈でHbが低下するため酸素運搬能は低下する(例:動脈酸素含量 $C_aO_2\approx1.34\times Hb\times SaO_2+0.003\times PaO_2$)。増加ではない。
回路充填に晶質液や人工膠質液を用い、低ヘマトクリットを一時的に許容することで同種血輸血の必要量を減らせるため、正しい。
希釈で血液粘性が下がり回路内の機械的ストレス(せん断応力)が小さくなるため血球損傷が減り、溶血は軽減される。正しい。
希釈によりアルブミンなど血漿タンパク濃度が低下し、膠質浸透圧は低下する。上昇は誤りで、むしろ組織浮腫の要因となる。
解説を表示するにはログインが必要です。ログインすると無料枠(1日5問)をご利用いただけます。
無料プランでは解説を1日5問まで表示できます。解説を表示すると残り回数が消費されます。
今日: 回 | 残り 回
本日の無料枠を使い切りました。プレミアム登録で無制限にご利用いただけます。
解説
人工心肺ではプライミング液(多くは晶質液)で循環血液が希釈され、ヘマトクリットとヘモグロビンが低下する。これにより血液粘性は下がり、膠質浸透圧も血漿タンパクの希釈で低下する。赤血球濃度と粘性が下がることは機械的ストレスを相対的に減らし、溶血のリスクを抑える方向に働く。一方、酸素運搬能はヘモグロビン濃度に依存するため、同一灌流量であれば希釈により低下する。人工心肺ではしばしば低体温・アルカローシスが併用され、酸素解離曲線は左方へ移動しやすい(ヘモグロビンの酸素親和性が増す)が、これは血液希釈そのものの直接効果ではない。したがって「酸素運搬能が増加する」は誤り。
選択肢別解説
正しい。血液希釈によりヘマトクリットが下がると、全血粘性は低下する。粘性低下は末梢循環抵抗の低下や灌流性の改善に寄与するが、極端な希釈では酸素運搬が不足し得る。
正しい。血漿タンパク(主にアルブミン)が希釈されるため膠質浸透圧は低下し、組織浮腫のリスクが上がる。必要に応じてアルブミンや人工膠質で補正することがある。
誤り。酸素運搬能は主にヘモグロビン量に依存し、血液希釈でヘモグロビンが低下するため減少する。動脈酸素含量は概ね CaO2 $= 1.34\times Hb\times SaO2 + 0.003\times PaO2$ で表され、Hb低下はCaO2低下を招く。一定灌流量(血流)なら酸素供給量 DO2 $= CaO2\times Q$ も低下する。
正しい。希釈により赤血球濃度と血液粘性が下がり、回路・ポンプで受ける機械的せん断や赤血球同士の衝突が相対的に減少するため、溶血は抑制されやすい。ただし過度の陰圧吸引や高回転など他要因があれば溶血は起こり得る。
正しい(人工心肺臨床で一般にみられる現象)。人工心肺では低体温や相対的アルカローシスが併用されやすく、これらは酸素解離曲線を左方移動させてヘモグロビンの酸素親和性を高める。なお、左方移動は血液希釈そのものの直接効果ではない点に留意する。
解説を表示するにはログインが必要です。ログインすると無料枠(1日5問)をご利用いただけます。
無料プランでは解説を1日5問まで表示できます。解説を表示すると残り回数が消費されます。
今日: 回 | 残り 回
本日の無料枠を使い切りました。プレミアム登録で無制限にご利用いただけます。
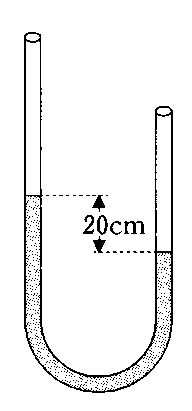
解説
生体での熱移動は大きく「熱伝導」「対流(血流や外気の流れ)」「熱放射」の3機序で説明できる。体表では外気との温度差により自然対流や気流(送風)による強制対流が生じ、熱放散を助ける(ニュートンの冷却則: 放熱はおおむね温度差に比例)。一方、皮膚など固相の組織内部ではバルクな流体運動がないため、基本的には熱伝導が支配的である。生体全体としては血流が熱を運ぶ対流効果が大きく、深部と体表の温度分布に強く影響する。熱放射については人体(約310 K)の放射ピークは遠赤外域(約10 µm付近)であり、近赤外ではない。熱伝導はフーリエの法則 $\mathbf{q}=-k\nabla T$ に従い温度勾配に比例し、温度の4乗に比例するのは放射(ステファン・ボルツマン則 $q=\varepsilon\sigma\left(T^4-T_{\text{周囲}}^4\right)$)である。
選択肢別解説
正しい。体表からの放熱には空気の自然対流や風による強制対流が寄与する。気流速度が上がると対流熱伝達係数が増し、放熱が促進される(ニュートンの冷却則 $q=hA\left(T_{\text{皮膚}}-T_{\text{空気}}\right)$)。
正しい。皮膚のような固相の組織内部ではバルクな流体運動がないため、熱の主な伝達は熱伝導であり、対流はほとんど存在しない。血流は微小循環として存在するが、ここでは「組織内の固相」における対流がほぼない点を述べていると解釈できる。
誤り。人体(約310 K)の熱放射のピーク波長はウィーンの変位則 $\lambda_{\max}\approx\frac{2.9\times10^{-3}}{T}$ より約9〜10 µmで、遠赤外域に相当する。近赤外(約0.75〜1.4 µm)ではない。
誤り。生体組織における熱伝導はフーリエの法則 $\mathbf{q}=-k\nabla T$ に従い温度勾配(温度差)に比例する。温度の4乗に比例するのは熱放射であり、ステファン・ボルツマン則に対応する。
正しい。生体内では血流が熱を運ぶ対流効果を担い、深部から体表への熱移送や局所の温度調節に大きく寄与する(Pennesの生体熱移動式でも灌流項が主要因として扱われる)。
解説を表示するにはログインが必要です。ログインすると無料枠(1日5問)をご利用いただけます。
無料プランでは解説を1日5問まで表示できます。解説を表示すると残り回数が消費されます。
今日: 回 | 残り 回
本日の無料枠を使い切りました。プレミアム登録で無制限にご利用いただけます。