臨床工学技士問題表示
臨床工学技士国家試験
解説
$電気メスは生体に高周波電流(一般に数100 kHz〜数 MHz、代表値は約300〜500 kHz)を流し、ジュール熱で切開 \cdot 凝固を行う。切開は連続波、凝固は断続(バースト)波を用いるのが基本で、性能試験や校正では数百Ω程度の模擬負荷を用いる。対極板は十分な接触面積(成人でおおむね150 cm^2 以上)が確保されていれば電流密度が低くなり熱傷リスクが低い。出力回路は患者に直流成分が流れないようコンデンサを直列挿入して直流遮断とし、コイル(インダクタ)を直列に入れる構成ではないため、「出力回路にはコイルが挿入されている」は誤り。$
選択肢別解説
正しい。電気メスの搬送周波数は臨床的にはおよそ数100 kHz〜数 MHz(代表的には約300〜500 kHz)が用いられる。100 kHz以上の高周波とすることで神経・筋の電気刺激を回避し、熱作用を主とした効果を得る。
正しい。電気メスの性能試験やキャリブレーションでは数百Ωの模擬負荷が想定され、200〜1,000 Ωは実用範囲に含まれる。代表的には300〜500 Ω付近での規定出力や測定が多い。
正しい。凝固は断続的なバースト(パルス変調)波形で組織を徐々に加熱・乾固させる。一方、切開は連続成分の強い波形(連続波)で瞬時に蒸散・切開する。
$正しい。対極板の接触面積が十分(成人の目安として150 cm^2 程度以上)であれば、同一出力でも電流密度が低下し熱傷リスクは小さい。200 W程度の出力でも、適切な貼付と皮膚条件が満たされていれば安全域と判断される。ただし実際の安全性は貼付状態や皮膚抵抗、ジェルの乾燥などにも依存する。$
誤り。患者への直流成分流入を防ぐため、出力回路にはコンデンサを直列挿入して直流遮断(カップリング)するのが基本である。インダクタ(コイル)は高周波でのリアクタンスが $X_L=2\pi fL$ に比例して大きくなり、高周波電流の通過を妨げるため、患者側直列要素としては不適切。正しくはコンデンサ($X_C=\frac{1}{2\pi fC}$)を用いる。
解説を表示するにはログインが必要です。ログインすると無料枠(1日5問)をご利用いただけます。
無料プランでは解説を1日5問まで表示できます。解説を表示すると残り回数が消費されます。
今日: 回 | 残り 回
本日の無料枠を使い切りました。プレミアム登録で無制限にご利用いただけます。
解説
体外循環では、充填液や循環管理の目的に応じて薬剤を併用する。マンニトールは浸透圧性利尿薬で、回路充填液に加えて浸透圧維持と利尿促進(腎保護)を図る目的で用いられ、適切な組合せである。乳酸加リンゲルは晶質液であり膠質浸透圧を保持する作用はないため、「膠質浸透圧の保持」との組合せは誤りである(膠質浸透圧維持にはアルブミン等の膠質液を用いる)。炭酸水素ナトリウムは代謝性アシドーシスの補正に用いるアルカリ薬であり、「アルカローシスの補正」との組合せは誤り。ハプトグロビン製剤は遊離ヘモグロビンと結合して腎障害を予防するため、溶血対策として適切。塩化カルシウムは心筋収縮力増強や低カルシウム血症是正に有用であり適切。したがって誤っている組合せは2と3である。
選択肢別解説
マンニトールは浸透圧性利尿薬で、回路充填液等に添加して浸透圧を保ち利尿を促進し、腎保護や浮腫抑制を目的に用いられる。よって「浸透圧の調節」との組合せは適切であり、誤りではない。
乳酸加リンゲルは晶質液であり、膠質浸透圧(主に血漿蛋白に依存)を保持する作用はない。膠質浸透圧の保持には5%アルブミンなどの膠質液を用いる。したがって本組合せは誤り。
炭酸水素ナトリウムは代謝性アシドーシスの補正に用いられるアルカリ薬であり、アルカローシスの補正には用いない。よって「アルカローシスの補正」との組合せは誤り。
ハプトグロビン製剤は遊離ヘモグロビンと結合し、腎尿細管障害を予防する。体外循環時の高度溶血への対応として適切であり、誤りではない。
塩化カルシウムは心筋の収縮に必須なCa2+を補給し、心収縮力増強や血圧上昇作用を示す。低Ca血症是正や収縮力低下への対応として適切であり、誤りではない。
解説を表示するにはログインが必要です。ログインすると無料枠(1日5問)をご利用いただけます。
無料プランでは解説を1日5問まで表示できます。解説を表示すると残り回数が消費されます。
今日: 回 | 残り 回
本日の無料枠を使い切りました。プレミアム登録で無制限にご利用いただけます。
解説
透析回路から気泡が体内に入った場合は、まず追加流入を直ちに止めることが最重要であり、血液ポンプ停止(必要に応じて返血側クランプ)を行う。体位は頭低位(トレンデレンブルグ体位)として、脳・冠循環への到達を抑える。一般に静脈系空気塞栓では左側臥位(Durant法)を併用して右心室流出路への空気移動を抑えるが、本設問の選択肢には左側臥位がないため、頭低位の選択が妥当となる。呼吸・循環管理としては高濃度酸素投与を速やかに開始し、低酸素血症の改善と窒素洗い出しによる気泡縮小を図る。起坐位は空気の頭側移動を助長し得るため不適切、右側臥位も推奨されない。
選択肢別解説
正しい。さらなる空気流入を防ぐため、最優先で血液ポンプを停止する(必要に応じて回路クランプ)。これにより体内への気泡追加流入を遮断する。
正しい。頭低位(トレンデレンブルグ体位)は気泡が脳や冠動脈側へ移行するリスクを下げる目的で推奨される。臨床では左側臥位(Durant法)を併用することが多いが、本問では頭低位の選択が適切。
誤り。静脈系空気塞栓への初期対応としては左側臥位が推奨される(Durant法)。右側臥位は右心室内での気泡位置制御に不利となり得るため適切でない。
誤り。起坐位は一般的な呼吸困難(例:肺水腫)では有用だが、空気塞栓では頭側への気泡移動を助長し脳・冠循環への到達リスクが高まる。頭低位が望ましい。
正しい。高濃度酸素は低酸素血症の改善に加え、窒素洗い出しにより気泡体積の縮小を促すため推奨される。
解説を表示するにはログインが必要です。ログインすると無料枠(1日5問)をご利用いただけます。
無料プランでは解説を1日5問まで表示できます。解説を表示すると残り回数が消費されます。
今日: 回 | 残り 回
本日の無料枠を使い切りました。プレミアム登録で無制限にご利用いただけます。
解説
体外循環回路の各構成要素と代表的な材料の組合せを問う問題。熱交換器は耐腐食性と十分な伝熱性をもつステンレス管が広く用いられる。膜型人工肺は主に多孔質中空糸膜(例: ポリプロピレン系)が主流で、ガス交換効率と圧損・耐久のバランスがよい。遠心ポンプはシャフトシールを用いず、外部モータ側マグネットとポンプ内ロータのマグネットを磁気結合(マグネットカップリング)させて駆動するのが一般的である。血液回路(チューブ)は柔軟性と加工性の観点からポリ塩化ビニル(PVC)が標準的に用いられる。これらはいずれも妥当な組合せ。一方、バブルトラップは送血系・静脈系の空気除去を目的とする捕気チャンバやメッシュを主体とした構造で、シリコーン中空糸膜は用いない。シリコーン系の均質膜(あるいは非多孔質系の中空糸)は人工肺のガス交換膜としての用途であり、バブルトラップとの組合せは不適切であるため、5が誤り。
選択肢別解説
熱交換器は水槽側との間で熱を伝える要素で、耐腐食性・洗浄性の良いステンレス管が広く用いられる。アルミ等の採用例もあるが、ステンレス管は代表的材料であり組合せは妥当。
膜型人工肺では多孔質中空糸膜(代表例: ポリプロピレン、ポリオレフィン系)が主流で、ガス透過と血漿漏れ抑制のバランスが取れている。よってこの組合せは正しい。
遠心ポンプは外部モータ側のマグネットとポンプ内ロータ側のマグネットを磁気結合させてトルクを伝達する方式(磁気駆動)を用いるのが一般的で、シールレスで血液へのせん断を抑えやすい。よって組合せは正しい。
体外循環の血液回路チューブは柔軟性・加工性に優れたポリ塩化ビニル(PVC)が標準的。可塑剤の種類などは製品により異なるが、材料としての組合せは妥当。
バブルトラップは回路内の気泡を捕捉・除去するためのチャンバやメッシュ主体の構造で、外筒にポリカーボネート、内部フィルタにポリエステル等が用いられるのが一般的。シリコーン中空糸膜は人工肺の均質膜系素材としての用途であり、バブルトラップには用いないためこの組合せは不適切(誤り)。
解説を表示するにはログインが必要です。ログインすると無料枠(1日5問)をご利用いただけます。
無料プランでは解説を1日5問まで表示できます。解説を表示すると残り回数が消費されます。
今日: 回 | 残り 回
本日の無料枠を使い切りました。プレミアム登録で無制限にご利用いただけます。
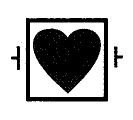
解説
提示図記号は「耐除細動形のCF形装着部」を示す。CF形は心臓に直接つながる可能性のある装着部に適用され、除細動時の高電圧・高電流から患者・機器を保護する設計(耐除細動)を満たしている。したがって、除細動の際に誘導コードを外す必要はないため、選択肢5は誤り。他の記述は、CF形・耐除細動形の特性および漏れ電流(接触電流)の規格要件に合致しており妥当である。接触電流(外装漏れ電流)の許容値は装着部の種別に依存せず、IEC 60601-1系規格ではおおむね正常状態100 µA、単一故障状態500 µAの水準が用いられる。
選択肢別解説
正しい。CF形装着部を備える心電図モニタは、通常の表面(胸部)誘導のモニタリングが可能である。耐除細動形であれば除細動時の保護も備える。
正しい。CF形は心臓に直接接続され得る装着部に要求される最も厳しい安全条件を満たす分類であり、ペーシングリードなどを介した心内心電図の誘導に適合し得る(機能の有無は機種依存だが、安全性分類としては許容される)。
正しい。ICUでは除細動の可能性があるため、除細動時の過大電圧に耐える『耐除細動形CF形』の心電図モニタが望ましい。誘導コードを外さずに連続監視を継続できる利点がある。
正しい。外装漏れ電流(接触電流)は装着部の種別(B/BF/CF)に依存せず同一水準の規格値が適用され、一般に正常状態約100 µA、単一故障状態約500 µAが上限である。したがって人工呼吸器等の他機器と『同程度でよい』という表現は妥当である。
誤り。図記号は『耐除細動形のCF形装着部』を示すため、除細動の際に誘導コードを外す必要はない(機器は除細動パルスに耐える設計)。ただし臨床上は電極位置の適切な配置や接触回避などの安全手順は必要である。
解説を表示するにはログインが必要です。ログインすると無料枠(1日5問)をご利用いただけます。
無料プランでは解説を1日5問まで表示できます。解説を表示すると残り回数が消費されます。
今日: 回 | 残り 回
本日の無料枠を使い切りました。プレミアム登録で無制限にご利用いただけます。