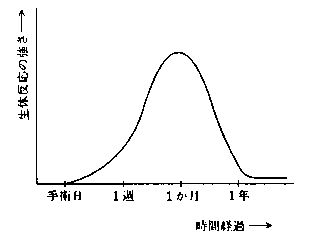臨床工学技士問題表示
臨床工学技士国家試験
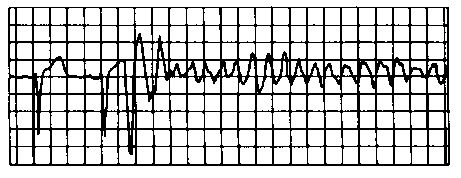
解説
血液透析施行中に装置が連続的に見張るべき項目は、患者安全に直結するアラーム系と血液回路の圧力監視である。具体的には、透析液側への血液の混入(漏血)は光学式の漏血検出器で、静脈側回路への気泡混入は超音波式の気泡検出器で、静脈側回路内圧は圧力センサで、それぞれ常時監視され、異常時にはポンプ停止やクランプ作動などで患者を保護する。一方、血漿浸透圧は生化学的指標で装置による連続測定の対象ではなく、透析液エンドトキシン濃度は水質管理として定期的な検査項目であり、透析中の常時監視には含まれない。したがって常時監視項目は漏血、気泡混入、静脈側回路内圧である。
選択肢別解説
不適切。血漿浸透圧は生化学的指標であり、透析装置がリアルタイムかつ連続で測定・監視する項目ではない。装置が連続監視するのは主に圧力・気泡・漏血・透析液の温度や導電率などである。
適切。ダイアライザ透析液側への血液混入(膜破損など)は光学式の漏血検出器で常時監視され、検出時はアラーム作動と装置の安全動作(透析液系バイパス、ポンプ停止など)で患者を保護する。
適切。静脈側回路には超音波式の気泡検出器が設置され、気泡混入を常時監視し、検出時は静脈クランプ閉鎖や血液ポンプ停止などの安全動作が作動する。
適切。静脈側回路内圧は圧力センサで連続的に監視され、穿刺部のトラブル、回路屈曲・閉塞、凝血などの兆候を早期に検知する。上限・下限アラーム設定により異常時に装置が介入する。
不適切。透析液エンドトキシン濃度は水質管理の一環として定期的にサンプリング検査される項目であり、透析中に装置がリアルタイムで常時監視するのが一般的ではない。
解説を表示するにはログインが必要です。ログインすると無料枠(1日5問)をご利用いただけます。
無料プランでは解説を1日5問まで表示できます。解説を表示すると残り回数が消費されます。
今日: 回 | 残り 回
本日の無料枠を使い切りました。プレミアム登録で無制限にご利用いただけます。
解説
透析装置(コンソール)には患者安全と治療の精度確保のため、血液回路・透析液回路の監視と制御機能が標準で組み込まれている。代表的な内蔵機能は、透析液側への赤血球混入を監視する漏血検出器、静脈側回路の気泡を検知して血液ポンプ停止・クランプ閉鎖を行う気泡検出器、透析液を約35~40℃に維持するための温度測定・加温制御、そして設定した除水速度・総量を達成する除水制御(TMP制御や体積平衡方式など)である。一方、透析液の濃度管理は電導度計(導電率計)と温度補正によってリアルタイムに監視・制御され、浸透圧計は凍結点降下などの原理でオフライン計測が中心で応答性に乏しく連続監視に適さないため、コンソールには組み込まれない。従って、組み込まれていないのは透析液浸透圧計である。
選択肢別解説
漏血検出器はダイアライザ透析液出口側の透析液を光学的に監視し、赤血球混入による透過率低下を捉えてアラーム・回路遮断を行う。患者安全確保のため透析装置コンソールに標準搭載される。よって『組込まれていない』には該当しない。
気泡検出器は静脈側回路に設置される超音波式(現在主流)や光学式で、気泡を検出すると血液ポンプ停止・静脈クランプ閉鎖などの安全動作を行う。コンソールに組み込まれる基本的安全機能であり、『組込まれていない』には該当しない。
透析液温計(温度計)は透析液温を連続測定し、ヒータと連携しておよそ35~40℃に制御する。患者の体温負荷やダイアライザ性能に直結するため、コンソール内蔵の基本機能である。よって『組込まれていない』には該当しない。
除水制御装置は設定した除水速度・総除水量を正確に実施するための機構で、TMP制御方式や、平衡チャンバ(ダイアフラム・ピストン)を用いた体積平衡式が用いられる。透析治療の中核機能としてコンソールに組み込まれているため、『組込まれていない』には該当しない。
透析液浸透圧計は一般にコンソールには内蔵されない。透析液の濃度管理は電解質濃度と相関する電導度の連続監視・制御で行われ、浸透圧計(凍結点降下法など)は応答が遅く連続リアルタイム監視に不向きで安全制御上の一次手段とならないためである。したがって本問の該当肢である。
解説を表示するにはログインが必要です。ログインすると無料枠(1日5問)をご利用いただけます。
無料プランでは解説を1日5問まで表示できます。解説を表示すると残り回数が消費されます。
今日: 回 | 残り 回
本日の無料枠を使い切りました。プレミアム登録で無制限にご利用いただけます。
解説
医療現場で用いられるガス・蒸気の代表的な有害作用の組み合わせを問う問題。酸素は未熟児に高濃度で投与すると網膜血管の異常増殖を来し未熟児網膜症の原因となりうる。亜酸化窒素はビタミンB12依存酵素(メチオニン合成酵素)を阻害して造血機能低下(巨赤芽球性貧血)や神経障害を生じうる。揮発性麻酔薬は一般に心筋抑制や血管拡張により心血管系抑制(血圧低下、不整脈傾向など)を起こしうる。酸化エチレンは滅菌用ガスで、吸入曝露により眼・鼻・気道粘膜の強い刺激性(損傷)を示す。一方、二酸化炭素の主な有害作用は高濃度吸入による高二酸化炭素血症(呼吸性アシドーシス、頭痛・意識障害など)であり、肝機能障害は典型的な副作用とはいえないため、選択肢2の組み合わせが誤りである。
選択肢別解説
酸素→未熟児網膜症は妥当。未熟児に高濃度酸素を持続投与すると網膜血管の収縮・閉塞とその後の異常新生血管増殖を介して網膜症を発症しうるため、NICUでは酸素化の厳密管理が行われる。
二酸化炭素→肝機能障害は不適切。CO2の主な有害作用は吸入時の高二酸化炭素血症による中枢神経抑制、頭痛、呼吸性アシドーシス、重篤例では意識障害・呼吸循環不全であり、肝毒性は典型ではない。よってこの組み合わせが誤り。
亜酸化窒素→造血機能低下は妥当。笑気はビタミンB12を不活化しメチオニン合成酵素を阻害するため、長期・高用量曝露で巨赤芽球性貧血などの造血障害や神経障害を来すことがある。
揮発性麻酔薬→心血管系抑制は妥当。ハロタンやイソフルラン等は用量依存的に心筋収縮抑制や末梢血管拡張を起こし、血圧低下や不整脈誘発性などの循環抑制を示す。
酸化エチレン→気道粘膜損傷は妥当。EOGは強い刺激性・感作性を持つ滅菌ガスで、曝露すると眼・上気道を中心に粘膜刺激症状や損傷を来しうる。
解説を表示するにはログインが必要です。ログインすると無料枠(1日5問)をご利用いただけます。
無料プランでは解説を1日5問まで表示できます。解説を表示すると残り回数が消費されます。
今日: 回 | 残り 回
本日の無料枠を使い切りました。プレミアム登録で無制限にご利用いただけます。