臨床工学技士問題表示
臨床工学技士国家試験
解説
体外循環中は希釈や酸塩基・温度変化、薬剤投与により電解質が大きく変動する。インスリンはNa⁺/K⁺-ATPアーゼを介してK⁺を細胞内へ取り込み、血清K⁺を低下させるため低カリウム血症に傾く。低体温やアルカローシスもK⁺を細胞内へ移動させ、血清K⁺を低下させる方向に働く。保存血の大量使用では、抗凝固剤クエン酸がイオン化Ca²⁺をキレートして低カルシウム血症を来しやすい。さらに、回路充填液や心筋保護液の影響を含む希釈により、体外循環の早期には低ナトリウム血症が生じやすい。これらの典型的変動を踏まえたモニタリングと補正が重要である。
選択肢別解説
正しい。インスリンはNa⁺/K⁺-ATPアーゼ活性を高め、K⁺を細胞内へ移動させるため血清K⁺が低下し、低カリウム血症になりやすい。体外循環中の高血糖是正や高K⁺是正でインスリンを用いる際は特に注意する。
誤り。低体温ではK⁺が細胞内へシフトしやすく、血清K⁺は低下する方向(低カリウム化)に向かう。高カリウムになりやすいのは復温時に細胞外へK⁺が戻る局面でみられうるが、「低体温時」そのものは高カリウム化の方向ではない。
誤り。アルカローシスではH⁺の細胞外移動に伴いK⁺が細胞内へ移動するため、血清K⁺は低下しやすい(低カリウム化)。高カリウム化はアシドーシスで問題となる。
正しい。保存血の抗凝固剤クエン酸がイオン化Ca²⁺をキレートして低下させ、低カルシウム血症を生じやすい。大量輸血や回路充填に保存血を用いる際はイオン化Ca²⁺のモニタとカルシウム投与が必要。
正しい。回路充填液や心筋保護液の影響による希釈で体外循環初期に血清Na⁺が低下(希釈性低ナトリウム血症)しやすい。なお、その後の補液・薬剤(例:NaHCO₃)や除水の有無でNa⁺は変動しうるため連続的評価が重要。
解説を表示するにはログインが必要です。ログインすると無料枠(1日5問)をご利用いただけます。
無料プランでは解説を1日5問まで表示できます。解説を表示すると残り回数が消費されます。
今日: 回 | 残り 回
本日の無料枠を使い切りました。プレミアム登録で無制限にご利用いただけます。
解説
透析監視装置は血液回路圧、ダイアライザの漏血、空気誤入、透析液の温度・電気伝導度(濃度指標)などを監視する。漏血はダイアライザの膜破損や継手不良により血液が透析液側へ漏れる事象で、排液側の光学式センサで検出される。一方、透析装置ヒータの故障は透析液温度異常(高温・低温)の原因であり、漏血の原因ではない。よって「漏血—透析装置ヒータの故障」の組合せは誤り。空気誤入は補液ラインのクランプ閉鎖忘れ等で陰圧側から空気を引き込みうる。血液側回路内圧異常は、凝固や回路閉塞で上昇し、脱血不良で低下(動脈圧がより強い陰圧化、あるいはポンプ流量維持不能)する。透析液濃度異常の監視は電気伝導度計に依存しており、その故障や電極汚染でも異常表示が発生しうる。
選択肢別解説
誤りの組合せ。漏血はダイアライザ膜破損やヘッダ部Oリング不良などで血液が透析液側へ混入する事象で、排液の光学式漏血センサで検出する。透析装置ヒータの故障は透析液温度異常(高温や低温)アラームの原因であり、漏血の原因とはならない。
妥当な組合せ。補液ラインの閉鎖(クランプ)忘れや接続不良により、陰圧がかかる回路側から空気を吸引し、空気誤入警報が作動しうる。補液バッグが空または脱落している場合は特に危険で、静脈側での気泡検出・遮断動作が求められる。
妥当な組合せ。血液凝固は回路抵抗を増大させ、特に静脈圧(ポンプ後圧)の上昇を招く。ほかにも回路の折れ曲がりや返血針閉塞でも上昇するが、血液凝固は代表的原因である。
妥当な組合せ。脱血不良(穿刺位置不良、陰圧過大、血管虚脱など)では動脈圧が低下(より強い陰圧化)して設定流量を維持できなくなり、血液側回路内圧低下の異常として検出される。
妥当な組合せ。透析液の濃度(電解質混合比)は電気伝導度で監視され、電気伝導度計の故障や電極汚染・キャリブレーション不良でも「透析液濃度異常」の警報が発生しうる(実際の濃度異常の一次原因としては原液枯渇や比例装置故障などもある)。
解説を表示するにはログインが必要です。ログインすると無料枠(1日5問)をご利用いただけます。
無料プランでは解説を1日5問まで表示できます。解説を表示すると残り回数が消費されます。
今日: 回 | 残り 回
本日の無料枠を使い切りました。プレミアム登録で無制限にご利用いただけます。
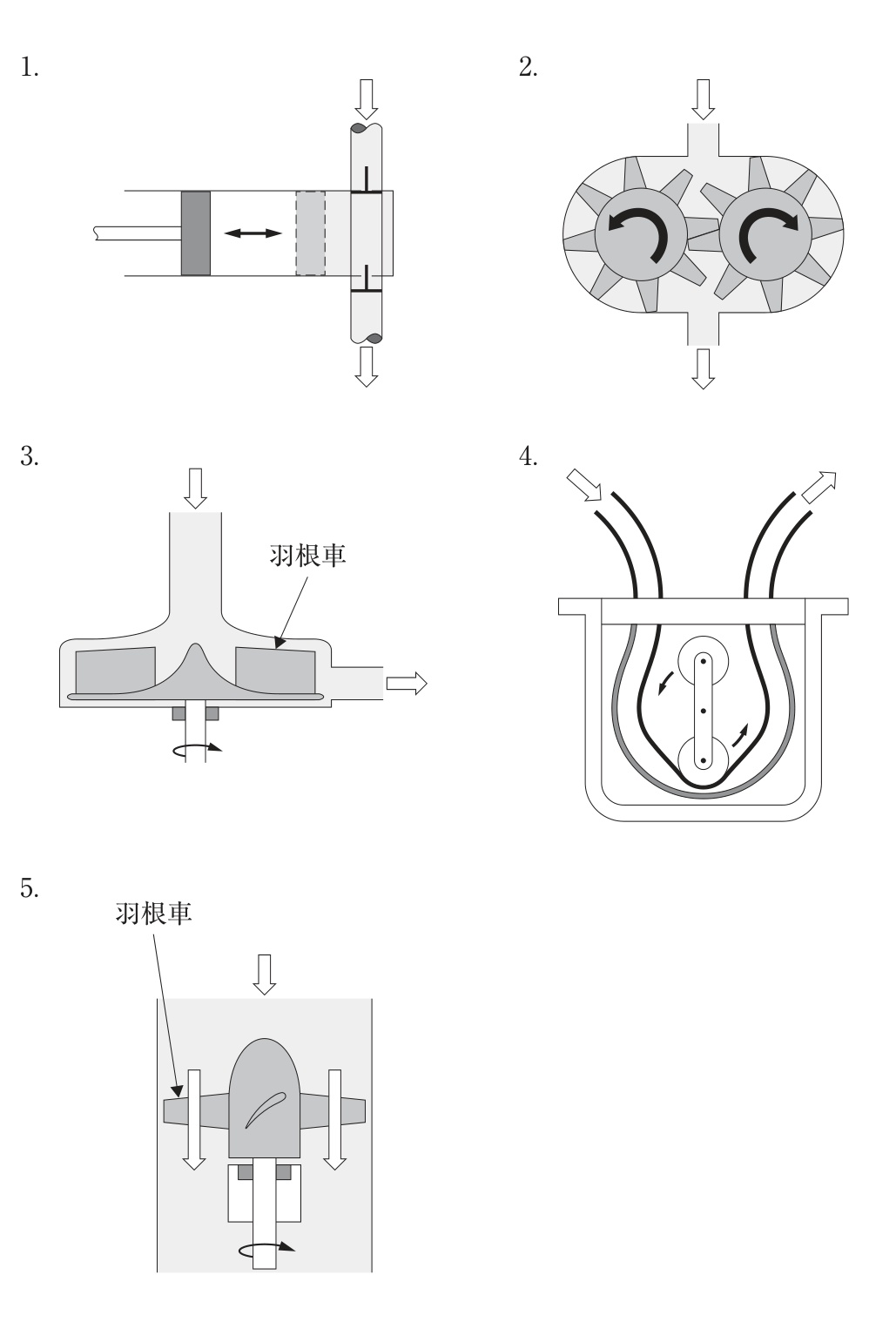
解説
膜型人工肺の膜には、(1)微小孔をもつ多孔質膜(例: ポリプロピレン中空糸)と、(2)微小孔をもたない均質膜(例: シリコン)に大別される。多孔質膜は疎水性で孔内にガス相を保持し高いガス交換効率を得る一方、長時間使用で血漿の湿潤に伴うプラズマリークが起こり得る。これを抑制する目的で、孔表面を被覆するなどの工夫を施したものが複合膜であり、血漿漏出の抑制を目的としている。均質膜(シリコン)はガスと血液が膜で厳密に隔てられ、拡散によりガス交換が行われる。シリコンでは一般にCO2の透過性がO2より高く、また機械的強度は多孔質膜(中空糸)の方が優れる。以上より、「複合膜は長時間使用すると血漿成分の漏出がある」は目的と逆で誤りである。
選択肢別解説
正しい。多孔質膜(ポリプロピレンなど)は疎水性で、孔内にガスを保持して血液が浸入しにくい性質を利用する。シリコンも疎水性を示すため、膜型人工肺の膜素材として疎水性材料が用いられる点は妥当である。
正しい。均質膜(シリコン膜など)は微小孔を持たず、膜そのものを介した溶解・拡散でガス交換が行われるため、血液とガスは直接接触しない。
正しい。シリコン膜ではCO2の溶解度・拡散性が高く、一般にCO2の透過性はO2より大きいとされるため、記述は適切である。
正しい。シリコン膜はガス透過性に優れる一方で機械的強度は低く、支持が必要となることが多い。多孔質膜(ポリプロピレン中空糸など)は機械的強度に優れ、取り扱い上も有利である。
誤り。複合膜は多孔質膜の欠点である血漿漏出(プラズマリーク)を抑制する目的で表面被覆等を施した設計であり、長時間使用での血漿成分漏出を減らすことを狙っている。したがって『長時間使用すると血漿成分の漏出がある』という断定は目的と矛盾し不適切である。
解説を表示するにはログインが必要です。ログインすると無料枠(1日5問)をご利用いただけます。
無料プランでは解説を1日5問まで表示できます。解説を表示すると残り回数が消費されます。
今日: 回 | 残り 回
本日の無料枠を使い切りました。プレミアム登録で無制限にご利用いただけます。