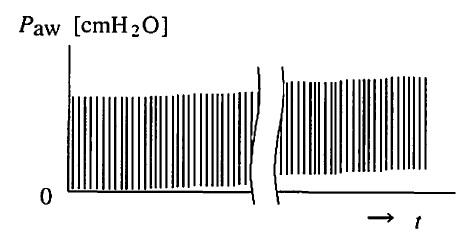臨床工学技士問題表示
臨床工学技士国家試験
解説
人工心肺(体外循環)では、血液が人工材料に接触し、機械的せん断や希釈、低体温管理、虚血再灌流などの影響を受ける。これにより血小板は吸着・活性化・消費・希釈で減少し、白血球活性化を介してIL-6などの炎症性サイトカインが放出される。また低体温やストレスホルモン優位により膵β細胞のインスリン分泌は抑制され高血糖傾向となる。一方、赤血球は回転ポンプや回路内での物理的ストレスにより溶血を生じ、血清遊離ヘモグロビンは増加するため「低下」は誤り。心房性ナトリウム利尿ペプチド(ANP)は心房伸展で分泌が増すホルモンであり、体外循環全体で一様に低下するとは言えない。特に大動脈遮断解除後や前負荷増大時に上昇がみられる報告があり、「低下する」と断定する記載は不適切である。
選択肢別解説
正しい。体外循環中は血液希釈、回路・酸素atorへの吸着、機械的ストレスによる活性化と消費により血小板数が低下する。術後早期に出血傾向の一因となり得る。
正しい。低体温管理や手術ストレスに伴うカテコラミン・グルカゴン上昇などにより、膵β細胞のインスリン分泌は抑制され相対的不足となり高血糖傾向を示す。よって体外循環中のインスリン分泌は減少する。
正しい。血液が人工材料に接触することで補体系や白血球が活性化し、IL-6、TNF-αなどの炎症性サイトカインが放出され全身炎症反応を惹起する。
誤り。体外循環では回路やポンプによる機械的せん断で赤血球溶血が生じ、血清遊離ヘモグロビンは増加する。したがって「低下する」は不正確。
誤り。ANPは心房壁伸展で分泌が増加する。体外循環中に一律の低下はみられず、特に遮断解除後や前負荷が回復・増加する局面で上昇する報告があるため、「低下する」と断定するのは不適切。
解説を表示するにはログインが必要です。ログインすると無料枠(1日5問)をご利用いただけます。
無料プランでは解説を1日5問まで表示できます。解説を表示すると残り回数が消費されます。
今日: 回 | 残り 回
本日の無料枠を使い切りました。プレミアム登録で無制限にご利用いただけます。
解説
誤っているのは5。透析用水の標準的な水処理フローは、原水→(前処理フィルタ)→硬水軟化装置→活性炭濾過→カートリッジフィルタ→逆浸透(RO)→供給系/循環ループである。ROを最上流に置くことはなく、ROを保護するために前段で硬度成分(Ca²⁺・Mg²⁺)や残留塩素・クロラミンを除去する。1は透析液側のカプラが汚染リスクの高い接続部位であり定期的な消毒が必要という点で正しい。2は透析液Na⁺濃度をやや高めに設定すると浸透圧低下が緩和され、除水時の血圧低下が抑えられ血圧が安定しやすい。3は透析液作製に用いる原水は水道法の水質基準を満たす安全な水を用い、その上で水処理により透析用水基準(細菌・エンドトキシンなど)に適合させるという趣旨で正しい。4はエンドトキシン捕捉フィルタが細菌およびエンドトキシンを除去して透析液の清浄化に寄与する点で正しい。
選択肢別解説
正しい。ダイアライザと装置を接続する透析液側のカプラは接触機会が多く汚染されやすい部位であり、透析液清浄化の観点から定期的な薬液消毒や熱消毒が求められる。施設手順やメーカー手順に沿った定期的な管理が標準である。
正しい。透析液Na⁺濃度を高めに設定(例: 通常より数mEq/L高値)すると血漿浸透圧の低下が緩和され、除水に伴う循環不安定(低血圧、筋痙攣など)が抑えられ血圧が安定しやすい。一方で口渇や間欠期体重増加、血圧上昇のリスクがあるため個別調整が必要。
正しい。透析液の作製に用いる原水(一般に上水)は水道法の水質基準を満たす安全な水であることが前提であり、井戸水等を使用する場合も同等の水質が求められる。そのうえで水処理装置を通して透析用水基準(細菌・エンドトキシンなど)に適合させる。
正しい。エンドトキシン捕捉フィルタ(透析液用超ろ過フィルタ)はサイズ排除や吸着によりエンドトキシンだけでなく細菌も除去し、透析液の清浄度を高めるために供給ライン下流側に設置される。
誤り。正しい順序は『硬水軟化装置→活性炭濾過→逆浸透(RO)』である。前段で硬度成分(Ca²⁺・Mg²⁺)や残留塩素・クロラミンを除去してRO膜のスケーリングや劣化を防いだ後、ROで溶解性不純物を大幅に低減する。設問の順序(RO→活性炭→軟化)は逆で不適切。
解説を表示するにはログインが必要です。ログインすると無料枠(1日5問)をご利用いただけます。
無料プランでは解説を1日5問まで表示できます。解説を表示すると残り回数が消費されます。
今日: 回 | 残り 回
本日の無料枠を使い切りました。プレミアム登録で無制限にご利用いただけます。
解説
体外循環用血液回路では、安全かつ血液に対して低反応であることが最重要である。回路チューブは気泡・血液色調・凝血塊などを目視確認する必要があるため透明材質が基本であり、回路全体は血液適合性の高い材料や表面処理で構成する。ヘパリンコーティングは表面の抗血栓性付与(血小板・凝固・補体系の活性化抑制)が目的であり、耐熱性向上の目的ではない。回路接続用コネクタは一般にポリカーボネート等の疎水性樹脂が用いられ、親水性である必要はない。ローラポンプ用チューブはスパレーション(摩耗粉)を極力生じにくい耐摩耗性材質(例: 医療用シリコーン等)が選択される。
選択肢別解説
正しい。気泡混入・血液色調・凝血塊の目視確認が不可欠であり、透明チューブが標準的に用いられる。視認性は安全管理上の基本要件である。
誤り。回路接続用コネクタに親水性材料を用いる必然性はなく、実際にはポリカーボネートなど疎水性の医療用樹脂が一般的である。親水化は潤滑性付与など別目的で用いられることはあるが、コネクタとして必須要件ではない。
誤り。ヘパリンコーティングの主目的は抗血栓性付与であり、血液が異物面に接触した際の凝固・血小板・補体系活性化を抑制するためである。耐熱性向上を目的とするものではない。
正しい。体外循環回路は血液異物面反応を最小化するため、血液適合性に優れた材料や表面改質(例: ヘパリン化)で構成される。これは溶血・血栓形成・炎症反応の低減に直結する。
正しい。ローラポンプはチューブを圧迫走行させるためスパレーション(摩耗粉)が問題となる。従って耐摩耗性が高く、摩耗粉を極力生じにくい材質のチューブを用いるのが望ましい(完全ゼロは難しいが最小化が要件)。
解説を表示するにはログインが必要です。ログインすると無料枠(1日5問)をご利用いただけます。
無料プランでは解説を1日5問まで表示できます。解説を表示すると残り回数が消費されます。
今日: 回 | 残り 回
本日の無料枠を使い切りました。プレミアム登録で無制限にご利用いただけます。
解説
誤っている組合せは「濃度計―浸透圧」。透析液の濃度監視は、電解質濃度に比例して変化する電気伝導度を電極で測定するのが一般的で、浸透圧を直接モニタする方式ではない。その他の組合せは、いずれも血液浄化装置で広く用いられる原理に合致する。漏血検出は透析液排液側の光透過測定で赤血球混濁に伴う透過率低下を検出、気泡検出は超音波の減衰・反射を利用、温度計はサーミスタ(NTCが一般的)で透析液温度の制御、圧力計はストレインゲージ式圧力変換器で動脈圧・静脈圧・TMPなどを監視する。
選択肢別解説
正しい組合せ。漏血検出器は透析液排液ラインに設置され、LEDとフォトセンサで光の透過量を測定する。透析膜破損などで血液が混入すると赤血球により混濁して透過率が低下し、しきい値超過でアラームを発する。
正しい組合せ。気泡検出器は超音波方式が一般的で、液体と気泡の音響インピーダンス差により伝搬の減衰・反射が生じることを用いて検出する。光学式もあるが、臨床機では非接触で配管外装着できる超音波式が広く使われる。
誤りの組合せ。透析液の濃度計は電極で交流を印加し電気伝導度を測定して電解質濃度を推定する。浸透圧は体液指標として用いられるが、透析装置の濃度監視の検出原理としては通常採用されない。
表記に誤りがあるが、原理としてはサーミスタが正しい組合せ。サーミスタ(thermistor)は温度によって抵抗値が変化する素子で、透析液温度(概ね35〜40℃)の測定・制御に用いられる。原文の「サーミスク」は誤記と考えられる。
正しい組合せ。圧力計にはストレインゲージ式圧力センサ(ひずみゲージ)が用いられ、動脈圧・静脈圧・透析膜間圧差(TMP)などを連続監視する。半導体ピエゾ抵抗式も使用されるが、ストレインゲージ式は一般的である。
解説を表示するにはログインが必要です。ログインすると無料枠(1日5問)をご利用いただけます。
無料プランでは解説を1日5問まで表示できます。解説を表示すると残り回数が消費されます。
今日: 回 | 残り 回
本日の無料枠を使い切りました。プレミアム登録で無制限にご利用いただけます。
解説
中空糸多孔質膜型人工肺では、初期は疎水性の多孔質膜(例:ポリプロピレン)が用いられ、膜孔内に気液界面が保持されることでガス交換が行われる。血漿蛋白が膜表面に吸着すると表面は親水化し、孔が濡れてプラズマリークの原因となるため「疎水性になる」は誤り。外部灌流型では血液が中空糸の外側(シェル側)を、ガスが中空糸内腔を通る。シェル側は実効流路断面積が大きく、内部灌流型に比べて圧力損失が小さい。また繊維束外側の流れは流路が複雑で乱流・擬似乱流成分が生じやすく、層流化しやすいとはいえない。多孔質膜では膜が気液界面を保持する形で血液とガスが孔内界面で接する概念であり、「直接接触しない」という一般的な“非接触(混合なし)”の表現とは区別される点に注意する。以上より正しいのは3と4。
選択肢別解説
誤り。疎水性多孔質膜に血漿蛋白が吸着すると表面は親水化し、孔が濡れやすくなってプラズマリークのリスクが増す。「疎水性になる」は逆である。
誤り。多孔質膜型では膜孔内に気液界面が保持され、血液は膜材とは隔てられるが、孔内の気液界面でガスと血液が接する概念である(非多孔質膜のような固体膜越しの溶解拡散とは異なる)。したがって「直接接触しない」という記述は本設問の多孔質膜の概念と合致しない。
正しい。外部灌流型は血液が中空糸の外側(シェル側)を流れるため有効流路断面積が大きく、内部灌流型(血液が中空糸内腔を流れる)に比べ圧力損失が小さくなりやすい。
正しい。外部灌流型の流路配置は、血液が中空糸の外側、ガスが中空糸の内側(内腔)を通る。
誤り。外部灌流型では繊維束外側の流路が複雑で、乱流・擾乱が生じやすく混合が促進される傾向がある。内部灌流型より層流になりやすいとはいえない。
解説を表示するにはログインが必要です。ログインすると無料枠(1日5問)をご利用いただけます。
無料プランでは解説を1日5問まで表示できます。解説を表示すると残り回数が消費されます。
今日: 回 | 残り 回
本日の無料枠を使い切りました。プレミアム登録で無制限にご利用いただけます。