臨床工学技士問題表示
臨床工学技士国家試験
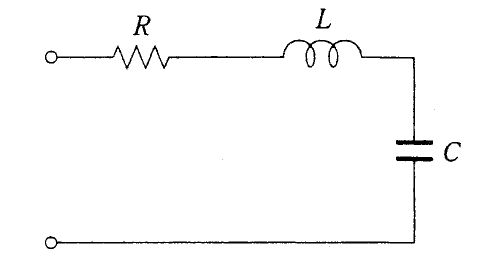
解説
超音波吸引手術器(CUSA など)は、おおむね数十kHz(典型的に20~40kHz台)の超音波振動をプローブ先端に与え、機械的振動とキャビテーション作用で軟らかい実質臓器などの組織を乳化・細分化しながら同時に吸引する装置である。体内に高周波電流を流すわけではないため対極板は不要で、止血能は電気メスに比べ限定的である。使用時は生理食塩液を灌流し、先端の冷却・破砕片の搬送・乳化の促進を図る。適応としては肝・脳の実質臓器手術に加え、眼科の白内障手術(超音波乳化吸引術:Phaco)でも広く用いられる。
選択肢別解説
誤り。超音波吸引手術器の振動周波数は一般に数十kHz(例:20~40kHz台)であり、5MHzのような高い周波数は超音波診断装置の送受信用プローブなどで用いられる帯域である。
誤り。超音波吸引手術器はプローブ先端の機械的超音波振動で組織を乳化・吸引するため、電気メスのように高周波電流を体内に流さない。よって対極板は不要である。
誤り。超音波吸引手術器の止血能は限定的で、特に太い・壁の薄い血管では十分な凝固が得られにくい。止血には電気メス(バイポーラなど)やクリップ・結紮の併用がしばしば必要であり、止血機能は電気メスに劣る。
正しい。生理食塩液を灌流しながら使用することで、プローブ先端や組織の冷却、破砕組織の乳化・搬送、吸引効率の向上、先端の過熱防止・閉塞予防が得られる。
正しい。白内障手術(超音波乳化吸引術:Phacoemulsification)で水晶体核を超音波で乳化し吸引除去する際に用いられる。ほかに脳腫瘍摘出や肝臓など実質臓器の部分切除にも適用される。
解説を表示するにはログインが必要です。ログインすると無料枠(1日5問)をご利用いただけます。
無料プランでは解説を1日5問まで表示できます。解説を表示すると残り回数が消費されます。
今日: 回 | 残り 回
本日の無料枠を使い切りました。プレミアム登録で無制限にご利用いただけます。
解説
超音波の波長は、波長 $\lambda$ と音速 $c$、周波数 $f$ の関係式 $\lambda = c/f$ で求める。生体軟部組織中の音速はおよそ 1500\,m/s(教科書的には 1500〜1540\,m/s)を用いる。周波数 1\,MHz = $1\times 10^6$\,Hz を代入すると、$\lambda = 1500 / (1\times 10^6) = 1.5\times 10^{-3}$\,m = 1.5\,mm となる。したがって、およその波長は 1.5\,mm。
選択肢別解説
誤り。0.015\,mm は 1.5\times 10^{-5}\,m であり、$f = c/\lambda$ に当てはめると約 100\,MHz に対応する値で、1\,MHz ではない。
誤り。0.15\,mm は 1.5\times 10^{-4}\,m で、対応周波数は $f = 1500 / 1.5\times 10^{-4} \approx 10\,\text{MHz}$。1\,MHz より 10 倍高い周波数での波長に相当する。
正しい。生体軟部組織の音速を約 1500\,m/s、周波数を 1\,MHz として $\lambda = c/f = 1500/(1\times 10^6) = 1.5\times 10^{-3}\,\text{m} = 1.5\,\text{mm}$ となる。
誤り。15\,mm は 1.5\times 10^{-2}\,m で、対応周波数は $f = 1500 / 1.5\times 10^{-2} \approx 0.1\,\text{MHz} = 100\,\text{kHz}$。1\,MHz より 1/10 の周波数に相当する。
誤り。150\,mm は 0.15\,m で、対応周波数は $f = 1500/0.15 = 10\,\text{kHz}$。超音波(数十 kHz 以上)としては低く、1\,MHz とは大きく異なる。
解説を表示するにはログインが必要です。ログインすると無料枠(1日5問)をご利用いただけます。
無料プランでは解説を1日5問まで表示できます。解説を表示すると残り回数が消費されます。
今日: 回 | 残り 回
本日の無料枠を使い切りました。プレミアム登録で無制限にご利用いただけます。