臨床工学技士問題表示
臨床工学技士国家試験
解説
植込み型不整脈治療機器の基本として、ICDは致死的不整脈に対する除細動・通電に加え、徐脈時のバックアップペーシングや頻拍停止目的の抗頻拍ペーシング(ATP)を備える機種が一般的であり、ペースメーカ機能を併せ持つ。CRT(CRT-P/CRT-D)は電気的不同期(例:左脚ブロック、QRS延長)を伴う心不全で両心室同期ペーシングにより機械的不同期を是正し、症状・予後の改善を図る治療である。リードレスペースメーカは現在広く用いられるものは右心室内に留置するシングルチャンバー型である。植込み型機器の電源は高エネルギー密度・長寿命・安全性の観点からリチウム系一次電池(例:リチウム‐ヨウ素、銀酸化バナジウム‐リチウムなど)が用いられ、アルカリ電池は用いない。リード留置は通常X線透視下で行い、超音波は静脈穿刺補助などで併用されることはあるが、リード誘導の主手段ではない。
選択肢別解説
正しい。ICDは除細動・通電による致死性頻脈治療に加え、徐脈時のバックアップペーシング機能や抗頻拍ペーシング(ATP)を備える機種が一般的であり、ペースメーカ機能を有する。
正しい。CRT(心臓再同期療法)用ペースメーカ/除細動器は、両心室を同期ペーシングして電気的・機械的不同期を是正し、心不全症例(特にQRS延長や左脚ブロックを伴うHFrEF)で症状・心機能・予後の改善を目的に用いられる。
正しい。現在一般に使用されるリードレスペースメーカ(例:右室内留置のシングルチャンバー型)はカプセル型デバイスを右心室心内膜側に固定して留置する。
誤り。植込み型機器の電源は高エネルギー密度・長寿命・低自己放電などの特性を持つリチウム系一次電池(例:リチウム‐ヨウ素、銀酸化バナジウム‐リチウム)が用いられる。アルカリ電池は植込み機器には用いない。
誤り。ペースメーカ/ICDの経静脈リード留置は原則としてX線透視下に行う。超音波は静脈穿刺(例:鎖骨下・腋窩静脈)の補助に用いられることはあるが、リード誘導の主たる画像誘導法ではない。
解説を表示するにはログインが必要です。ログインすると無料枠(1日5問)をご利用いただけます。
無料プランでは解説を1日5問まで表示できます。解説を表示すると残り回数が消費されます。
今日: 回 | 残り 回
本日の無料枠を使い切りました。プレミアム登録で無制限にご利用いただけます。
解説
医療機器の安全操作の原則として、患者に接続する前に機器の電源を入れて自己診断・設定確認を完了しておくのが適切である(誘導コードやプローブ装着前に起動・点検)。一方、医療ガス用ホースは使用の都度接続・取り外しを行い、放置接続は漏えい・汚染・機械的損傷やつまずきリスクを高め不適切。追加保護接地は規定された接地極や等電位(ボンディング)端子を用いるべきで、テレビのアンテナ端子など不確実な経路は不可。流量計の球形(ボール)浮子は浮子中心で目盛りを読み、上端で読むのは球形以外の浮子に適用される読取り法である。複数機器を電源供給する場合は接地極付き3Pの医用電源タップ(医療用規格適合)を用い、2Pタップの使用は安全上不適切である。
選択肢別解説
不適切。ホースアセンブリは使用のたびに端末器に接続し、使用後は外してキャップ等で端部を保護するのが原則。常時接続はガス漏えい・汚染混入・誤接続・機械的損傷やつまずき事故のリスクを高める。
適切。患者への誘導コード装着前に電源を入れて自己診断・初期化・アラームや設定値の確認を済ませておくと、異常時の影響を患者に及ぼしにくく、安全かつ確実に測定・治療を開始できる。
不適切。テレビのアンテナ端子は保護接地としての連続性やインピーダンスが保証されず、アイソレータ等で大地から浮いている場合もある。追加保護接地はコンセントの接地極や医用等電位ボンディング端子など、規定の接地点を用いる必要がある。
不適切。ボール型(球形浮子)の流量計は浮子の中心で目盛りを読む。上端で読むのは球形以外の一部浮子形状に対する読取り法であり、球形には適用しない。視差を避けるため指示線やミラーに合わせて読む。
不適切。医療機器は接地極付き3Pプラグが基本であり、複数機器を用いる場合は医療用規格に適合した3Pの医用テーブルタップ(過負荷保護等付き)を使用する。2Pタップは接地が取れず、漏れ電流や感電リスクの面で不適切。
解説を表示するにはログインが必要です。ログインすると無料枠(1日5問)をご利用いただけます。
無料プランでは解説を1日5問まで表示できます。解説を表示すると残り回数が消費されます。
今日: 回 | 残り 回
本日の無料枠を使い切りました。プレミアム登録で無制限にご利用いただけます。
解説
人工呼吸管理中の気管吸引は、低酸素血症・徐脈・肺虚脱・粘膜損傷などの合併症を最小化するために「必要時に、できるだけ短時間・低陰圧・細めのカテーテル」で行うのが原則である。具体的には、一回の吸引はおおむね10秒程度(最長でも15秒以内)にとどめ、成人の吸引圧はおよそ10〜20 kPa(約80〜150 mmHg)程度の範囲で最低有効圧を用いる。吸引カテーテルの外径は気管チューブ内径の50%以下とし、気道閉塞や陰圧過大による肺虚脱を避ける。また、気管吸引は適応(分泌物貯留、呼吸音の変化、SpO2低下、人工呼吸器のピーク圧上昇など)を評価して必要時に実施し、ルーチンの時間指定で行わない。実施者は医師や看護師に限定されず、施設の手順と教育を受けたコメディカル(臨床工学技士等)が関与し得る。
選択肢別解説
正しい。気管吸引は一回あたり10秒程度、長くとも15秒以内が一般的推奨で、長時間の吸引は低酸素血症や徐脈、粘膜損傷のリスクを高める。必要に応じて事前酸素投与やモニタ監視下で実施する。
誤り。気管吸引は医師・看護師に限られず、施設の手順・指示の下で、教育・訓練を受けたコメディカル(例:臨床工学技士等)が実施し得る医療行為である。したがって「医師または看護師だけ」に限定されない。
誤り。吸引は適応を評価して必要時に行うべきで、時刻を決めたルーチン実施は不要な侵襲や合併症(低酸素血症、粘膜損傷、VAPリスク増)を招く可能性がある。分泌物量、呼吸音、SpO2、人工呼吸器アラームなどで必要性を判断する。
誤り。成人の吸引圧はおおむね10〜20 kPa(約80〜150 mmHg)程度が目安で、必要最小限の陰圧を用いる。30 kPa(約225 mmHg)以上は過大で、粘膜損傷や肺虚脱のリスクが高まる。
正しい。吸引カテーテル外径は気管チューブ内径の50%以下が目安。太すぎるカテーテルは換気障害や陰圧過大を招き、無気肺や粘膜損傷のリスクを高める。例:内径8.0 mmのチューブなら外径4.0 mm以下(約12 Fr)が目安。
解説を表示するにはログインが必要です。ログインすると無料枠(1日5問)をご利用いただけます。
無料プランでは解説を1日5問まで表示できます。解説を表示すると残り回数が消費されます。
今日: 回 | 残り 回
本日の無料枠を使い切りました。プレミアム登録で無制限にご利用いただけます。
解説
テスト肺は人工呼吸器の患者側に接続して用いる模擬肺で、換気動作が設定どおりに出力されているか(圧・流量・回数・トリガ応答など)を負荷をかけた状態で確認するための道具である。したがって、患者回路側で観察できる回路内圧、換気回数、トリガ感度はテスト肺で確認できる。一方、電源電圧や医療ガス供給圧は供給側(入力側)の点検項目であり、内蔵計や外部計測器で確認すべき内容で、テスト肺の接続は前提でも必須でもない。以上より、回路内圧・換気回数・トリガ感度が該当する。
選択肢別解説
電源電圧は人工呼吸器の電源・電気系統の点検項目であり、テスト肺(患者側負荷)を接続しても評価対象とはならない。電圧は内蔵監視やテスター等で確認する。したがってテスト肺でチェックできる項目ではない。
医療ガス供給圧は供給源(ボンベ・中央配管)からの入力圧で、圧力計や人工呼吸器の供給圧表示で確認する。これは供給側の点検であり、テスト肺(患者側負荷)の有無に依存しないため、テスト肺でチェックする項目ではない。
回路内圧(ピーク圧、プラトー圧、PEEP など)は、テスト肺を接続して換気させることで実測・表示により確認できる。設定と表示が整合するか、過圧やリークの有無も併せて評価可能である。
換気回数(RR)は、テスト肺を接続して実際に換気させ、表示・波形や動作音などで1分当たりの回数が設定値と一致するかを確認できる。
トリガ感度は、テスト肺側で陰圧や流量変化を与える(テスト肺を軽く引く、回路を一時的に開放して負圧を作る等)ことで、設定感度で確実に呼吸器がトリガされるかを確認できる。
解説を表示するにはログインが必要です。ログインすると無料枠(1日5問)をご利用いただけます。
無料プランでは解説を1日5問まで表示できます。解説を表示すると残り回数が消費されます。
今日: 回 | 残り 回
本日の無料枠を使い切りました。プレミアム登録で無制限にご利用いただけます。
解説
PCIでは橈骨動脈や大腿動脈(必要に応じて上腕動脈)などの動脈アクセスからカテーテルを挿入し、X線透視・造影下にワイヤ/カテーテルを病変部へ誘導する。狭窄の拡張に用いる冠動脈バルーンは一般に高圧(およそ8~20気圧、約0.8~2.0 MPa)で加圧し、0.2 MPa(約2気圧)では不十分である。硬い石灰化病変に対するロータブレータ(回転アテレクトミー)では、切削片や器具占有により手技中に一過性のslow flow/血流低下が起こり得る。ステント留置後はステント血栓症予防のため、直後から抗血小板療法(通常は二剤併用)が必要である。以上より、正しい記述はロータブレータ施行時の一過性の冠血流低下に関する選択肢である。
選択肢別解説
誤り。冠動脈は大動脈起始の動脈系であり、PCIは橈骨動脈・大腿動脈(場合によっては上腕動脈)などの動脈アクセスから行う。上腕静脈は静脈系であり、PCIのルートとしては用いない(静脈アクセスは右心系カテーテルやデバイス留置で用いられる)。
誤り。カテーテルやガイドワイヤの誘導・位置確認は主にX線透視(血管造影装置)で行う。超音波(IVUS)は病変性状評価やステントサイズ決定・最適化に用いられる補助モダリティであり、「患部までの誘導」を超音波だけで行うわけではない。
誤り。冠動脈バルーンの拡張は通常8~20気圧程度(約0.8~2.0 MPa)で行う。0.2 MPa(約2気圧)は低すぎ、狭窄部の十分な拡張は得られない。
正しい。ロータブレータ(回転アテレクトミー)では、切削片の微小塞栓や器具による一時的占有・血管攣縮などにより、手技中に冠血流が一過性に低下(slow flow)することがある。これに対し、適切なラン(短時間・複数回)、血管拡張薬添加のフラッシュなどで対策する。
誤り。ステント留置後はステント血栓症予防のため抗血小板療法が必須で、通常はアスピリンとP2Y12阻害薬の二剤併用(DAPT)を直後から行う。「不要である」は不適切。
解説を表示するにはログインが必要です。ログインすると無料枠(1日5問)をご利用いただけます。
無料プランでは解説を1日5問まで表示できます。解説を表示すると残り回数が消費されます。
今日: 回 | 残り 回
本日の無料枠を使い切りました。プレミアム登録で無制限にご利用いただけます。
解説
$人工心肺では、動脈血酸素分圧(PaO2)は人工肺への吹送ガス中の酸素濃度(FiO2)で調整し、二酸化炭素分圧(PaCO2)は吹送ガス流量(スウィープ流量)で調整するのが基本である。体外循環の開始は、脱血が安定していることと血圧 \cdot 回路内圧 \cdot 気泡の有無を確認しながら低流量で立ち上げ、部分体外循環を経て目標灌流量(成人では灌流指数およそ2.2〜2.4 L/min/m^2を目安)に段階的に到達する。したがって「至適灌流量で体外循環を開始する」は不適切で誤り。上行大動脈遮断時は、一時的に送血流量(ひいては灌流圧)を下げることで遮断鉗子の適用を安全にし、大動脈壁への負荷や塞栓リスクを抑える。心停止中の左心腔の過伸展防止にはベント吸引で減圧する。離脱時はまず脱血(静脈側)を絞って生体側へ容量を戻し、自己拍出 \cdot 血圧を確認しながらポンプ流量を段階的に下げる。$
選択肢別解説
正しい。PaO2は人工肺に送る吹送ガス中の酸素濃度(FiO2)の増減で調整する。なおPaCO2は主に吹送ガス流量(スウィープ流量)で調整する点を併せて理解する。
$誤り。体外循環は低流量で立ち上げ、脱血の安定 \cdot 圧モニタ \cdot 回路内の安全を確認しつつ、部分体外循環を経て目標灌流量(成人での目安は灌流指数2.2〜2.4 L/min/m^2程度)へ段階的に増加させる。開始直後から至適灌流量とするのは急激な循環変動や回路トラブル時の危険を高めるため不適切。$
正しい。上行大動脈遮断時には一時的に送血流量を下げ、灌流圧を低めにして遮断鉗子の挿入・適用を容易かつ安全にする。高圧のまま遮断すると大動脈損傷や塞栓のリスクが増す。
正しい。心停止中に左心系へ還流する血液や気泡で過伸展・肺うっ血を来さないよう、左房や左室のベント吸引で心腔内を減圧する。吸引過多による空気誤吸引や組織損傷に注意する。
正しい。離脱開始時はまず脱血量(静脈側)を減らして心臓へ容量を戻し、自己拍出・血圧・充満圧を確認しながら送血流量を段階的に下げていく。これにより循環をスムーズに生体側へ移行できる。
解説を表示するにはログインが必要です。ログインすると無料枠(1日5問)をご利用いただけます。
無料プランでは解説を1日5問まで表示できます。解説を表示すると残り回数が消費されます。
今日: 回 | 残り 回
本日の無料枠を使い切りました。プレミアム登録で無制限にご利用いただけます。
解説
人工心肺(完全体外循環)中の安全管理では、空気誤送、動脈解離、脱血不良、人工肺血栓などの重大事象に対し、原因に即した初期対応が求められる。空気は貯血槽の液面低下だけでなく、脱血側の陰圧(VAVD)による吸気、回路接続部の緩み、ベントや心筋保護系からの逆流・逆転、人工肺内の脱ガスなど多経路で発生し得るため、貯血槽が空でなくても誤送は起こり得る。動脈解離が疑われる場合は解離腔の拡大を避けるため送血流量を直ちに低下または停止し、送血部位の変更準備や低体温化、圧モニタ・TEE等での確認を行う。脱血不良では原因(カニューレ先端の壁貼り付き、屈曲・閉塞、陰圧過大、循環血液量不足など)を同定し、カニューレの前後位置調整(しばしば浅く引き戻す)、回路確認、陰圧・ポンプ流量の整合、容量補充等で対処する。人工肺内血栓は圧力差上昇やガス交換不全を伴い致命的になり得るため、抗凝固状態の確認(ACT 等)を行いつつも基本対応は人工肺の速やかな交換であり、ヘパリン追加のみでは既存血栓は解決しない。脱血回路に持続的な微小気泡が見られる場合は陰圧過大や接続部吸気が疑われるため、陰圧やポンプ流量の調整、接続部の増し締め、容量補充、カニューレ位置調整など脱血側の是正を優先する。動脈側に空気が到達した場合に初めて送血停止が適応となる。
選択肢別解説
正しい。空気誤送は貯血槽の液面低下以外にも、脱血側の陰圧(VAVD)による吸気、回路接続部の微小リーク、ベント・心筋保護回路からの逆流やポンプ逆転、人工肺での脱ガスなど多経路で発生し得る。したがって貯血槽が完全に空でなくても空気が動脈側へ移行する危険はある。常にエアトラップ・フィルタ・監視を併用し、流量と陰圧の整合、接続部の点検を行う。
誤り。動脈解離が発生・疑われる場面で送血流量を増やせば解離腔へ灌流が集中し解離が進展する危険が高い。適切な対応は送血流量を低下または停止し、動脈圧を下げた上で送血部位変更(例:腋窩・大腿)、低体温化や循環停止の準備、TEEや圧ラインでの評価を行うことである。
誤り。脱血不良に対してカニューレをむやみに深く挿入すると、血管壁への貼り付きや狭小部への迷入でさらに流入が悪化することがある。まずはカニューレの前後位置を微調整(多くはやや引き戻す)、屈曲や陰圧過大の是正、循環血液量の補充、VAVD設定やポンプ流量の整合、必要に応じ二本目カニューレの追加などで対処する。
誤り。人工肺内血栓形成が疑われる場合、最優先は人工肺(必要により回路)の速やかな交換である。ACT低下など抗凝固不足があれば是正(ヘパリン追加)するが、追加投与のみでは既に形成された血栓は解消せず、塞栓やガス交換・圧損悪化の危険が続く。
誤り。脱血回路の持続的微小気泡は陰圧過大や接続部の吸気を示唆するため、まず脱血側の原因是正(陰圧や送血流量の調整、接続部の締結確認、容量補充、カニューレ位置調整等)を行う。動脈側への空気到達が確認・疑われる場合に送血停止を行うのであって、微小気泡が脱血側に限局する段階で直ちに送血を停止するのは一般的対応ではない。
解説を表示するにはログインが必要です。ログインすると無料枠(1日5問)をご利用いただけます。
無料プランでは解説を1日5問まで表示できます。解説を表示すると残り回数が消費されます。
今日: 回 | 残り 回
本日の無料枠を使い切りました。プレミアム登録で無制限にご利用いただけます。
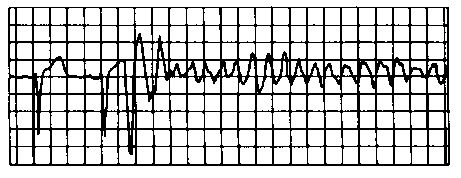
解説
電気メス起因が疑われる熱傷が術直後に判明した場合、臨床工学技士の初動は「患者安全の確保」「証拠保全」「機器点検」「記録化」の4点が基本となる。具体的には、使用したディスポーザブル対極板(コードやコネクタを含む)の回収・保管によって貼付状態や導通、ジェル状態、ロット情報等を後日検証できるようにする。さらに電気メス本体は高周波漏れ電流など安全性能を専用アナライザで点検し、機器側要因(異常な分流・漏れ)の有無を評価する。熱傷部は患者の同意を得たうえで写真撮影し、部位・大きさ・周囲皮膚の状態などを記録して経時的観察と原因究明に資する。一方、原因究明のために患者を手術室へ不必要に留め置くことは有害であり、必要な処置を行ったうえで適切な場所へ速やかに移送する。心電図モニタの「低周波」患者漏れ電流測定は電気メスによる高周波熱傷の原因解析としては不適切で、求められるのは高周波側の評価である。
選択肢別解説
正しい。事故対応では証拠保全が重要であり、使用済みディスポーザブル対極板(貼付部位・剥離状況・ジェル状態、コードやコネクタの接触不良の有無等)を回収・保管して後日の検証に備える。廃棄すると貼付不良や分流の手掛かりが失われる。
正しい。電気メス本体の高周波漏れ電流などの安全性能を専用アナライザで測定し、異常な分流や機器故障の有無を確認する。高周波領域の評価は高周波熱傷の原因究明に直結する。
誤り。心電図モニタの患者漏れ電流測定は主として低周波(商用周波数帯)評価であり、高周波電流が関与する電気メス熱傷の原因解析としては適切でない。必要なのは高周波側の分流・漏れの評価である。
誤り。原因究明が終わるまで患者を手術室に留め置くのは不適切。患者の安全と術後管理を優先し、必要な処置と記録を行ったうえで速やかに適切な病棟等へ移送し、原因調査は別途進める。
正しい。患者の同意を得たうえで熱傷部位を写真記録しておくことは、経過観察と原因究明に有用である(部位・大きさ・周囲皮膚の状態、スケール併記等)。個人情報保護と同意取得を徹底する。
解説を表示するにはログインが必要です。ログインすると無料枠(1日5問)をご利用いただけます。
無料プランでは解説を1日5問まで表示できます。解説を表示すると残り回数が消費されます。
今日: 回 | 残り 回
本日の無料枠を使い切りました。プレミアム登録で無制限にご利用いただけます。
解説
人工心肺(体外循環)中の代表的トラブルと初期対応の組合せを問う問題。脱血カニューレの脱落時は静脈リターンが急減しリザーバ血液量が低下、空気吸引による動脈側への空気誤送リスクが高い。直ちに送血ポンプを停止(または即時減速・停止)し、送血ライン遮断・心筋保護とともに原因除去を行うのが原則であり適切。膜型人工肺のwet lung(ガス側の結露・水侵入などによるガス交換低下)では、一時的にスイープガス流量増加や乾燥化で改善を試みるが、改善しなければ人工肺交換が適切。人工肺内の血栓形成に対しては、ヘパリン追加では既存血栓は溶解できず、圧較差増大やガス交換低下を伴えば酸素ator交換が原則であるため、提示の対応は不適切。熱交換器の水漏れは汚染・溶血や回路内への水混入の危険があり、原因部位である熱交換器(多くは人工肺一体型)自体の交換が必要で、冷温水槽の交換では解決しない。大動脈内への気泡誤送時は直ちにポンプ停止・動脈ライン遮断・Trendelenburg体位・大動脈基部ベント等での吸引などで対応し、必要に応じ回路再循環等を用いる。送血ポンプの逆回転は推奨されず不適切。したがって正しい組合せは1と2である。
選択肢別解説
正しい。脱血カニューレの脱落では静脈回路からの空気吸引によりリザーバが空になり、動脈側への空気誤送(空気塞栓)の危険が高い。直ちに送血ポンプを停止(または即時減速し停止)し、送血ラインの遮断・原因部位の確認と復旧を行うのが標準的対応である。
正しい。膜型人工肺のwet lung(ガス側結露・水侵入によるガス交換低下)は、一時的にスイープガス流量増加や乾燥化で改善を試みるが、改善しない場合は人工肺の交換が適切である。
誤り。人工肺内で形成済みの血栓はヘパリン追加投与では溶解できない。人工肺前後圧較差の上昇やガス交換能低下を伴う場合は回路停止手順を踏んだ上で人工肺の交換を検討するのが妥当である。
誤り。熱交換器の水漏れは血液汚染・溶血・回路内水混入の危険があるため、原因部位である熱交換器(多くは人工肺一体型)の交換が必要である。冷温水槽(ヒータークーラー)の交換では漏れ源を解決できない。
誤り。大動脈内への気泡誤送時は、即時の送血ポンプ停止・動脈ライン遮断・頭低位、可能なら大動脈基部ベント等での吸引、回路の再循環などで気泡除去を図る。送血ポンプの逆回転は推奨されず不適切である。
解説を表示するにはログインが必要です。ログインすると無料枠(1日5問)をご利用いただけます。
無料プランでは解説を1日5問まで表示できます。解説を表示すると残り回数が消費されます。
今日: 回 | 残り 回
本日の無料枠を使い切りました。プレミアム登録で無制限にご利用いただけます。
解説
人工心肺(体外循環)は心臓と肺の機能を一時的に代行する装置・回路で、静脈リザーバ(貯血槽)、血液ポンプ、人工肺、熱交換器、フィルタ、吸引系(心腔内・術野吸引)などで構成される。心臓手術で広く用いられている標準的な人工心肺回路は、大気に開放された静脈リザーバを備える開放回路型が主流である。血液ポンプは無拍動の定常流(ローラポンプや遠心ポンプ)が一般的で、拍動流は必須ではない。ECMOは長期循環補助を目的とした閉鎖回路で、人工心肺のような開放リザーバや術野吸引系を基本的に含まないため回路構成が異なる。体外循環時間は手術内容に応じて可変であり、3時間を超えて安全に運用されることも多い。
選択肢別解説
誤り。人工心肺は体循環と肺循環の双方を代行し、心臓手術中に全身の血液酸素化と灌流を担う。一方「左心補助」はLVADなど左心系に限定した補助であり、人工心肺の目的・適応とは異なる。
誤り。ECMOは長時間補助を目的とした閉鎖回路で、静脈リザーバ(大気開放の貯血槽)や心腔内・術野吸引系を基本構成に含まない。一方、人工心肺は開放リザーバや吸引系を備えるなど回路構成が異なる。
正しい。心臓手術で用いられる標準的な人工心肺回路は、大気に開放された静脈リザーバを持つ開放回路型が広く採用されている(ハードシェルリザーバ)。近年、閉鎖型や最小侵襲型(MiECC)もあるが主流は開放回路である。
誤り。人工心肺は無拍動の定常流で安全に運用されており、ローラポンプや遠心ポンプが主流である。拍動流ポンプは選択肢の一つではあるが「必要とする」わけではない。
誤り。体外循環に絶対的な「3時間の使用限界」はない。手術内容により2~3時間程度で終えることも多いが、4~6時間以上に及ぶ症例もあり、3時間を超えて運用されることは一般的である。
解説を表示するにはログインが必要です。ログインすると無料枠(1日5問)をご利用いただけます。
無料プランでは解説を1日5問まで表示できます。解説を表示すると残り回数が消費されます。
今日: 回 | 残り 回
本日の無料枠を使い切りました。プレミアム登録で無制限にご利用いただけます。