臨床工学技士問題表示
臨床工学技士国家試験
解説
人工心肺(CPB)では、低体温管理と希釈灌流が生体に特有の影響を与える。低体温では代謝率と酸素消費量が低下するため、必要な灌流量(至適灌流量)はむしろ減らせる方向となる。CPB中はストレスホルモンの上昇や低体温の影響で膵β細胞からのインスリン分泌が抑制されやすく、高血糖傾向を来す。希釈および低体温は酸素解離曲線を左方移動させ(酸素親和性増大)、一方で回路内のせん断応力や陰圧吸引・異物接触により溶血が生じ、血中遊離ヘモグロビンが増加する。さらに液体一般と同様に、体温低下は血液粘ちょう度を上昇させる。以上より、正しい選択肢は4と5である。
選択肢別解説
誤り。低体温では組織代謝と酸素消費量が低下するため、必要灌流量(至適灌流量)は増加ではなく低下方向に調整できる。体温を下げるほど多く流す必要はなく、むしろ過灌流を避ける。
誤り。CPBと低体温はストレスホルモン優位や膵分泌低下を介してインスリン分泌を抑制しやすく、血糖は上昇傾向となる。よって血中インスリン濃度が上昇するとは言えない。
誤り。体外循環に伴う血液希釈(プライミングによる急性希釈など)や低体温は、酸素解離曲線を左方へ移動させ酸素親和性を増大させる方向に働く(2,3-DPG低下や温度低下の影響など)。右方偏位とは逆。
正しい。人工心肺回路内でのポンプやチューブによるせん断、陰圧吸引、人工材料への接触などで溶血が生じ、血中遊離ヘモグロビンが増加する。溶血は腎機能障害や黄疸のリスクとなるため監視が重要。
正しい。液体の粘度は温度低下で上昇する性質があり、血液も同様に体温の低下で粘ちょう度が上昇する。CPBでは希釈により粘ちょう度を下げて血流維持を図ることがあるが、本設問の記述自体は正しい。
解説を表示するにはログインが必要です。ログインすると無料枠(1日5問)をご利用いただけます。
無料プランでは解説を1日5問まで表示できます。解説を表示すると残り回数が消費されます。
今日: 回 | 残り 回
本日の無料枠を使い切りました。プレミアム登録で無制限にご利用いただけます。
解説
単一故障状態(Single Fault Condition)は、医用機器の基本安全や本質性能を守るための保護手段が1つだけ失われた、または合理的に想定可能な単一の異常が生じた状態を仮定して安全性を評価する考え方である。JIS T 0601-1(IEC 60601-1)では、代表例として「電源導線の1本の断線」「F形装着部に外部電圧が現れる」「温度制御(または温度制限)機能の故障」「(フラマブル環境を想定する場合の)可燃性麻酔ガス等の漏れ」などが挙げられる。一方、「二重絶縁の双方が同時に短絡」といった二重の保護手段が同時に失われる事象は、単一故障ではなく二重故障に相当するため、単一故障状態には該当しない。したがって本問の正答は『二重絶縁の双方の短絡』である。
選択肢別解説
温度制御(あるいは温度制限)機能の故障は、加温・加熱回路の安全性評価で想定される典型的な単一故障状態である。温度上昇抑制の保護手段が1つ失われた状態として評価されるため、単一故障状態に該当する。従って本問(該当しないもの)の解としては不適。
可燃性麻酔混合ガスの漏れは、フラマブル環境で使用される機器を想定した安全性評価において、外装等からのガス漏えいを単一故障として仮定する例に該当する。よって単一故障状態に該当し、本問の解としては不適。
F形装着部(Type F applied part)に外部電圧が現れる事象は、装着部の絶縁・隔離機能の一部喪失を仮定する単一故障状態の典型例である。従って単一故障状態に該当し、本問の解としては不適。
二重絶縁の双方の短絡は、独立した2つの保護手段が同時に失われる状態であり、単一故障ではなく二重故障に相当する。よって単一故障状態には該当しないため、本問の正答に該当する。
機器の電源導線の1本の断線は、電源系の単一の断線を仮定する典型的な単一故障状態である。よって単一故障状態に該当し、本問の解としては不適。
解説を表示するにはログインが必要です。ログインすると無料枠(1日5問)をご利用いただけます。
無料プランでは解説を1日5問まで表示できます。解説を表示すると残り回数が消費されます。
今日: 回 | 残り 回
本日の無料枠を使い切りました。プレミアム登録で無制限にご利用いただけます。
解説
血液透析中に装置が「常時監視」すべきなのは、重大な事故や膜破損を即時に検知して治療を自動停止・警報できる項目です。血液系では気泡(空気塞栓の危険)を超音波式エア検知器で連続監視します。透析液系ではダイアライザ破損による漏血を光学式センサで、透析液圧を圧力センサで常時監視し、これらはTMP管理や回路異常の早期検出にも不可欠です。一方、血漿浸透圧は患者検査項目で装置による連続測定対象ではなく、透析液エンドトキシン濃度は水質管理(LAL法等)として定期測定であり常時監視には当たりません。従って、常時監視すべきは「気泡」「漏血」「透析液圧」です。
選択肢別解説
血漿浸透圧は患者側の検査指標であり、透析装置がセンサで連続的に監視する項目ではない。通常は治療前後や必要時に検査で評価されるため「常時監視」の対象外。
気泡(空気)は血液回路内に混入すると空気塞栓の重大リスクがあるため、超音波式エア検知器で連続監視され、検知時は血液ポンプ停止・静脈側クランプ等の安全動作が作動する。よって常時監視項目である。
漏血はダイアライザ膜破損により血液が透析液側へ漏れる事象で、光学式(赤外線等)センサで透析液排液を連続監視する。検知時は警報・治療停止が行われるため、常時監視項目に該当する。
透析液圧(入口・出口圧など)は圧力センサで常時計測され、血液側との圧力差(TMP)管理や回路閉塞・リーク等の異常検出に不可欠である。したがって常時監視項目である。
透析液エンドトキシン濃度は透析液水質管理の指標で、LAL試験等により定期的(例:月1回以上など施設基準に準拠)に測定されるのが一般的であり、装置によるリアルタイム連続監視の対象ではない。
解説を表示するにはログインが必要です。ログインすると無料枠(1日5問)をご利用いただけます。
無料プランでは解説を1日5問まで表示できます。解説を表示すると残り回数が消費されます。
今日: 回 | 残り 回
本日の無料枠を使い切りました。プレミアム登録で無制限にご利用いただけます。
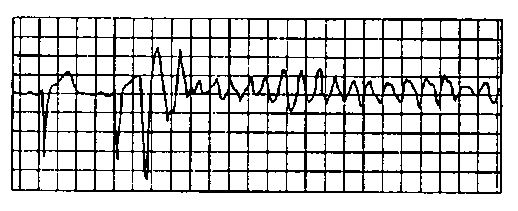
解説
体外循環では、回路充填や循環動態の維持、腎・脳保護のために薬剤を適切に選択する。マンニトールは浸透圧性利尿薬として浸透圧を調整し腎保護に寄与する。アドレナリンは強力なカテコールアミンで心収縮力を増強し離脱時の循環補助に用いる。乳酸加リンゲル液は細胞外液組成に近い平衡晶質液で、充填・希釈に用い体液(細胞外液)補正に資する。アルブミン製剤は膠質浸透圧を維持し循環血液量の保持に役立つ。一方、ハプトグロビン(設問の表記は誤記)製剤は溶血で生じた遊離ヘモグロビンと結合して腎障害を予防する目的で投与され、出血予防(止血)目的の薬剤ではない。したがって「ハプトグロビン製剤—出血の予防」は誤りである。
選択肢別解説
マンニトールは浸透圧性利尿薬で、回路充填液に添加して浸透圧を調整し、利尿を促進して尿量を確保することで腎保護に寄与する。脳浮腫軽減などの目的にも適合し、組合せは妥当である。
アドレナリン(エピネフリン)はβ1作用による心収縮力増強(陽性変力作用)と心拍数増加、α作用による血圧維持作用を持ち、体外循環離脱時の低心拍出や低血圧の是正に用いられる。目的の記載は適切である。
正しくはハプトグロビン製剤で、遊離ヘモグロビンと結合して腎尿細管障害を予防することが主目的である。出血の予防(止血)目的では用いないため、組合せは誤りである。出血予防には一般に抗線溶薬(例:トラネキサム酸)などを用いる。
乳酸加リンゲル液はNa、Cl、K、Ca、乳酸を含む平衡晶質液で細胞外液組成に近く、回路充填・希釈での細胞外液量の補正に用いられる。記載の目的は妥当である。
アルブミン製剤は血漿膠質浸透圧を維持・調整し、循環血液量の保持や組織浮腫の抑制に有用である。体外循環の充填液に併用されることがあり、目的の記載は適切である。
解説を表示するにはログインが必要です。ログインすると無料枠(1日5問)をご利用いただけます。
無料プランでは解説を1日5問まで表示できます。解説を表示すると残り回数が消費されます。
今日: 回 | 残り 回
本日の無料枠を使い切りました。プレミアム登録で無制限にご利用いただけます。
解説
体外循環では血液が人工物表面に接触し、非生理的な圧力・せん断応力や希釈、補体活性化などを受け、溶血・血小板減少・白血球動態変化・免疫機能低下が生じる。送血ポンプ(ローラ/遠心いずれも)による過大な陰圧・陽圧や高いせん断応力は赤血球膜を損傷し溶血の原因となる。リンパ球は接触活性化・サイトカイン環境・ステロイド投与等の影響で機能低下(T細胞・NK細胞活性低下)を示す。顆粒球は開始直後は肺へのトラッピング等により一過性に減少し、その後反跳的に増加しうるため「開始直後から増加」は誤り。血小板は希釈、表面吸着、活性化・消費で減少するが一般に30〜50%程度で、70〜80%減少は過大表現で通常所見とは言い難い。溶血では遊離ヘモグロビンがハプトグロビンと結合して消費され、血中ハプトグロビン濃度は低下する。
選択肢別解説
正しい。送血ポンプのローラ圧過大、遠心ポンプの高回転・吸引、狭小回路での高せん断などにより赤血球膜が損傷し溶血が生じる。所見として血漿遊離ヘモグロビン上昇、LDH上昇、間接ビリルビン上昇、尿中ヘモグロビンなどを認めうる。対策は適正オクルージョン・回転数管理、陰圧・吸引の最小化、気泡回避など。
正しい。体外循環に伴う補体活性化・サイトカイン放出、人工物表面接触、希釈やステロイド投与などにより、T細胞やNK細胞の数や機能が一過性に低下し、細胞性免疫が抑制される。術後感染リスクやウイルス再活性化の一因となる。
誤り。顆粒球(好中球)は人工心肺開始直後は肺毛細血管へのトラッピングや接触活性化による辺縁化で一過性に減少し、その後リバウンド的に増加することが多い。「開始直後から増加」とする記載は適切でない。
誤り。血小板は希釈、人工物表面への吸着、活性化・消費、剪断応力などで減少するが、一般的には30〜50%程度の減少が多い。70〜80%減少は通常の体外循環の範囲を超える大幅減少で、他病態(重度出血、HITなど)の関与を疑う所見である。
誤り。溶血で増加するのは血漿遊離ヘモグロビンであり、ハプトグロビンはこれと結合して肝で処理されるため消費され低下する。溶血進行時はハプトグロビン低下、遊離ヘモグロビン上昇が典型である。
解説を表示するにはログインが必要です。ログインすると無料枠(1日5問)をご利用いただけます。
無料プランでは解説を1日5問まで表示できます。解説を表示すると残り回数が消費されます。
今日: 回 | 残り 回
本日の無料枠を使い切りました。プレミアム登録で無制限にご利用いただけます。