臨床工学技士問題表示
臨床工学技士国家試験
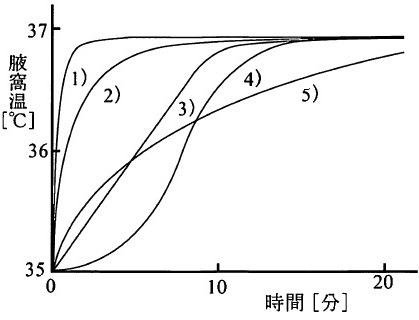
解説
生体計測で用いるトランスデューサは、物理量(圧力、温度、光、超音波など)を電気信号へ変換する素子である。超音波診断装置は圧電素子で電気エネルギーと音響エネルギーを相互変換する。熱希釈式心拍出量計は血液温変化を高感度に検出するサーミスタを用いる。カプノメータはCO₂の赤外線吸収特性を利用し、赤外線検出素子で濃度(分圧)を測定する。観血式血圧計は受圧部の変形をストレインゲージの抵抗変化として検出する。一方、パルスオキシメータは赤色光と赤外光の透過・反射の変動をフォトダイオード等の光電変換素子で受光して酸素飽和度を算出するため、磁界検出用のホール素子は用いない。したがって「パルスオキシメータ—ホール素子」の組合せが誤りである。
選択肢別解説
超音波診断装置の振動子は圧電現象を利用する圧電素子で、送受信の双方で電気—音響エネルギーを相互変換する。適切な組合せである。
熱希釈式心拍出量計では、冷却液注入後の血液温の時間変化をサーミスタで検出して心拍出量を算出する。温度検出素子としてサーミスタを用いるのは正しい。
パルスオキシメータは赤色光と赤外光の吸光度比を用い、受光にはフォトダイオード等の光電変換素子を用いる。ホール素子は磁界検出用であり本装置には不適切。よってこの組合せは誤り。
カプノメータはCO₂が中赤外域を吸収する性質を利用し、赤外線検出素子で吸収量を測ってCO₂濃度(分圧)を求める。適切な組合せである。
観血式血圧計では受圧膜の変形(圧力)をストレインゲージの抵抗変化として電気信号に変換する。一般的で適切な組合せである。
解説を表示するにはログインが必要です。ログインすると無料枠(1日5問)をご利用いただけます。
無料プランでは解説を1日5問まで表示できます。解説を表示すると残り回数が消費されます。
今日: 回 | 残り 回
本日の無料枠を使い切りました。プレミアム登録で無制限にご利用いただけます。
解説
経皮的血液ガス分析装置は、皮膚表面をおおむね $42\sim 44^\circ\text{C}$ に加温して毛細血管を動脈化し、血液ガスが角質層を拡散してくる分圧を電極で連続測定する。電極はガス透過膜を介して皮膚に密着させ、酸素はクラーク電極、二酸化炭素はセベリングハウス電極で検出するのが一般的である。組織での酸素消費や皮膚の拡散抵抗のため、経皮的酸素分圧 $\text{PtcO}_2$ は通常、動脈血酸素分圧 $\text{PaO}_2$ より低く出る。一方で二酸化炭素は皮膚代謝の影響で $\text{PtcCO}_2$ が $\text{PaCO}_2$ より高くなりやすい。以上より、「$\text{PtcO}_2$ は $\text{PaO}_2$ より高値」とする記述は誤り。新生児のように動脈血採血が困難な症例で非侵襲・連続モニタとして有用である。
選択肢別解説
正しい。新生児は反復的な動脈採血が困難で侵襲も大きいため、非侵襲かつ連続的に酸素化・換気の指標を得られる経皮的測定が広く用いられる。
正しい。皮膚を約 $42\sim 44^\circ\text{C}$(設問の43℃程度)に加温して血流を増やし、毛細血管を動脈化し、皮膚のガス透過性を高めて測定の追従性と精度を確保する。
誤り。皮膚組織での酸素消費と拡散抵抗のため、経皮的酸素分圧 $\text{PtcO}_2$ は一般に動脈血酸素分圧 $\text{PaO}_2$ より低値となる。したがって「$\text{PtcO}_2$ は $\text{PaO}_2$ よりも高値を示す」は不適切。
正しい。電極はガス透過膜(酸素用クラーク電極、二酸化炭素用セベリングハウス電極)を介して皮膚に密着させ、皮膚から拡散してくるガスを検出する。
正しい。加温により動脈化された毛細血管の血液ガスが角質層を通って皮膚表面へ拡散した分圧を測定しており、原理に合致する記述である。
解説を表示するにはログインが必要です。ログインすると無料枠(1日5問)をご利用いただけます。
無料プランでは解説を1日5問まで表示できます。解説を表示すると残り回数が消費されます。
今日: 回 | 残り 回
本日の無料枠を使い切りました。プレミアム登録で無制限にご利用いただけます。