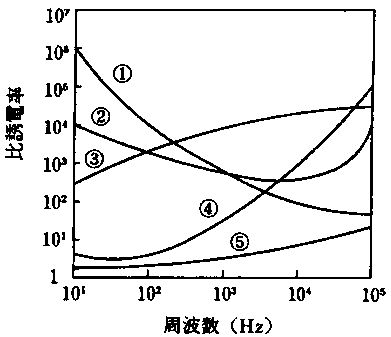第40回ME2午前50問の類似問題
ME2第28回午前:第54問
厚さの等しい血液層に同じ強度の光を照射したとき、最も透過光強度が強くなる組合せはどれか。なお、図はヘモグロビンの吸光係数の波長特性を示す。ただし、血液のヘマトクリット値はすべて同じとし、動脈血の酸素飽和度は97%、静脈血では70%とする。
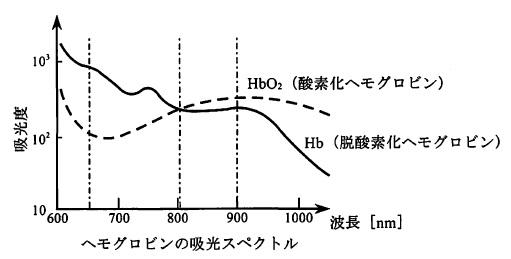
1:静脈血 -- 波長650nm
2:動脈血 -- 波長650nm
3:静脈血 -- 波長805nm
4:動脈血 -- 波長900nm
5:静脈血 -- 波長900nm
国試第18回午前:第55問
血液計測で誤っているのはどれか。(生体計測装置学)
1:電磁流量計の原理は電磁誘導である。
2:経皮的ドプラ血流計は無侵襲計測器である。
3:色素希釈法は心拍出量測定に用いられる。
4:プレチスモグラフィは組織血流計測に用いられる。
5:熱希釈式心拍出量計測法は大動脈血液温の変化を利用している。
国試第33回午前:第28問
トランジットタイム型超音波血流計の特徴で正しいのはどれか。
a:伝搬時間を利用する。
b:複数チャネルの同時計測が可能である。
c:ゼロ点補正が必要である。
d:体表面からの測定が可能である。
e:一つの超音波振動子で計測できる。
1. a b 2. a e 3. b c 4. c d 5. d e