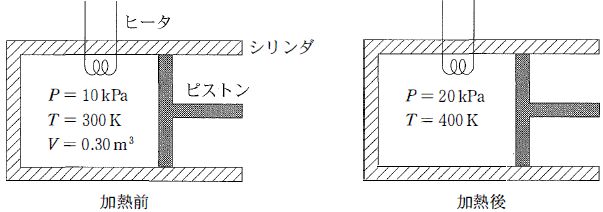第18回国試午後84問の類似問題
国試第29回午前:第70問
人工肺に用いられるポリプロピレン多孔質膜について正しいのはどれか。
1:親水性である。
2:膜厚は200?400 nm である。
3:微細孔の大きさは10?nm である。
4:物質移動係数はシリコーン均質膜よりも高い。
5:ポリプロピレンの気体透過係数はシリコーンよりも高い。
国試第21回午後:第62問
塩化ナトリウム、塩化カルシウム、ブドウ糖をそれぞれ1mmol溶かして1Lにした水溶液の浸透圧濃度はどれか。
1:2mOsm/L
2:3mOsm/L
3:4mOsm/L
4:5mOsm/L
5:6mOsm/L
ME2第30回午前:第38問
5%のブドウ糖液で生ずる浸透圧の値は何mOsm/Lになるか。
1:9
2:20
3:36
4:278
5:556
国試第6回午後:第72問
大気圧プラス2気圧の高気圧酸素治療を行うとき、生体内の気泡について正しいのはどれか。
a:気泡は体積も圧力も変わらない。
b:気泡の体積は1/2になる。
c:気泡の体積は1/3になる。
d:気泡の圧力は3絶対気圧になる。
e:気泡の圧力は2絶対気圧になる。
1. a b 2. a e 3. b c 4. c d 5. d e
国試第6回午前:第62問
生体膜における輸送現象に関係のないのはどれか。
1:浸透圧
2:蠕動運動
3:拡散
4:組織圧
5:能動輸送
国試第36回午後:第33問
皮膚を通して生体内に伝達される物理的エネルギーによって、生体に何らかの不可逆的な障害が生じるとされているエネルギー密度の下限はどれか。
1:1mW/cm2
2:10mW/cm2
3:100mW/cm2
4:1W/cm2
5:10W/cm2
国試第12回午後:第58問
1mmol/l のブドウ糖溶液、NaCl溶液及びCaCl2溶液のそれぞれの浸透圧(mOsm/l) はどれか。ブドウ糖溶液,NaCl溶液,CaCl2溶液
1:1, 1, 1
2:1, 2, 1
3:1, 2, 2
4:1, 2, 3
5:2, 2, 3
国試第5回午後:第60問
皮膚を通して生体内に伝達される物理的エネルギーによって、生体に不可逆的な障害が生じるといわれているエネルギー密度の限界値はどれか。
1:100μW/cm2
2:100mW/cm2
3:100W/cm2
4:100kW/cm2
5:100MW/cm2
国試第4回午後:第55問
皮膚を通して生体内に伝達される物理的エネルギーによって、生体になんらかの不可逆的な障害を生じるといわれているエネルギー密度の限界値はどれか。
1:10μW/cm2
2:100μW/cm2
3:10mW/cm2
4:100mW/cm2
5:1000mW/cm2