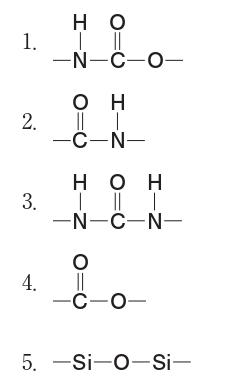生体物性材料工学の過去問
国試第32回午前:第27問
生体用金属電極について正しいのはどれか。
a:電極と生体間の接触面積を大きくすると電極接触インピーダンスは増加する。
b:周波数が高くなると電極接触インピーダンスは増加する。
c:電極用ペーストは電極接触インピーダンスを下げる効果がある。
d:新しい金属電極はエージング後の電極と比べて基線の変動が大きい。
e:電極電位は使用する金属の種類によって異なる。
1. a b c 2. a b e 3. a d e 4. b c d 5. c d e