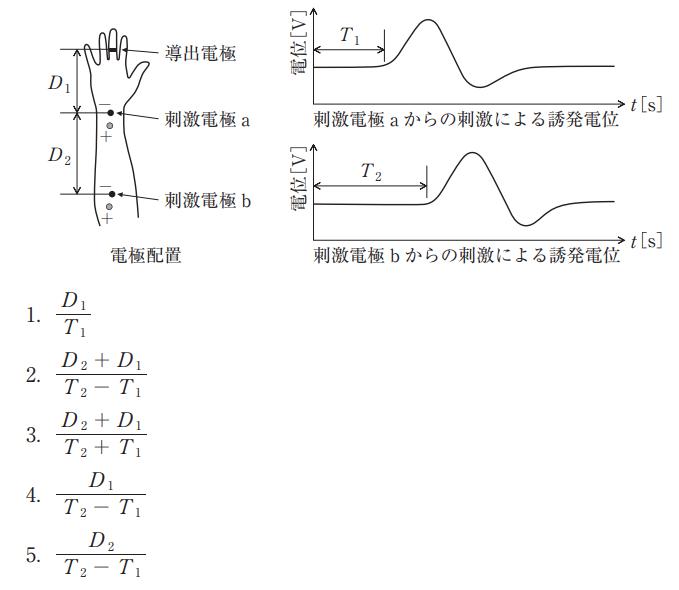臨床工学技士問題表示
臨床工学技士国家試験
大分類
生体計測装置学
20問表示中
広告
36
第二種ME技術認定試験 -
第37回 午後
科目:
熱希釈式心拍出量測定について誤っているのはどれか。
1
カテーテル先端は肺動脈に留置する。
2
右心房の位置にあるカテーテル側孔から注入液を注入する。
3
注入液には約0℃の5%ブドウ糖液を使用する。
4
注入液量に応じてカテーテル係数を変更する。
5
注入液はゆっくり注入する。
22
臨床工学技士国家試験 -
第36回 午前
重要度:低
正答率:95%
科目:
麻酔中のカプノメータによるモニタリングで検出できないのはどれか。
1
呼吸回路脱離
2
食道挿管
3
不整脈
4
肺塞栓症
5
低換気
広告
29
臨床工学技士国家試験 -
第36回 午前
重要度:低
正答率:89%
パルスオキシメータの測定誤差の要因とならないのはどれか。
1
患者の体動
2
大気圧の低下
3
末梢循環不全
4
異常ヘモグロビン
5
診断用色素の投与
30
臨床工学技士国家試験 -
第36回 午前
重要度:重要
正答率:76%
科目:
経皮的血液ガス分析について正しいのはどれか。
1
皮下の血流増加のために加温する。
2
計測には脈波信号が必要である。
3
赤外線の吸収を計測している。
4
新生児には使用できない。
5
侵襲的な計測方法である。
31
臨床工学技士国家試験 -
第36回 午前
重要度:低
正答率:63%
超音波画像計測について正しいのはどれか。
a
生体軟部組織中の音速は約340m/sである。
b
超音波の周波数が高いほど体内での減衰が小さい。
c
超音波は音響インピーダンスが異なる界面で反射する。
d
心室壁の厚さを測定できる。
e
血管内から血管の断面を観察できる。
組み合わせ:
1. a b c
2. a b e
3. a d e
4. b c d
5. c d e
広告
40
第二種ME技術認定試験 -
第36回 午前
科目:
オシロメトリック法を用いた自動血圧計について誤っているのはどれか。
1
カフの装着位置が多少でもずれると測定誤差が生じる。
2
カフ部の圧力の微小変化を検出している。
3
水銀血圧計を基準として校正されている。
4
厚地の着衣の上からカフを装着すると測定誤差が生じる。
5
脈波の大きさの変化から血圧値を算出している。
41
第二種ME技術認定試験 -
第36回 午前
科目:
観血式血圧計について誤っているのはどれか。
1
CF形装着部を持つ増幅器が使用される。
2
トランスデューサを右房より高く設置すると平均血圧が高く表示される。
3
カテーテル内に気泡が入ると波形が歪む。
4
フラッシングによりカテーテルの詰まりを予防する。
5
測定系全体の共振周波数は高いほどよい。
43
第二種ME技術認定試験 -
第36回 午前
超音波診断装置について誤っているのはどれか。
1
音響レンズで超音波を集束できる。
2
超音波が平面波のままで伝播する領域を近距離音場という。
3
画像上で胆石の後方が黒い影になる現象を音響陰影という。
4
サイドローブからの反射は実像と重なってアーチファクトとして表示される。
5
超音波の周波数が高いほど深部臓器の観察ができる。
44
第二種ME技術認定試験 -
第36回 午前
科目:
18FDG PET検査について誤っているのはどれか。
1
18Fはポジトロン核種である。
2
18FDGはグルコース代謝の活発な細胞に特異的に集まる。
3
18FDGはサイクロトロンで生成する。
4
18Fから放出されるβ線を検出する。
5
厚い放射線遮へい壁が必要である。
広告
87
臨床工学技士国家試験 -
第36回 午前
正答率:82%
体表から非接触で体温を測定するときに用いるのはどれか。
1
ステファン・ボルツマンの法則
2
ランベルト・ベールの法則
3
ニュートンの法則
4
フックの法則
5
スネルの法則
4
第二種ME技術認定試験 -
第36回 午後
科目:
SPECTについて誤っているのはどれか。
1
X線CTに比べ空間分解能が高い。
2
RIからのγ線を検出する。
3
コンピュータで画像化する。
4
3次元画像が得られる。
5
放射線被曝がある。
広告