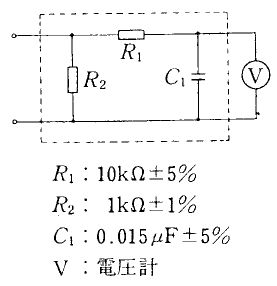第4回国試午後75問の類似問題
国試第13回午前:第78問
正しいのはどれか。
1:1W/cm2の超音波の照射で血中に気泡が発生する。
2:1Tの静磁場では心室細動が起こる。
3:10mW/cm2のCO2レーザを胸部に照射すると呼吸が停止する。
4:45°Cで皮膚表面を3時間加温すると熱傷が起こる。
5:1.5N/m2の圧縮荷重で健常人の大腿骨が骨折する。