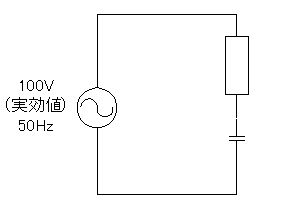第25回国試午後41問の類似問題
国試第27回午後:第38問
医療機器と注意すべき傷害との組合せで正しいのはどれか。
1:非観血式血圧モニタ 不整脈
2:パルスオキシメータ キャビテーション
3:経皮的酸素分圧測定装置 熱 傷
4:レーザ手術装置 ミクロショック
5:超音波吸引手術装置 紅 斑
国試第17回午前:第77問
誤っているのはどれか。
a:ビリビリと感じ始める電流値を最小感知電流という。
b:人体への電撃の作用機序は電流によって発生する熱による組織破壊である。
c:商用交流電流が危険なのは人体組織がこの周波数付近の電流を最も流しやすいからである。
d:電気メスで心室細動が起こらないのは高周波電流を使用しているからである。
e:右房圧のモニタリングではミクロショックの危険がある。
1. a b 2. a e 3. b c 4. c d 5. d e
国試第6回午前:第78問
生体電気現象の計測について正しいのはどれか。
a:低周波領域では電極接触インピーダンスは周波数に比例する。
b:金属と電解液の接触面では静止電位が発生する。
c:電極に電流が流れると静止電位の他に電極と生体間に分極電圧が発生する。
d:生体と電極との接触インピーダンスはできるだけ小さい方がよい。
e:増幅器の入力インピーダンスはできるだけ小さい方がよい。
1. a b c 2. a b e 3. a d e 4. b c d 5. c d e
国試第6回午後:第75問
医療の現場で注意すべき安全問題について誤っているのはどれか。
1:電気的安全問題の中には情報のひずみや他の機器への干渉が含まれる。
2:複数機器の同時使用時には機器単体使用時に比べて安全性は低下する。
3:過大エネルギー投与に折る熱傷の防止には適切な出力選択が必要である。
4:火花を伴う機器には取扱上の制限が必要である。
5:機械的安全問題の中には]機器の腐食や爆発が含まれる。
国試第7回午前:第80問
生体電気計測に使用するフィルタについて正しいのはどれか。
a:帯域除去フィルタの代表的なものはハム除去フィルタである。
b:低域遮断フィルタを備えた増幅器をAC増幅器という。
c:集積回路を利用したフィルタを受動フィルタという。
d:静止電位の測定にはAC増幅器を用いなければならない。
e:分極などによる不要な直流成分やドリフトを除去するにはDC増幅器を用いるとよい。
1. a b 2. a e 3. b c 4. c d 5. d e
ME2第34回午後:第27問
経皮的血液ガス分圧測定装置について正しいのはどれか。
1:センサ付近の加温は体温以下にする。
2:センサの加温は装着後に行う。
3:センサの装着は血流のよい部位とする。
4:長期間の測定ではセンサ装着部位を変更しない。
5:低心拍出量患者での測定が可能である。
国試第4回午後:第80問
JIS-T-1022「病院電気設備の安全基準」で非常電源について正しいのはどれか。
a:非常電源で用いられる自家用発電設備は連続して最小限40時間運転できる。
b:瞬時特別非常電源の最少連続運転時間は15分である。
c:非常電源用のコンセントの外郭表面は赤色である。
d:手術灯の電源回路には瞬時特別非常電源を設けなければならない。
e:特別非常電源の電圧確立時間は10秒以内である。
1. a b c 2. a b e 3. a d e 4. b c d 5. c d e