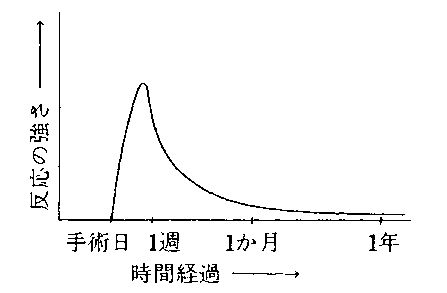臨床工学技士問題表示
臨床工学技士国家試験
解説
医用材料が体内に置かれると、異物反応としてカプセル化(線維性被膜の形成)、補体活性化(C3a・C5aなどアナフィラトキシン産生)、石灰化(リン酸カルシウム沈着)、血栓形成(血小板と凝固系の活性化)、炎症(ヒスタミンなどメディエーター放出)といった生体反応が起こりうる。カプセル化は線維芽細胞が産生するコラーゲンにより異物周囲に被膜が形成される現象で妥当、補体活性化はアナフィラトキシン(C3a、C5aなど)の産生と対応、石灰化はリン酸カルシウム(ハイドロキシアパタイトなど)の沈着と対応、炎症はヒスタミン放出と対応する。一方、血栓形成は血小板粘着・凝集とフィブリノーゲン→フィブリン形成(凝固系)によるもので、エラスチンは血管壁の弾性線維の主要成分であり血栓形成そのものの担い手ではないため、4が誤りの組合せである。
選択肢別解説
正しい組合せ。異物の慢性局所反応であるカプセル化では、線維芽細胞が産生するコラーゲンにより線維性被膜が形成され、医用材料が周囲組織から隔離される。
正しい組合せ。補体が活性化されるとC3aやC5a(場合によりC4a)などのアナフィラトキシンが生成し、血管透過性亢進、平滑筋収縮、好中球遊走などの炎症反応を惹起する。
正しい組合せ。生体材料周囲にリン酸カルシウム(ハイドロキシアパタイトなど)が沈着して硬化する石灰化は、慢性反応として知られる。
誤った組合せ。血栓形成は血小板の粘着・凝集と凝固因子によりフィブリノーゲンがフィブリンへ転換して進行する。関連因子はvWF、トロンビン、フィブリノーゲンなどであり、エラスチンは血管壁の弾性線維の主要構成蛋白で血栓形成の主要因子ではない。
正しい組合せ。炎症初期には肥満細胞や好塩基球からヒスタミンが放出され、血管拡張や血管透過性の亢進を引き起こす。
解説を表示するにはログインが必要です。ログインすると無料枠(1日5問)をご利用いただけます。
無料プランでは解説を1日5問まで表示できます。解説を表示すると残り回数が消費されます。
今日: 回 | 残り 回
本日の無料枠を使い切りました。プレミアム登録で無制限にご利用いただけます。
解説
医用材料が血液に触れると、まず数秒以内に血漿タンパク質(特にフィブリノーゲン、アルブミン、免疫グロブリンなど)が材料表面に吸着し(Vroman効果)、吸着・変性したタンパク質を介して血小板の粘着・活性化が起こる。さらに材料表面での接触相(内因系)の活性化により凝固カスケードが進み、フィブリン形成へ至る。従って「血小板の粘着」「血液凝固系の活性化」「タンパクの吸着」はいずれも起こり得る現象である。一方、通常の医用材料が血液と接触しただけで化学反応により気体が発生したり、材料自体が融解することは想定されない。
選択肢別解説
血小板は材料表面にまず吸着したフィブリノーゲンやvWFなどを介して粘着し、形態変化・活性化・放出反応・凝集へ進むため、実際にみられる現象である。
材料表面は血漿タンパク質の吸着・変性を引き起こし、内因系(接触相:XII因子など)の活性化を介して凝固系が進展する。したがって正しい。
通常の医用材料と血液の単純接触で化学的に気体が生成されることはない。ガス発生は想定されないため不適。
血液成分により材料が融解することは通常起こらない。生体接触で想定されるのは表面でのタンパク吸着や血栓形成関連反応であり、融解は誤り。
血液接触の最初期現象は血漿タンパク質の迅速な吸着(Vroman効果)で、後続の血小板粘着・凝固活性化の前提となるため正しい。
解説を表示するにはログインが必要です。ログインすると無料枠(1日5問)をご利用いただけます。
無料プランでは解説を1日5問まで表示できます。解説を表示すると残り回数が消費されます。
今日: 回 | 残り 回
本日の無料枠を使い切りました。プレミアム登録で無制限にご利用いただけます。
解説
体内に植え込まれた材料と生体は相互作用し、変化は大きく「生体側の反応」と「材料側の変化」に分けられる。肉芽形成・血小板活性化・補体活性化・(仮に生じるとしても)がん化はいずれも生体側で起こる現象であり、材料自体の性状が変わるわけではない。一方、腐食は金属材料そのものが体液中で酸化還元反応によりイオンとして溶出し、孔食・すき間腐食・ガルバニック腐食などを通じて機械的強度や表面性状が低下する「材料側の変化」である。よって材料側に起こる変化として該当するのは腐食である。
選択肢別解説
誤り。肉芽形成は生体側の創傷治癒・異物反応の一部で、炎症後に線維芽細胞や新生血管が増生して形成される。材料自体の性状が変化する現象ではない。
誤り。血小板活性化は血液適合性に関わる生体側(血液側)の反応で、材料表面への蛋白吸着・血小板付着を介して生じるが、変化の主体は生体の血小板機能であり材料側の物理化学的性状変化ではない。
誤り。補体活性化は生体防御系のカスケードであり生体側の反応である。材料表面が引き金になることはあるが、材料自体が変質するわけではない。
誤り。がん化は生体組織の細胞学的変化であり材料側の変化ではない。動物での報告はあるが、ヒトで材料接触が直接原因と断定できる腫瘍形成の知見は限定的とされる。
正しい。腐食は材料側の変化で、金属が体液(塩化物イオン、溶存酸素など)環境で酸化還元反応によりイオン化・溶出し、孔食・すき間腐食・ガルバニック腐食などを生じうる。結果として機械的強度低下や表面性状の悪化、金属イオンの遊離を来す。
解説を表示するにはログインが必要です。ログインすると無料枠(1日5問)をご利用いただけます。
無料プランでは解説を1日5問まで表示できます。解説を表示すると残り回数が消費されます。
今日: 回 | 残り 回
本日の無料枠を使い切りました。プレミアム登録で無制限にご利用いただけます。
解説
血液に直接触れる材料(体外循環回路、カテーテル、人工血管など)では、血液適合性として血栓形成性、溶血性、補体系活性化などの血液学的・血栓止血学的反応を最小化できるかが重要である。材料表面へのタンパク質吸着を端緒として血小板活性化や内因系凝固が進み血栓形成を招きうる。また溶出物や表面特性により赤血球膜が損傷すれば溶血が起こる。さらに材料表面は補体の古典経路・代替経路・レクチン経路を介した補体活性化を誘発し炎症反応を増強する。一方、被包化や肉芽形成は主に埋植材料に対する組織(間質)側の異物反応であり、血液と接触した際の血液適合性とは評価領域が異なる。以上より、血液適合性に関係するのは「溶血」「血栓形成」「補体活性化」である。
選択肢別解説
正しい。溶出物(可塑剤・残留モノマーなど)や表面粗さ・親水疎水性・帯電などにより赤血球膜が損傷すると溶血が生じる。血液適合性評価では溶血性試験(ヘモリシス率など)が実施され、溶血の有無は重要な判定項目である。
正しい。材料表面へのタンパク質吸着と変性を契機に血小板の付着・活性化が進み、内因系凝固カスケードが作動して血栓形成に至る。血栓形成性(抗血栓性)は血液適合性の中心的評価項目であり、血管内留置デバイスや体外循環回路では特に重要となる。
誤り。被包化(線維性被膜形成)は埋植材料に対する慢性の異物反応で、周囲組織に肉芽・線維化が進んで材料を被膜で囲む現象である。これは主として組織適合性(組織反応)の領域であり、血液と接触した際の血液適合性の評価項目とは異なる。
誤り。肉芽形成は炎症や創傷治癒過程で線維芽細胞や新生血管を含む肉芽組織が形成される現象で、埋植材料に対する組織側の反応を示す。血液適合性の直接的な評価項目ではない。
正しい。材料表面は補体の古典経路・代替経路・レクチン経路の活性化を誘発しうる。補体活性化は発熱・炎症・白血球活性化や血小板機能へも波及し、血液適合性評価で確認すべき重要な反応である。
解説を表示するにはログインが必要です。ログインすると無料枠(1日5問)をご利用いただけます。
無料プランでは解説を1日5問まで表示できます。解説を表示すると残り回数が消費されます。
今日: 回 | 残り 回
本日の無料枠を使い切りました。プレミアム登録で無制限にご利用いただけます。
解説
血液が医用材料表面に触れると、最初に起こるのは血漿タンパク質(アルブミン、フィブリノーゲン、免疫グロブリンなど)の極めて迅速な吸着である(ミリ秒〜秒)。吸着に伴ってタンパク質が部分的に変性し、露出したドメインが内因系凝固の活性化(接触因子活性化)や補体系活性化、さらには血小板の粘着・活性化の足場となる。したがって一連の血液適合性反応の出発点はタンパク質吸着である。血小板粘着や凝固・線溶、石灰化などはこの後段で起こる。
選択肢別解説
正しい。材料表面への血漿タンパク質の迅速な吸着が最初の事象であり、以後の血小板粘着・凝固・補体活性化などの生体反応はこのタンパク質層(しばしば変性を伴う)に規定されて進行する。
誤り。線溶は凝固により形成されたフィブリンをプラスミンが分解する過程であり、凝固反応の後段に位置する。材料接触直後の第一段階ではない。
誤り。赤血球凝集は血漿タンパク質架橋や免疫学的要因、低せん断などの条件で生じ得るが、材料接触直後に普遍的に最初に起こる現象ではない。初発はタンパク質吸着である。
誤り。血小板粘着は、まず表面に吸着・変性したフィブリノーゲンやvWF等を介して生じるため、タンパク質吸着の後に続く段階である。
誤り。石灰化はリン酸カルシウム沈着などによる慢性期の現象で、材料表面の長期的変化に属する。接触直後の初発反応ではない。
解説を表示するにはログインが必要です。ログインすると無料枠(1日5問)をご利用いただけます。
無料プランでは解説を1日5問まで表示できます。解説を表示すると残り回数が消費されます。
今日: 回 | 残り 回
本日の無料枠を使い切りました。プレミアム登録で無制限にご利用いただけます。
解説
本問は代表的な生体反応の組合せ判定。石灰化は組織や材料表面へのリン酸カルシウム(主にアパタイト)沈着で正しい。血栓形成はトロンビン活性化によりフィブリノーゲンがフィブリンへと変換され進行するため「トロンビンの活性阻害」は誤り。アナフィラキシーはIgE依存のI型アレルギーで、主役は肥満細胞の脱顆粒でありT細胞活性化が主となるIV型とは異なるため誤り。血液凝固では露出コラーゲンは血小板接着の足場として働き、コラーゲン分解は凝固の本質ではないため誤り。炎症では急性期の好中球に続き慢性期にマクロファージ浸潤が顕著であり正しい。従って正しい組合せは1と5。
選択肢別解説
正しい。石灰化は生体内でリン酸カルシウム(ハイドロキシアパタイトなど)が沈着し硬化する現象で、異所性石灰化として医用材料周囲でも起こり得る。
誤り。血栓形成にはトロンビンの活性化が不可欠で、トロンビンがフィブリノーゲンをフィブリンへ変換して血栓を形成する。「活性阻害」はヘパリン等の抗凝固作用の説明であり、血栓形成の記述としては逆。
誤り。アナフィラキシーはI型アレルギーで、IgEと抗原の架橋により肥満細胞が脱顆粒しヒスタミンなどを放出する。T細胞の活性化が主となるのはIV型アレルギー(遅延型)。
誤り。血液凝固では血管損傷により露出したコラーゲンが血小板接着・活性化の足場となる。コラーゲンの分解は凝固の中心的過程ではない。
正しい。炎症反応では急性期に好中球が、慢性期にはマクロファージやリンパ球が浸潤する。特に慢性炎症でマクロファージ浸潤が顕著。
解説を表示するにはログインが必要です。ログインすると無料枠(1日5問)をご利用いただけます。
無料プランでは解説を1日5問まで表示できます。解説を表示すると残り回数が消費されます。
今日: 回 | 残り 回
本日の無料枠を使い切りました。プレミアム登録で無制限にご利用いただけます。
解説
医療機器の生物学的評価は、ISO 10993/JIS T 0993-1に基づき、患者接触の有無・接触部位・接触時間に応じて試験項目が選定される。主要評価(基本的にまず検討される試験)のうち、細胞毒性試験は広範な機器で必須とされる代表的項目で、抽出液法・直接接触法などで材料の細胞に対する毒性を評価する。一方、埋植試験は体内に埋め込む機器や長期接触(例:30日超)などで局所組織反応を確認するために義務づけられる。慢性毒性や発癌性は長期暴露を前提とする特殊・追加評価であり、通電性は生物学的評価ではなく電気的安全・性能評価の範疇である。
選択肢別解説
慢性毒性は長期暴露に関する評価で、必要性は材料特性や接触時間(長期接触・植込み等)により個別判断される追加的評価である。主要評価試験として一律に義務づけられる項目ではないため、不適切。
発癌性(遺伝毒性・変異原性評価と関連)は、懸念がある材料や長期暴露が想定される場合に検討される追加試験であり、主要評価として一律に義務づけられるわけではない。不適切。
細胞毒性試験は生物学的評価の基本項目であり、材料からの溶出物や直接接触が細胞へ与える毒性を評価する。広く義務的に要求される主要評価試験で、抽出液法・直接接触法・寒天拡散法などが用いられる。適切。
埋植試験は、植込み型機器や組織・血液と長期に接触する機器で局所組織反応を確認する主要評価として義務づけられる。人工弁、人工血管、長期留置カテーテル等で必須となる。適切。
通電性は電気的安全・性能に関する評価事項であり、生物学的評価(生体適合性)に含まれない。したがって主要評価試験としての義務項目ではない。不適切。
解説を表示するにはログインが必要です。ログインすると無料枠(1日5問)をご利用いただけます。
無料プランでは解説を1日5問まで表示できます。解説を表示すると残り回数が消費されます。
今日: 回 | 残り 回
本日の無料枠を使い切りました。プレミアム登録で無制限にご利用いただけます。
解説
医療機器材料の生物学的安全性評価では、JIS T 0993(ISO 10993)に基づき、感作性、刺激性、全身毒性(急性~慢性)、遺伝毒性(変異原性)、血液適合性などの試験区分に分けて評価する。感作性試験は皮膚でのアレルギー性(遅延型過敏反応)を、刺激性試験は皮膚・粘膜・眼などの局所刺激反応をみる。トキシコキネティクスは化学物質の体内動態(吸収・分布・代謝・排泄:ADME)を扱う。血液適合性試験には溶血性の評価が含まれる。一方、慢性毒性試験は長期間の反復曝露による全身毒性(臓器毒性など)をみる試験であり、染色体の変異は遺伝毒性(変異原性)試験の評価項目である。よって「慢性毒性試験 ― 染色体の変異」の組合せが誤りとなる。
選択肢別解説
正しい組合せ。感作性試験は材料やその抽出物が皮膚にアレルギー性(遅延型過敏反応)を惹起するかを評価し、皮膚の組織反応の程度(紅斑・浮腫など)で判定する。
正しい組合せ。刺激性試験は材料や抽出物が生体組織に与える局所刺激を評価し、皮膚や粘膜に加えて眼刺激性の評価も行われる。したがって「目(眼)の組織反応」は刺激性試験の対象として妥当である。
誤った組合せ。慢性毒性試験は長期間(反復曝露)における全身毒性や臓器影響を評価する。一方、染色体の変異は遺伝毒性(変異原性)試験の評価項目であり、慢性毒性試験の本来の指標ではない。
正しい組合せ。トキシコキネティクス(毒物動態学)は化学物質の体内動態(ADME:吸収・分布・代謝・排泄)を解析する学問領域であり、定義に合致する。
正しい組合せ。血液適合性試験には、材料に起因する溶血(赤血球破壊)の評価が含まれる。その他にも血栓形成傾向、凝固・補体系活性化などが評価対象となるが、溶血反応は代表的な指標である。
解説を表示するにはログインが必要です。ログインすると無料枠(1日5問)をご利用いただけます。
無料プランでは解説を1日5問まで表示できます。解説を表示すると残り回数が消費されます。
今日: 回 | 残り 回
本日の無料枠を使い切りました。プレミアム登録で無制限にご利用いただけます。
解説
医療機器の生物学的安全性評価は ISO 10993-1(JIS T 0993-1)に基づき、「生体との接触部位」と「接触時間」によって機器を分類し、その分類に応じて必要な評価項目(例:細胞毒性、感作性、刺激性/皮内反応、急性・亜急性・亜慢性全身毒性、遺伝毒性、埋植試験など)を選択する。接触面積は分類基準には用いない。なお抽出試験の条件設定(表面積/抽出液量比など)では面積が関与するが、これは評価の前処理条件であり、分類軸ではない。したがって「生体と接触する面積で分類される」は誤りとなる。
選択肢別解説
正しい。感作性試験は ISO 10993-1(JIS T 0993-1)で示される生物学的評価項目の一つで、該当する接触部位・接触時間の機器に対して必要に応じて実施される(アレルギー誘発の有無を評価)。
正しい。細胞毒性試験は基本的な初期スクリーニングであり、多くの医療機器材料で求められる。抽出物または直接接触により細胞への毒性(生存率低下、増殖阻害など)を評価する。
正しい。分類は接触時間に依存し、一時的(24時間以内)、短期(24時間超〜30日以下)、長期(30日超)に区分される。時間区分により要求される評価項目が異なる。
誤り。生物学的安全性評価の分類は接触部位と接触時間で行い、接触面積は分類基準ではない。面積は抽出試験の条件設定(表面積/抽出液量比)などで考慮されるが、分類そのものには用いない。
正しい。分類は接触部位に依存し、表面接触(皮膚、粘膜、損傷皮膚など)、外部と体内を連結する機器(血液路等)、体内埋込機器などのカテゴリで評価項目が決まる。
解説を表示するにはログインが必要です。ログインすると無料枠(1日5問)をご利用いただけます。
無料プランでは解説を1日5問まで表示できます。解説を表示すると残り回数が消費されます。
今日: 回 | 残り 回
本日の無料枠を使い切りました。プレミアム登録で無制限にご利用いただけます。
解説
医療機器の生物学的安全性評価は ISO 10993-1(JIS T 0993-1 に相当)に基づき、機器の接触部位(表面接触:皮膚・粘膜・損傷皮膚など)と接触時間で必要な試験項目を選定する。表面接触機器では、基本的評価として細胞毒性試験と感作性試験(加えて通常は刺激性/皮膚刺激性試験)を実施する。一方、血液適合性試験は血液に接触する機器で必要、埋植試験は体内に埋め込まれる機器の局所反応評価で必要、発がん性試験は長期埋植や遺伝毒性所見等がある場合に限り検討するもので、表面接触機器に一律には求められない。したがって本問では細胞毒性試験と感作性試験が正しい。
選択肢別解説
誤り。血液適合性試験は血液と直接接触する機器(体外循環回路、血管内留置器具など)で評価が必要となる。表面接触機器(皮膚・粘膜・損傷皮膚など)に血液接触がない場合は原則不要である。
誤り。埋植試験(implantation test)は体内に埋め込まれる機器や材料の局所組織反応を評価するための試験であり、体表や粘膜などの表面接触機器には通常適用されない。
正しい。細胞毒性試験はすべての接触機器で基本的に実施が推奨される基礎評価項目であり、表面接触機器でも必須の評価とされる。
正しい。感作性試験(皮膚感作性)は表面接触機器における重要な評価項目であり、材料由来のアレルギー誘発性の有無を確認するため実施が求められる。
誤り。発がん性試験は長期(一般に30日超)の埋植機器や、遺伝毒性試験結果などにより必要性が示唆される場合に検討される。表面接触機器に一律で要求される試験ではない。
解説を表示するにはログインが必要です。ログインすると無料枠(1日5問)をご利用いただけます。
無料プランでは解説を1日5問まで表示できます。解説を表示すると残り回数が消費されます。
今日: 回 | 残り 回
本日の無料枠を使い切りました。プレミアム登録で無制限にご利用いただけます。
解説
誤りは「人工腎臓には再吸収機能がある。」である。人工腎臓(血液透析器・ダイアライザ)は半透膜を介した拡散(透析)と圧力差による限外濾過(濾過)で溶質・水分を除去する装置であり、腎臓の近位〜遠位尿細管・集合管で行われる能動輸送やチャネル制御に基づく再吸収・分泌機能は備えていない。その他の選択肢は、医用材料の基礎として妥当である。生体適合性に求められる要件は使用部位(血液・組織接触の有無)、使用期間、機能要求などにより異なり、材料選定にも影響する。EOG(エチレンオキサイドガス)滅菌は低温での滅菌が可能なため、熱に弱い高分子・複合材などで用いられる。ニッケルを含む形状記憶合金など、アレルギー原因となり得る元素を含む医用材料は実在する。生体吸収性材料は体内で加水分解・生体吸収されるため、長期強度維持には不向きで、非吸収性材料と比べ耐久性は低い。
選択肢別解説
正しい。生体適合性の要求水準は用途・接触部位(血液接触、皮下、骨内など)、使用期間(短期・長期)、必要な機械的特性や表面特性によって変わるため、材料(およびその使われ方)によって求められる要件は異なる。
正しい。EOG(エチレンオキサイドガス)滅菌は低温で行えるため、高圧蒸気滅菌に耐えない熱可塑性樹脂や複合材、電子部品を含む医療機器などの滅菌に用いられる。残留ガス低減のためのエアレーション管理が必要である。
誤り。人工腎臓(ダイアライザ)は半透膜による拡散(透析)と限外濾過(濾過)で老廃物や水分を除去する受動輸送主体の装置であり、腎尿細管の能動輸送により行われる電解質・水の再吸収機能は有していない。
正しい。医用材料の中にはアレルギーの原因となり得る元素を含むものがある。例としてニッケルを含むニッケル–チタン合金(形状記憶合金)や、コバルト・クロムを含む合金などが挙げられる。使用時は生体適合性評価やアレルギーリスクの管理が重要である。
正しい。生体吸収性材料(例:ポリグリコール酸、ポリ乳酸、コラーゲンなど)は体内で分解・吸収される設計であるため、時間経過とともに機械的強度が低下し、長期耐久性は非吸収性材料に劣る。吸収性縫合糸や一時的インプラントなどの用途に適している。
解説を表示するにはログインが必要です。ログインすると無料枠(1日5問)をご利用いただけます。
無料プランでは解説を1日5問まで表示できます。解説を表示すると残り回数が消費されます。
今日: 回 | 残り 回
本日の無料枠を使い切りました。プレミアム登録で無制限にご利用いただけます。