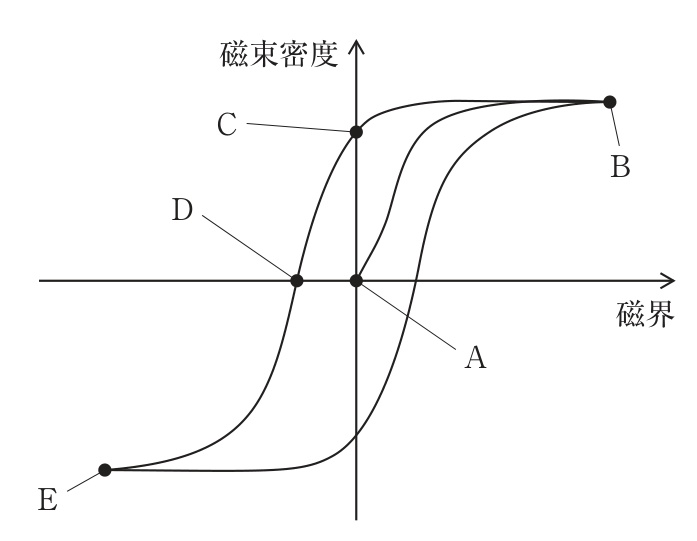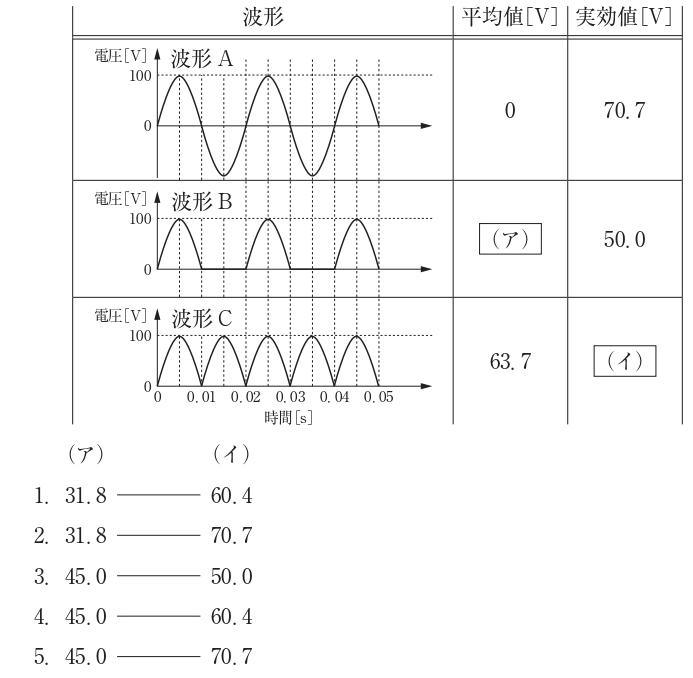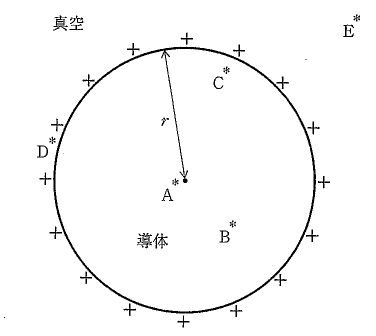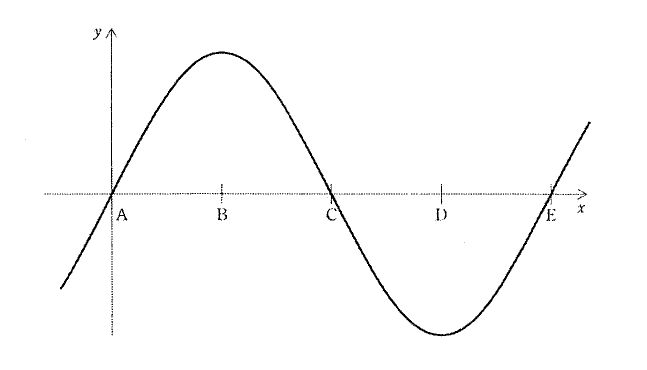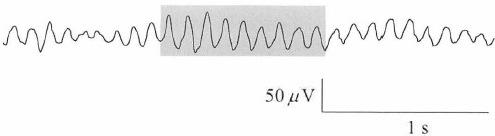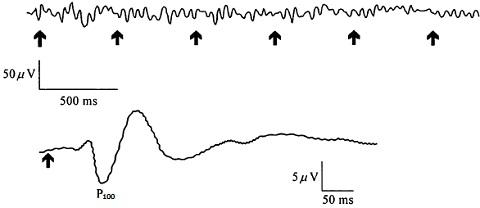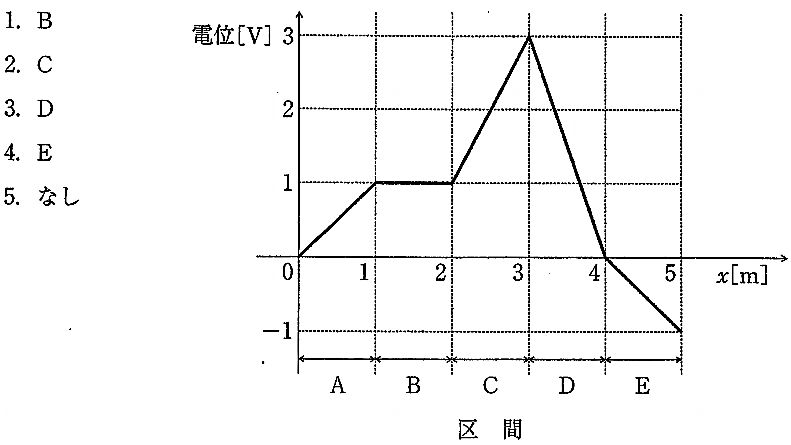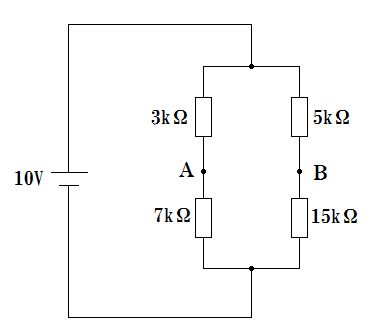第9回国試午後79問の類似問題
国試第26回午後:第25問
適切でない組合せはどれか。
a:ベクトル心電図 -------------- ゴールドバーガー誘導法
b:脳 波 --------------------- 10/20法
c:筋電図 -------------------- 針電極
d:心磁図 -------------------- SQUID
e:眼振図 -------------------- 圧電素子
1. a b 2. a e 3. b c 4. c d 5. d e