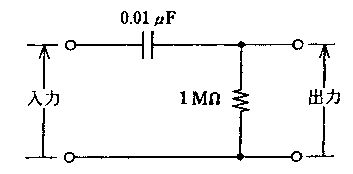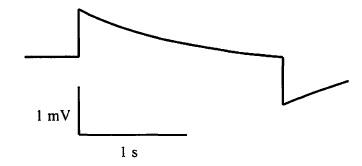第39回ME2午後19問の類似問題
国試第3回午前:第81問
光→電気変換器を使用するのはどれか。
1:脳波計
2:筋電計
3:指先容積脈波計
4:pHメータ
5:眼振計