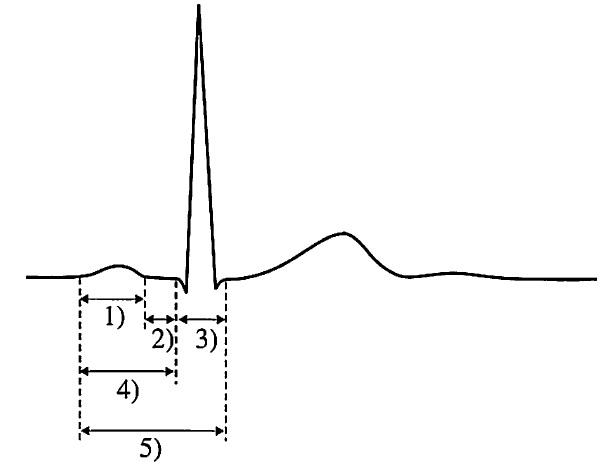第4回国試午前77問の類似問題
国試第30回午前:第38問
300 kHzの交流電流を1 秒間通電したときの感知電流の閾値[mA]に近いのはどれか。
1:30
2:100
3:150
4:300
5:500
国試第32回午前:第29問
トランジットタイム型超音波血流計について正しいのはどれか。
a:複数チャネルの同時計側か可能である。
b:電気的干渉を受けやすい。
c:測定開始前にゼロ点補正が必要である。
d:体外循環用のチューブで使用可能である。
e:内胸動脈グラフトで使用可能である。
1. a b c 2. a b e 3. a d e 4. b c d 5. c d e