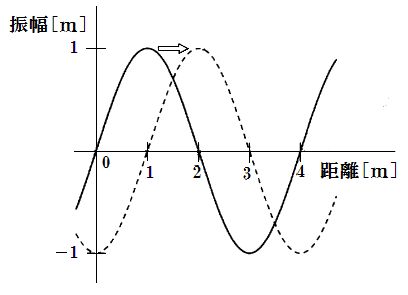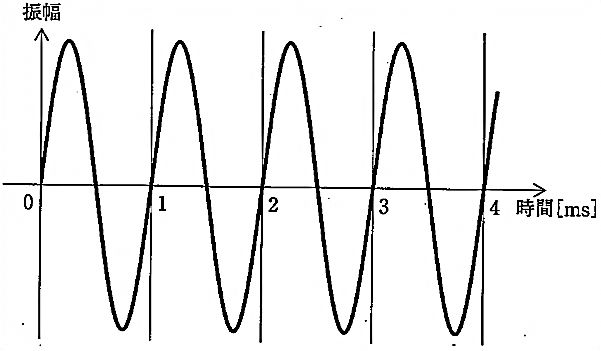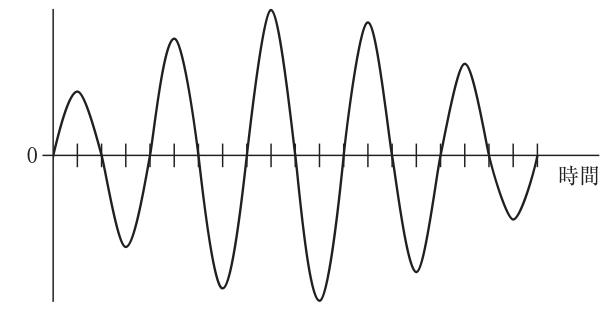第4回国試午前55問の類似問題
国試第9回午後:第71問
正しいのはどれか。
a:外力により物体内部に生じる単位面積当たりの力を応力という。
b:外力により生じた長さの変化量を変形前の長さで割った値をひずみという。
c:太さが一様な丸棒にかかる応力をその結果生じるひずみで割った値をポアソン比という。
d:弾性係数は単位の応力を与えるひずみである。
e:切り欠けのある材料が外力に対して破壊しやすいのは応力集中を生じるためである。
1. a b c 2. a b e 3. a d e 4. b c d 5. c d e