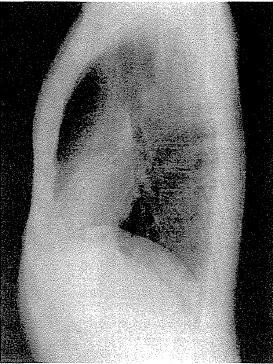臨床工学技士問題表示
臨床工学技士国家試験
解説
$正しいのは4。CT値は水を基準(0 HU)として定義され、空気は約-1000 HU、骨は数百HU以上となる。定義式は HU = 1000 \times \frac{\mu - \mu_{water}}{\mu_{water}}(\mu は線減弱係数)であり、骨を基準にはしない。臨床用X線CTのスライス厚は一般に0.5〜10 mm程度で、50 µmのような極薄スライスは臨床CTでは用いない(それは主にマイクロCTの領域)。空間分解能も臨床装置でおおむね0.3〜0.5 mm程度であり、5 mmは粗すぎて不適切。時間差分法はデジタルサブトラクションアンギオグラフィ(DSA)の時間サブトラクションで、造影前(マスク像)を造影後(ライブ像)から差し引き血管のみを強調する。ヨード系造影剤は原子番号が高くK吸収端(約33 keV)付近でのフォトン吸収が大きく、X線減弱が大きいのでコントラスト増強に用いられる。$
選択肢別解説
$誤り。CT値(HU)は水の線減弱係数を基準(0 HU)として定義される。定義式は HU = 1000 \times \frac{\mu - \mu_{water}}{\mu_{water}}。骨は基準ではなく、結果として数百HU以上の高い値を示す。$
誤り。臨床用X線CTのスライス厚は通常0.5〜10 mm程度で設定される。50 µm(0.05 mm)は臨床CTとしては極端に薄く、主にマイクロCTの領域である。
誤り。X線CTの空間分解能は臨床装置でおおむね0.3〜0.5 mm程度(高分解能で約0.3 mm)であり、5 mmという値は粗すぎる。
正しい。時間差分法(DSAの時間サブトラクション)は、造影剤投与前のマスク像を、投与後のライブ像から減算して血管像を強調する手法である。
誤り。ヨード系造影剤は高い原子番号によりX線のフォトエレクトリック効果が増大し、X線減弱(吸収)が大きい。したがってコントラスト増強に用いられる。
解説を表示するにはログインが必要です。ログインすると無料枠(1日5問)をご利用いただけます。
無料プランでは解説を1日5問まで表示できます。解説を表示すると残り回数が消費されます。
今日: 回 | 残り 回
本日の無料枠を使い切りました。プレミアム登録で無制限にご利用いただけます。
解説
MRIは主に水素原子核の核スピンが静磁場中で示すラーモア歳差運動をRFパルスで励起し、縦緩和(T1)・横緩和(T2)などの緩和過程で生じる信号を検出して画像化する。位置情報は傾斜磁場で空間的にラーモア周波数や位相を位置依存に変化させて符号化(スライス選択・周波数エンコード・位相エンコード)する。検査室は外来ノイズの侵入・RF漏洩を防ぐため通常シールドルームが必要であり、またMRIはX線撮影に比べ軟部組織のコントラスト分解能に優れる。
選択肢別解説
誤り。MRIは電子スピンではなく原子核(主に水素原子核)の核スピンによる核磁気共鳴を利用する。電子スピンを用いる手法はESR/EPRであり、臨床MRIとは異なる。
誤り。緩和は励起された核磁化が平衡状態へ戻る過程を指し、縦磁化の回復(T1)や横磁化の位相揃いの崩れ(T2)で表される。歳差運動そのものの回転が遅くなることを意味しない(ラーモア周波数自体が変わるわけではない)。
誤り。MRI装置は外部電波ノイズの侵入やRF漏洩を防ぐため、通常RFシールド(シールドルーム)が必要となる。「必要としない」は不適切。
正しい。傾斜磁場を印加すると位置ごとにラーモア周波数や位相が変化し、スライス選択・周波数エンコード・位相エンコードによって信号の発生位置(空間情報)を取得できる。
正しい。MRIは軟部組織間のコントラスト分解能が高く、X線撮影(主に骨の描出に優れる)よりも軟部組織の描出に優れる。
解説を表示するにはログインが必要です。ログインすると無料枠(1日5問)をご利用いただけます。
無料プランでは解説を1日5問まで表示できます。解説を表示すると残り回数が消費されます。
今日: 回 | 残り 回
本日の無料枠を使い切りました。プレミアム登録で無制限にご利用いただけます。
解説
MRIは強磁場中で水素原子核(プロトン)の核磁気共鳴を利用し、RF励起と傾斜磁場による位置エンコードで信号を収集して画像化する。プロトン密度やT1・T2緩和特性の差により軟部組織コントラストに優れ、血流はTOFや位相コントラスト法などで評価可能で、ボリューム撮像から3次元再構成も行える。一方で撮像時間が相対的に長く、体動・呼吸・拍動などの運動に起因するアーチファクトを受けやすいため、心臓など動きのある臓器は同期(ECGゲーティング)、呼吸停止、cine撮像等の工夫が必要で、一般論として「適している」とは言い難い。したがって誤っているのは「動きのある臓器の撮影に適している」。
選択肢別解説
正しい。MRI信号の主な起源は生体内の水分子に含まれる水素原子核(プロトン)であり、その空間分布や緩和特性の違いを画像化する(プロトン密度像、T1/T2強調像など)。
正しい。MRIはT1・T2緩和の差を強調でき、水分含有量の差が反映されるため、脳・脊髄・筋・靱帯・腫瘍など軟部組織のコントラスト分解能に優れる。
正しい。MRA(TOF、位相コントラスト)や4D Flow MRIなどにより血流の有無・方向・速度分布の測定が可能で、造影剤を用いない手法も広く用いられる。
正しい。傾斜磁場で位置をエンコードし、薄スライスのボリューム撮像や等方ボクセル収集からの3D再構成により臓器の3次元構造を画像化できる。
誤り。MRIは一般に撮像時間が長く運動アーチファクトの影響を受けやすいため、心臓など動きのある臓器の撮影には不利である。ECG同期、呼吸同期、cineや高速シーケンス等で克服可能だが、原理的に「適している」とは言えない。
解説を表示するにはログインが必要です。ログインすると無料枠(1日5問)をご利用いただけます。
無料プランでは解説を1日5問まで表示できます。解説を表示すると残り回数が消費されます。
今日: 回 | 残り 回
本日の無料枠を使い切りました。プレミアム登録で無制限にご利用いただけます。
解説
超音波診断装置は電離放射線ではなく音波を用いるため放射線被曝がなく、一般に非侵襲的で繰り返し使用しやすい。一方で超音波は骨・空気で強く反射・減衰するため、全身を一括に撮る「全身撮影」には適さない。心エコーではMモードや2Dで左室自由壁や心室中隔の壁厚を収縮期・拡張期に定量できる。さらに血管内超音波(IVUS)ではカテーテル先端のプローブにより血管内腔から断層像を取得可能である。電子走査により高フレームレートでリアルタイム表示が可能である。以上より、正しいのは3・4・5である。
選択肢別解説
誤り。超音波は電離放射線を用いないため放射線被曝はなく、診断用出力では一般に非侵襲的に実施できる。被曝に伴う侵襲性という表現はX線/CT/核医学に当てはまるが、超音波には当てはまらない。
誤り。超音波は骨や空気(肺・消化管内ガス)で強く反射・減衰するため透過性が不均一で、全身を一括で描出する「全身撮影」には不向きである。目的部位ごとに探触子を当てて限られた範囲を観察する。
正しい。心エコー(経胸壁や経食道)ではMモードや2D画像から左室壁や心室中隔の壁厚を測定でき、拡張期・収縮期の壁厚評価が可能である。
正しい。血管内超音波(IVUS)はカテーテル先端の小型振動子で血管内腔から超音波を送受信し、血管壁の断層像を取得できるため、血管内の画像が得られる。
正しい。電子走査・ビームフォーミングにより高フレームレートで画像更新が行われ、実時間(リアルタイム)の撮影・表示が可能である。
解説を表示するにはログインが必要です。ログインすると無料枠(1日5問)をご利用いただけます。
無料プランでは解説を1日5問まで表示できます。解説を表示すると残り回数が消費されます。
今日: 回 | 残り 回
本日の無料枠を使い切りました。プレミアム登録で無制限にご利用いただけます。
解説
誤っているのは「装置から発生する音はMRIよりも大きい。」である。CTはガントリ回転や寝台移動の機械音はあるが、MRIのように傾斜磁場コイルの急速スイッチングによる大きな騒音は発生しにくく、一般に騒音はMRIの方が大きい。一方、CTではヨード系造影剤を用いたCT angiographyなどで血管の描出を強調でき、手術ナビゲーション(画像誘導手術)の基礎データとしても広く用いられる。撮影中の体動はモーションアーチファクトを生じ像が不鮮明になるため、胸腹部では息止め等が求められる。また、CTは電離放射線(X線)を用いるため、遮蔽・時間・距離の原則など放射線防護対策が必要である。
選択肢別解説
誤り。CT装置の作動音はあるが、一般にMRIの方が騒音は大きい。MRIでは傾斜磁場コイルが強い静磁場中で急速に励磁・切替される際の力によってコイルが微小振動し、大きな騒音を生じる。したがって「CTの方が大きい」とする本記述は不適切。
正しい。CTではヨード系造影剤を静注して血管や腫瘍の強調を行い、CT angiographyなどで血管走行や狭窄・閉塞の評価に用いられる。
正しい。CT画像は術前計画や手術ナビゲーション(画像誘導手術)に広く利用され、特に骨構造の位置同定や座標把握に有用である。必要に応じて術中CTが用いられることもある。
正しい。撮影中の体動はモーションアーチファクトを生じ、像が不鮮明になる。胸腹部では息止め指示などで体動を抑制して画質劣化を防ぐ。
正しい。CTはX線を使用するため、検査に関わるスタッフや同席者には鉛防護具の着用、線量低減(時間・距離・遮蔽)の放射線防護対策が必要である。
解説を表示するにはログインが必要です。ログインすると無料枠(1日5問)をご利用いただけます。
無料プランでは解説を1日5問まで表示できます。解説を表示すると残り回数が消費されます。
今日: 回 | 残り 回
本日の無料枠を使い切りました。プレミアム登録で無制限にご利用いただけます。