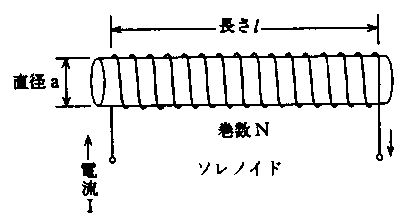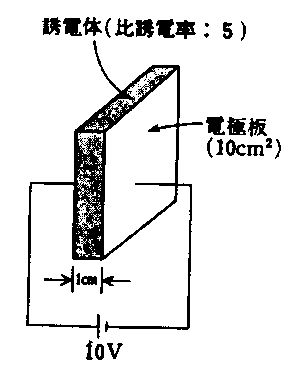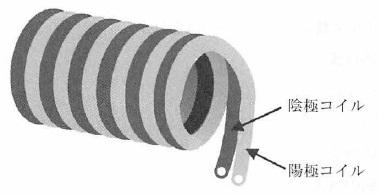第8回国試午後5問の類似問題
国試第27回午後:第52問
1次巻線数肌、2次巻線数心の理想変圧器について正しいのはどれか。
a:交流電圧の変換に用いられる。
b:コイルに発生する誘導起電力を利用している。
c:1次と2次のインピーダンス比は巻数の二乗に反比例する。
d:1次電圧をV1、2次電圧をV2としたときV1/ V2 = n1/ n2 が成立する。
e:1次電流をi1、2次電流をi2としたときi2/ i1 = n1/ n2 が成立する。
1. a b c 2. a b e 3. a d e 4. b c d 5. c d e
国試第15回午後:第4問
1次巻線数N1、2次巻線数N2のトランスについて正しいのはどれか。
a:直流の電圧・電流の変換に用いられる。
b:電磁誘導現象を利用している。
c:インピーダンス変換に用いられる。
d:1次電圧をE1、2次電圧をE2としたとき$\frac{N_1}{N_2}=\frac{E_1}{E_2}$が成立する。
e:1次電流をI1、2次電流をI2としたとき$\frac{N_1}{N_2}=\frac{I_1}{I_2}$が成立する。
1. a b c 2. a b e 3. a d e 4. b c d 5. c d e