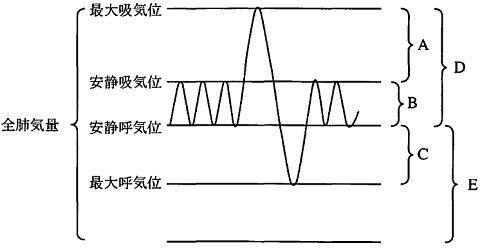臨床工学技士問題表示
臨床工学技士国家試験
中分類
人体の構造及び機能
20問表示中
広告
83
臨床工学技士国家試験 -
第34回 午前
正答率:55%
正しいのはどれか。
a
動脈血圧のピーク値は体の部位によって異なる。
b
血管内径が小さくなると血管抵抗は上昇する。
c
血管に石灰化が起こると脈波伝搬速度は増加する。
d
大動脈では動圧の値と静圧の値はほぼ等しい。
e
動脈径が大きいほど脈波伝搬速度は増加する。
組み合わせ:
1. a b c
2. a b e
3. a d e
4. b c d
5. c d e
広告
5
臨床工学技士国家試験 -
第34回 午後
重要度:低
正答率:81%
細胞について正しいのはどれか。
a
細胞膜は主にフィブリンで構成される。
b
ゴルジ装置は ATP 産生を担う。
c
リボゾームはタンパク合成を担う。
d
リソソームは物質を分解処理する。
e
核は DNA を含む。
組み合わせ:
1. a b c
2. a b e
3. a d e
4. b c d
5. c d e
7
臨床工学技士国家試験 -
第34回 午後
重要度:低
正答率:67%
心臓の刺激伝導系と心電図について正しいのはどれか。
a
洞房結節と房室結節の間にヒス束がある。
b
プルキンエ線維は主に心室筋の収縮を担う。
c
P 波は心房筋の興奮を表す。
d
心房細動では P 波を認めない。
e
QRS 波とともに拡張期が始まる。
組み合わせ:
1. a b c
2. a b e
3. a d e
4. b c d
5. c d e
広告
広告
6
第二種ME技術認定試験 -
第33回 午前
ニューロンA、B、C、Dが図のようにシナプス結合しているとき、ニューロンDの活動性が亢進する条件はどれか。ただし、A、Cは抑制性ニューロン、Bは興奮性ニューロンとして機能し、信号伝達能力は比率として、A:B:C=1:1:1とする。
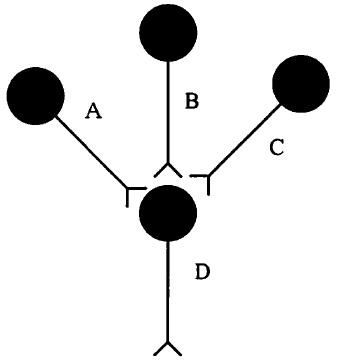
1
Aの活動性亢進、Bの活動性亢進、Cの活動性亢進
2
Aの活動性亢進、Bの活動性亢進、Cの活動性低下
3
Aの活動性亢進、Bの活動性低下、Cの活動性亢進
4
Aの活動性低下、Bの活動性亢進、Cの活動性亢進
5
Aの活動性低下、Bの活動性亢進、Cの活動性低下
広告