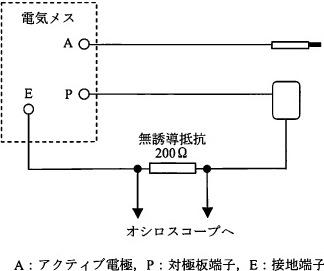第16回国試午前73問の類似問題
ME2第29回午前:第50問
次の組合せで誤っているのはどれか。
1:電気メスの搬送周波数 -- 400kHz
2:マイクロ波メスの周波数 -- 300MHz
3:低温常圧型冷凍手術装置の冷却最低温度 -- -196℃
4:超音波吸引手術装置の先端チップ振動振幅 -- 150μm
5:CO2レーザメスの発振波長 -- 10.6μm
国試第15回午前:第83問
病院電気設備の安全基準について正しいのはどれか。
a:等電位接地はミクロショック防止のための設備である。
b:医用接地センターには10Ω以下の接地抵抗を持つ接地極を設ける。
c:生命維持管理装置用の非常電源として一般非常電源を用いる。
d:非接地配線方式はミクロショック防止に役立つ。
e:集中治療室には必要に応じて瞬時特別非常電源を設ける。
1. a b c 2. a b e 3. a d e 4. b c d 5. c d e
ME2第31回午後:第16問
発熱を主作用としない手術装置はどれか。
1:電気メス
2:CO2レーザメス
3:マイクロ波メス
4:赤外線コアギュレータ
5:超音波メス
国試第2回午後:第74問
JIS-T-1001「医用電気機器の安全通則」、JIS-T-1002「病院電気設備の安全基準」について正しいのはどれか。
a:形別装着部の分類は保護手段のみに基づいている。
b:非常電源はその電源供給継続時間のみにより一般、特別、瞬時特別に分類されている。
c:CF形機器では正常状態での患者洩れ電流を10μA以下に抑えている。
d:等電位化接地では患者の接触可能なすべての金属表面の電位差を10mV以下にしている。
e:接地ピン付きの3Pプラグのついた機器はすべてクラスI機器である。
1. a b 2. a e 3. b c 4. c d 5. d e
国試第16回午前:第76問
臨床工学技士による医用機器管理業務で適切でないのはどれか。
1:電気メスの購入に当たって性能に関する医師の要望をメーカに伝えた。
2:新規購入機器の操作法を手術室で指導した。
3:心電図モニタの患者リード線が断線したので修理した。
4:脳波検査室で脳波計を使用中に接地漏れ電流を測定した。
5:患者から摘出した植込み式ペースメーカの出力電圧を測定した。
国試第9回午前:第65問
医用治療機器について正しいのはどれか。
a:治療余裕度(致死限界と治療効果が生じるエネルギー密度の差)を最小にする。
b:治療効果比(主作間/副作用)を最大にする。
c:皮膚を通して生体内に伝達される物理的エネルギーの密度は100mW/cm2以下とする。
d:状態によらず一定出カで使用する。
e:治療に用いるすべての物理的エネルギーの安全限界は同一である。
1. a b 2. a e 3. b c 4. c d 5. d e
国試第6回午後:第76問
正しい組み合わせはどれか。
a:電気メスの高周波分流 ----------------- 熱的安全性
b:膜型人工肺の材用劣化 ---------------- 機械的安全性
c:医用ガスの誤用 ---------------------- 化学的安全性
d:透析回路への気泡の混入 ―――――--- 生物学的安全性
e:レーザ光の目的物以外への照射 ------- 工学的安全性
1. a b c 2. a b e 3. a d e 4. b c d 5. c d e