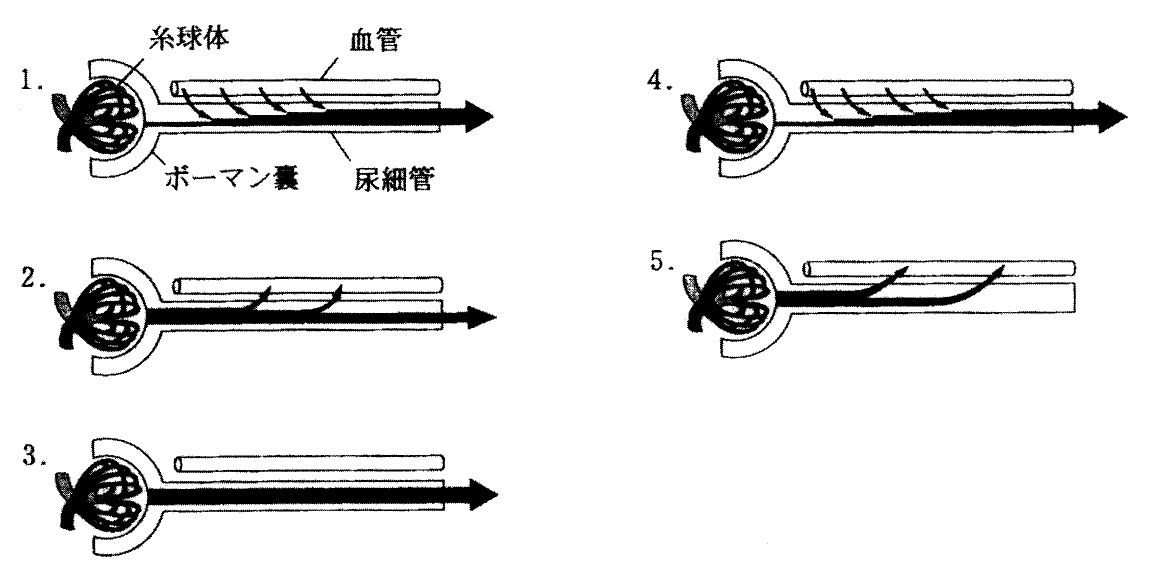第14回国試午前11問の類似問題
国試第7回午前:第22問
腎・尿路系について誤っているのはどれか。
a:尿管膀胱移行部が正常でも膀胱内尿は尿管へ逆流する。
b:腎細胞癌(Grawitz tumor)は小児に多い。
c:重複尿管は先天性異常として認められる。
d:急性腎孟腎炎は上行性感染によることが多い。
e:膀胱炎は男性より女性に起こりやすい。
1. a b 2. a e 3. b c 4. c d 5. d e
国試第19回午前:第29問
糸球体機能検査はどれか。(腎臓・泌尿器学)
1:尿中カリウム排泄量
2:濃縮試験
3:クレアチニンクリアランス
4:尿pH
5:尿浸透圧