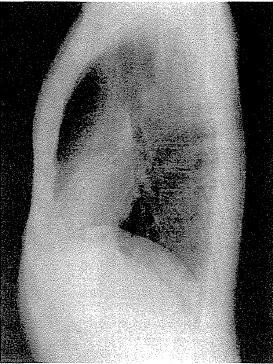臨床工学技士問題表示
臨床工学技士国家試験
検索元問題
第27回 午前 第32問
20件の類似問題
ラジオアイソトープ(RI)を用いた医用画像について誤っているのはどれか。...
広告
6
第二種ME技術認定試験 -
第36回 午後
類似度 55.0%
科目:
PETについて正しいのはどれか。
1
ポジトロン放出核は海水から抽出する。
2
患者に高電圧を印加する。
3
患者に陽電子を照射する。
4
患者体内で核融合現象が生じる。
5
検出器に入射した光子を測定する。
30
臨床工学技士国家試験 -
第29回 午後
重要度:標準
正答率:93%
類似度 54.9%
超音波診断装置について正しいのはどれか。
a
被曝に伴う侵襲性がある。
b
全身撮影が可能である。
c
心室の壁厚を測定できる。
d
血管内の画像が得られる。
e
実時間の撮影が可能である。
組み合わせ:
1. a b c
2. a b e
3. a d e
4. b c d
5. c d e
広告
48
第二種ME技術認定試験 -
第37回 午前
類似度 54.4%
科目:
18FDG PET検査について正しいのはどれか。
1
18Fの半減期は6時間である。
2
18FDGはグルコース代謝の活発な細胞に特異的に集まる。
3
18Fは原子炉で生成する。
4
18Fから放出されるβ線を検出する。
5
放射線遮へい壁は不要である。
32
臨床工学技士国家試験 -
第38回 午前
類似度 54.1%
X線による撮像について正しいのはどれか。
a
神経の走行方向の観察に適している。
b
臓器の動きの撮影が可能である。
c
組織を透過したX線を画像化する。
d
造影剤は空間分解能の改善のために使用する。
e
得られる画像の空間分解能は5 mm程度である。
組み合わせ:
1. a b
2. a e
3. b c
4. c d
5. d e
広告
30
臨床工学技士国家試験 -
第33回 午後
重要度:重要
正答率:79%
類似度 53.9%
核磁気共鳴画像法について正しいのはどれか。
a
放射線被曝はない。
b
磁力線の透過性を画像化している。
c
臓器の画像再構成は一断面に限られる。
d
空間分解能は 5 mm 程度である。
e
撮影手法として T2 強調がある。
組み合わせ:
1. a b
2. a e
3. b c
4. c d
5. d e
87
臨床工学技士国家試験 -
第2回 午前
正答率:62%
類似度 53.9%
正しいのはどれか。
a
超音波診断は原子の種類により異なる反射波を利用する。
b
エックス線の吸収は原子の密度で定まり、その種類には依存しない。
c
生体内で可視光線を主に吸収するのは脂肪である。
d
RIは代謝の機能や特定の臓器の形態を知るのに利用される。
e
電磁波の吸収は筋肉層の方が脂肪層より大きい。
組み合わせ:
1. a b
2. a e
3. b c
4. c d
5. d e
85
臨床工学技士国家試験 -
第7回 午前
正答率:56%
類似度 53.7%
サーモグラフィについて正しいのはどれか。
1
外部から赤外線を照射してその反射率を画像化する。
2
検出器には超伝導を利用したSQUIDが使われる。
3
着衣のままで検査ができる。
4
レイノー病による手足の血流障害の診断に利用されている。
5
腎臓などの深部臓器の診断に有用である。
54
第二種ME技術認定試験 -
第40回 午前
類似度 53.5%
科目:
核医学(nuclear medicine)検査用機器はどれか。
1
PET装置
2
MRI装置
3
DNAシーケンサ
4
蛍光顕微鏡
5
フローサイトメータ
広告
52
第二種ME技術認定試験 -
第34回 午前
類似度 53.4%
体表面の物理量を計測するのはどれか。
1
サーモグラフ
2
X線CT
3
MRI
4
超音波診断装置
5
PET
31
臨床工学技士国家試験 -
第30回 午後
重要度:標準
正答率:65%
類似度 53.2%
X 線CT 画像について正しいのはどれか。
a
臓器の3 次元構造が得られる。
b
画像再構成法として逆投影法がある。
c
血管の撮像が可能である。
d
X 線を双方向に照射する。
e
空間分解能は1程度である。
組み合わせ:
1. a b c
2. a b e
3. a d e
4. b c d
5. c d e
広告