第34回午後第19問の類似問題
第42回午後:第18問
腎臓で正しいのはどれか。2つ選べ。 ア.糸球体は髄質にある。イ.近位尿細管は腎盂にある。ウ.尿管は皮質と連結する。エ.輸入細動脈は糸球体と連結する。オ.遠位尿細管はヘンレ係蹄と連結する。
1: ア
2: イ
3: ウ
4: エ
5: オ
- 答え:4 ・5
- 科目:生理学(消化・吸収・排泄系)
- 重要度:プレミアム特典
- 類似問題を見る
- この問題について報告する
第39回午後:第18問
腎臓についての正しいのはどれか。
1: 糸球体は髄質にある。
2: 糸球体は血液をろ過する。
3: 遠位尿細管は腎盂にある。
4: 尿細管はブドウ糖を排出する。
5: 尿管は皮質と連結する。
- 答え:2
- 科目:解剖学(その他)
- 重要度:プレミアム特典
- 類似問題を見る
- この問題について報告する
第36回午後:第9問
腎臓について正しいのはどれか。
1: 遠位尿細管は腎盂にある。
2: 尿管は皮質と連結する。
3: 糸球体は髄質にある。
4: 糸球体は血液をろ過する。
5: 尿細管はブドウ糖を排出する。
- 答え:4
- 科目:解剖学(その他)
- 重要度:プレミアム特典
- 類似問題を見る
- この問題について報告する
第36回午後:第4問
運動単位に含まれないのはどれか。
1: 錐体路
2: 前角細胞
3: 末梢神経線維
4: 神経筋接合部
5: 筋線維
- 答え:1
- 科目:解剖学(筋・骨格・神経系)
- 重要度:プレミアム特典
- 類似問題を見る
- この問題について報告する
第49回午前:第56問
大脳基底核に含まれないのはどれか。
1: 被殻
2: 網様体
3: 淡蒼球
4: 尾状核
5: 扁桃体
- 答え:2
- 科目:解剖学(筋・骨格・神経系)
- 重要度:プレミアム特典
- 類似問題を見る
- この問題について報告する
第54回午前:第57問
腎臓で誤っているのはどれか。
1: 遠位尿細管は集合管につながる。
2: 尿細管は腎小体の尿管極に始まる。
3: Henle係蹄は小葉間静脈につながる。
4: Bowman囊は糸球体を包んでいる。
5: 輸入細動脈は糸球体につながる。
- 答え:3
- 解説:腎臓は尿の生成と排泄を担当する臓器であり、その構造は複雑です。腎臓の主要な構造は腎小体と尿細管であり、それらが連携して尿の生成と濃縮を行います。
- 遠位尿細管は集合管につながるので、この選択肢は正しいです。遠位尿細管は尿の濃縮や酸素濃度の調整を行い、最終的に集合管に尿を送ります。
- 尿細管は腎小体の尿管極に始まるので、この選択肢は正しいです。尿管極は腎小体から尿細管への尿の移動を開始する部分であり、尿の生成が始まります。
- Henle係蹄は小葉間静脈につながるのではなく、遠位尿細管につながるため、この選択肢は誤りです。Henle係蹄は尿の濃縮を行う部分であり、遠位尿細管に尿を送ります。
- Bowman囊は糸球体を包んでいるので、この選択肢は正しいです。Bowman囊は糸球体からの尿の取り込みを行い、尿細管へ送る役割を果たします。
- 輸入細動脈は糸球体につながるので、この選択肢は正しいです。輸入細動脈は糸球体に血液を供給し、尿の生成過程で濾過された血液成分を回収する役割を果たします。
- 科目:解剖学(その他)
- 重要度:プレミアム特典
- 類似問題を見る
- この問題について報告する
第34回午後:第25問
触受容器でないのはどれか。
1: ゴルジ終末
2: パチニ小体
3: メルケル細胞
4: ルフィニー小体
5: マイスネル小体
- 答え:1
- 科目:解剖学(その他)
- 重要度:プレミアム特典
- 類似問題を見る
- この問題について報告する
第42回午後:第36問
免疫系に関与しないのはどれか。
1: 骨髄
2: 扁桃
3: 胸腺
4: 脾臓
5: 膵臓
- 答え:5
- 科目:生理学(その他)
- 重要度:プレミアム特典
- 類似問題を見る
- この問題について報告する
第37回午後:第1問
月状骨と関節を構成しないのはどれか。
1: 橈骨
2: 三角骨
3: 小菱形骨
4: 有頭骨
5: 有鈎骨
- 答え:3
- 科目:解剖学(筋・骨格・神経系)
- 重要度:プレミアム特典
- 類似問題を見る
- この問題について報告する
第34回午後:第49問
正常細胞の基本構造で細胞質に含まれないのはどれか。
1: 細胞膜
2: 小胞体
3: 基底膜
4: ゴルジ装置
5: ミトコンドリア
- 答え:3
- 科目:生理学(その他)
- 重要度:プレミアム特典
- 類似問題を見る
- この問題について報告する
第50回午後:第52問
月状骨と関節を構成しないのはどれか。
1: 橈骨
2: 三角骨
3: 有鉤骨
4: 有頭骨
5: 小菱形骨
- 答え:5
- 科目:解剖学(筋・骨格・神経系)
- 重要度:プレミアム特典
- 類似問題を見る
- この問題について報告する
第46回午前:第77問
骨格筋の病理組織標本を示す。矢印で示すのはどれか。
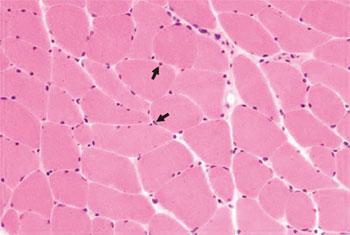
1: 核
2: 赤血球
3: リンパ球
4: 末梢神経
5: 毛細血管
- 答え:1
- 科目:臨床医学総論(病理学)
- 重要度:プレミアム特典
- 類似問題を見る
- この問題について報告する
第55回午前:第67問
腎臓の排尿機構で正しいのはどれか。
1: Bowman囊は集合管に接続する。
2: 近位尿細管ではNa+が再吸収される。
3: ネフロンは糸球体と近位尿細管から構成される。
4: 糸球体ではアルブミンは水よりも濾過されやすい。
5: 糸球体濾過量は健常成人では1日に1~1.5 Lである。
- 答え:2
- 解説:腎臓の排尿機構に関する問題です。ネフロンは腎臓の基本単位であり、糸球体と尿細管から構成されます。糸球体では水や小分子が濾過され、尿細管では再吸収や分泌が行われます。
- Bowman囊は糸球体を包む構造であり、集合管には接続していません。集合管には複数のネフロンから来る遠位尿細管が合流します。
- 正解です。近位尿細管ではNa+が再吸収されるほか、アミノ酸やK+、Cl-などのイオンや水分、グルコースなども再吸収されます。
- ネフロンは腎臓の構造的、機能的単位で、1個の腎小体(糸球体とBowman嚢)と、それに続く1本の尿細管からなる。近位尿細管だけではなく、遠位尿細管も含まれます。
- 糸球体では水や小分子が濾過されやすいですが、アルブミンをはじめとする蛋白質はほとんど通さないため、アルブミンは水よりも濾過されにくいです。
- 糸球体濾過量(原尿)は血漿成分が糸球体からBowman嚢へと濾過された液体の量で、160 L/日程度です。1~1.5 L/日であるのは、健常成人の尿量です。
- 科目:生理学(消化・吸収・排泄系)
- 重要度:プレミアム特典
- 類似問題を見る
- この問題について報告する
第47回午後:第54問
大脳辺縁系に含まれないのはどれか。
1: 海馬
2: 内包
3: 帯状回
4: 乳頭体
5: 扁桃体
- 答え:2
- 科目:解剖学(筋・骨格・神経系)
- 重要度:プレミアム特典
- 類似問題を見る
- この問題について報告する
第53回午後:第57問
後腹膜腔に存在しないのはどれか。
1: 横行結腸
2: 腎臓
3: 十二指腸
4: 膵臓
5: 副腎
- 答え:1
- 解説:後腹膜腔に存在する臓器は、十二指腸、膵臓、腎臓、副腎、腹大動脈、下大静脈などであり、横行結腸は後腹膜腔に存在しない。
- 横行結腸はほとんど全表面が腹膜臓側葉で包まれ、間膜によって体壁につながれているため、後腹膜腔には存在しない。
- 腎臓は腹膜後器官であり、後腹壁に癒着し、腹膜の壁側葉の後ろに隠れるため、後腹膜腔に存在する。
- 十二指腸は腹膜後器官であり、全長にわたって後腹壁に癒着し、空腸や回腸のように腸間膜をもたないため、後腹膜腔に存在する。
- 膵臓は腹膜後器官であり、消化酵素を分泌するため、後腹膜腔に存在する。
- 副腎は腎臓の上端に位置する腹膜後器官であり、後腹膜に癒着しているため、後腹膜腔に存在する。
- 科目:解剖学(その他)
- 重要度:プレミアム特典
- 類似問題を見る
- この問題について報告する
第35回午後:第25問
感覚受容器でないのはどれか。
1: 自由神経終末
2: マイスネル小体
3: パチニ小体
4: 筋紡錘
5: 上皮小体
- 答え:5
- 科目:生理学(筋・感覚・神経系)
- 重要度:プレミアム特典
- 類似問題を見る
- この問題について報告する
第47回午後:第55問
線条体を構成するのはどれか。2つ選べ。
1: 前障
2: 被殻
3: 淡蒼球
4: 尾状核
5: 下垂体
- 答え:2 ・4
- 科目:解剖学(筋・骨格・神経系)
- 重要度:プレミアム特典
- 類似問題を見る
- この問題について報告する
第39回午後:第55問
免疫に関与する臓器、組織で誤っているのはどれか。
1: 胸腺
2: 脾臓
3: 膵臓
4: リンパ節
5: 骨髄
- 答え:3
- 科目:臨床医学総論(病理学)
- 重要度:プレミアム特典
- 類似問題を見る
- この問題について報告する
第40回午後:第9問
手の有頭骨と関節を構成しないのはどれか。
1: 舟状骨
2: 月状骨
3: 三角骨
4: 有鈎骨
5: 小菱形骨
- 答え:3
- 科目:解剖学(筋・骨格・神経系)
- 重要度:プレミアム特典
- 類似問題を見る
- この問題について報告する
第34回午後:第17問
小腸で誤っているのはどれか。
1: 大十二指腸乳頭は総胆管と膵管の開口部である。
2: 空腸と回腸は腸間膜で固定されている。
3: 小腸の壁の粘膜は半月ヒダである。
4: 筋層の間や粘膜下組織に神経叢がある。
5: 腸腺は絨毛の間に開口する。
- 答え:3
- 科目:解剖学(その他)
- 重要度:プレミアム特典
- 類似問題を見る
- この問題について報告する