第44回午前第8問の類似問題
第49回午前:第8問
45歳の女性。脊髄小脳変性症。ADLは自立している。独歩は可能で、会社へは電車で通勤している。最近ふらつきが多くなり、ときに転倒することがあるという。この患者に指導する内容として適切なのはどれか。
1: 背臥位でのストレッチ
2: 眼球運動による前庭刺激運動
3: 立位での下肢筋力増強
4: 外的リズムに合わせた平地歩行
5: T字杖を使用した応用歩行
- 答え:3
- 科目:神経筋・感覚障害
- 重要度:プレミアム特典
- 類似問題を見る
- この問題について報告する
第52回午前:第9問
78歳の女性。布団を持ち上げようとした際、背部から腹部への強い帯状痛を生じ、寝返りも困難となったため入院となった。入院時のエックス線写真(A)とMRI(B)を示す。この患者の病態はどれか。2つ選べ。
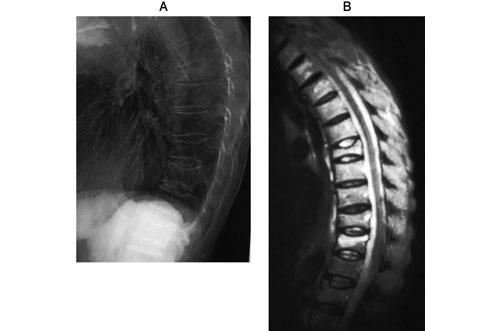
1: 骨粗鬆症
2: 脊椎分離症
3: 脊柱管狭窄症
4: 椎間板ヘルニア
5: 脊椎椎体圧迫骨折
- 答え:1 ・5
- 科目:高齢期障害
- 重要度:プレミアム特典
- 類似問題を見る
- この問題について報告する
第37回午前:第15問
62歳の女性。転倒により骨折した。固定期間中に非固定部の関節可動域訓練を行う際、適切でないのはどれか。
1: 固定後早期から開始する。
2: 可動域検査は上肢全体を行う。
3: 自動運動を原則とする。
4: 骨折部を固定して行う。
5: 骨折部の痛みがあっても続ける。
- 答え:5
- 科目:整形外科疾患
- 重要度:プレミアム特典
- 類似問題を見る
- この問題について報告する
第47回午後:第10問
68歳の男性。作業中に脚立の上から転落したため搬入された。強い腰痛を訴え、下肢の運動麻痺が認められる。脊椎MRIを示す。画像所見上、損傷部位として考えられるのはどれか。
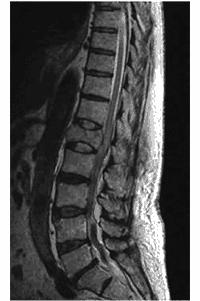
1: 第9胸椎
2: 第11胸椎
3: 第1腰椎
4: 第3腰椎
5: 第5腰椎
- 答え:3
- 科目:整形外科
- 重要度:プレミアム特典
- 類似問題を見る
- この問題について報告する
第56回午前:第15問
45歳の女性。3日前、自宅で荷物を持ち上げた際に、腰部と左下腿の後面から足背外側部にかけての強い痛みがあった。安静にしていたが、疼痛が軽快しないため受診し、腰椎椎間板ヘルニアと診断された。最も疑われる病変部位はどれか。
1: L1/2
2: L2/3
3: L3/4
4: L4/5
5: L5/S1
- 答え:5
- 科目:整形外科
- 重要度:プレミアム特典
- 類似問題を見る
- この問題について報告する
第53回午前:第11問
72歳の女性。関節リウマチ。SteinbrockerのステージⅢ、クラス3。訪問リハビリテーションを行っている。最近、新たに後頸部痛と歩きにくさとを訴えている。この患者への対応として適切でないのはどれか。
1: 転倒予防の指導を行う。
2: 頸部の可動域運動を行う。
3: 調理の際に椅子の使用を勧める。
4: 高い枕を用いないよう指導する。
5: 柔らかいマットレスを避けるよう指導する。
- 答え:2
- 解説:この問題では、関節リウマチの患者である72歳の女性が後頸部痛と歩きにくさを訴えており、適切でない対応を選ぶ必要があります。選択肢の中で、頸部の可動域運動を行うことが適切でない対応です。
- 転倒予防の指導を行うことは適切な対応です。歩きにくさを訴えている患者に対して、転倒のリスクを減らすための指導を行うことは重要です。
- 頸部の可動域運動を行うことは適切でない対応です。関節リウマチの患者に対して、無理な運動を行うことは症状の悪化を招く可能性があります。適切な運動やストレッチを専門家と相談して決定することが望ましいです。
- 調理の際に椅子の使用を勧めることは適切な対応です。立ち仕事が困難な患者に対して、椅子を使用して調理を行うことで、負担を軽減することができます。
- 高い枕を用いないよう指導することは適切な対応です。後頸部痛を訴える患者に対して、高い枕は頸部に負担をかける可能性があるため、適切な高さの枕を使用することが望ましいです。
- 柔らかいマットレスを避けるよう指導することは適切な対応です。柔らかいマットレスは、関節リウマチの患者にとって関節への負担が大きくなる可能性があるため、適切な硬さのマットレスを使用することが望ましいです。
- 科目:整形外科疾患
- 重要度:プレミアム特典
- 類似問題を見る
- この問題について報告する
第48回午後:第15問
46歳の女性。BMIは29である。両側の変形性股関節症で、股関節周囲の筋力低下と荷重時の股関節痛がある。理学療法で適切でないのはどれか。
1: 杖を用いた歩行訓練
2: 水中歩行による有酸素運動
3: 階段昇降による筋力増強訓練
4: 背臥位での下肢筋のストレッチ
5: 自転車エルゴメーターでの筋持久性訓練
- 答え:3
- 科目:整形外科
- 重要度:プレミアム特典
- 類似問題を見る
- この問題について報告する
第35回午前:第13問
70歳の女性。変形性股関節症に対する左人工股関節全置換(骨セメント使用)後3週経過。全荷重歩行可能。ADLの指導で適切でないのはどれか。
1: 手すりを用いた階段昇降
2: 洋式トイレ動作
3: シャワーチェアを用いた入浴
4: ソックスエイドを用いた靴下はき
5: あぐら座位
- 答え:5
- 科目:整形外科
- 重要度:プレミアム特典
- 類似問題を見る
- この問題について報告する
第44回午前:第25問
65歳の女性。脊髄損傷(第10胸髄節まで機能残存)。1階は店舗のため、階段に昇降機を設置することとした。普通型車椅子での生活に必要な家屋改造計画を図に示す。適切なのはどれか。
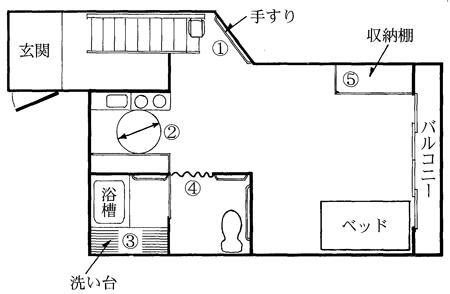
1: ①高さ100〜120 cm
2: ②直径90〜120 cm
3: ③高さ40〜45 cm
4: ④幅70〜80 cm
5: ⑤高さ80〜170 cm
- 答え:3
- 科目:脊髄損傷
- 重要度:プレミアム特典
- 類似問題を見る
- この問題について報告する
第35回午前:第16問
70歳の女性。慢性関節リウマチ。スタインブロッカーの機能障害分類クラスII。人工膝関節置換術後4週で歩行訓練中だが、同側の股関節深部の疼痛が強く訓練に支障をきたしている。疼痛軽減に適切な機器はどれか。
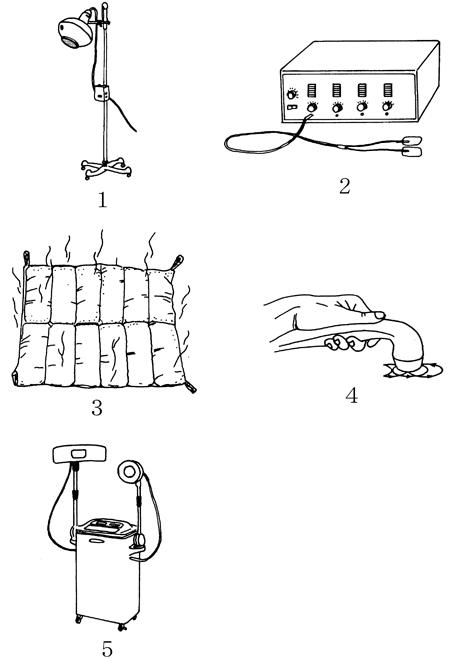
- 答え:4
- 科目:整形外科
- 重要度:プレミアム特典
- 類似問題を見る
- この問題について報告する
第36回午前:第22問
80歳の女性。右大腿骨頸部骨折を受傷。人工骨頭置換術後6か月経過。室内ADLは自立し、在宅療養となった。室内環境整備として適切でないのはどれか。
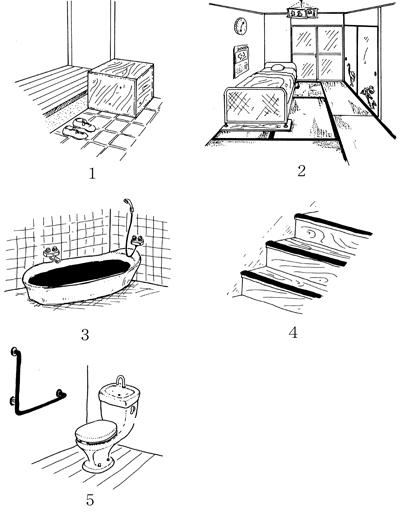
- 答え:3
- 科目:整形外科疾患
- 重要度:プレミアム特典
- 類似問題を見る
- この問題について報告する
第34回午前:第17問
50歳の女性。慢性関節リウマチでスタインブロッカーのステージIII、クラスII。発症後2年経過。両膝に外反変形、両外反母趾がある。両手関節の痛みは強く、腫脹もあるが、平行棒内での歩行は可能。理学療法で適切でないのはどれか。
1: 関節保護
2: 靴インサートの製作
3: 体幹伸筋群を中心とした筋力増強
4: 低い椅子からの立ち上がり訓練
5: 歩行器での歩行訓練
- 答え:4
- 科目:整形外科
- 重要度:プレミアム特典
- 類似問題を見る
- この問題について報告する
第37回午前:第9問
60 歳の女性。筋萎縮性側索硬化症。下肢の痙縮が強く、介助歩行でははさみ足の傾向がある。手指は鷲手変形を呈し、上肢近位部の筋力は2。最近、嗄声が進行している。この患者の作業療法で適切でないのはどれか。
1: ベッド上動作を容易にするため滑りやすい布をシーツとして使う。
2: 夜間家族を呼ぶため足スイッチコールを設置する。
3: PSBと万能カフを用いて食事をする。
4: ストロー付カップで補水をする。
5: 1スイッチ入力コミュニケーションエイドを使う。
- 答え:2
- 科目:神経筋疾患
- 重要度:プレミアム特典
- 類似問題を見る
- この問題について報告する
第55回午後:第15問
46歳の女性。BMIは29.0である。両側の変形性股関節症で、股関節周囲の筋力低下と荷重時の股関節痛がある。理学療法で適切でないのはどれか。
1: 杖を用いた歩行練習
2: 水中歩行による有酸素運動
3: 背臥位での下肢筋のストレッチ
4: 階段昇降による筋力増強トレーニング
5: 自転車エルゴメーターでの筋持久性トレーニング
- 答え:4
- 科目:整形外科
- 重要度:プレミアム特典
- 類似問題を見る
- この問題について報告する
第37回午前:第17問
83歳の男性。大腿骨頸部骨折で入院中。受傷前は屋内歩行が自立していた。自宅退院に向けた準備を開始した。適切でないのはどれか。
1: 便座の高さは30 cmにする。
2: 玄関スペースは車椅子用に130 cm×130 cm確保する。
3: 洗い場、浴槽内とも滑り止めを敷く。
4: 廊下に足元灯をつける。
5: ベッドに移動バーをつける。
- 答え:1
- 科目:整形外科疾患
- 重要度:プレミアム特典
- 類似問題を見る
- この問題について報告する
第52回午後:第16問
20歳の女性。1か月前に転倒し、疼痛は軽減したが膝関節の不安定感があり来院した。実施した検査を図に示す。矢印は力を加えた方向を示す。この検査で陽性となったとき、損傷されたのはどれか。

1: 外側側副靱帯
2: 後十字靱帯
3: 前十字靱帯
4: 腸脛靱帯
5: 内側側副靱帯
- 答え:2
- 科目:整形外科
- 重要度:プレミアム特典
- 類似問題を見る
- この問題について報告する
第41回午前:第14問
62歳の女性。転倒後、四肢麻痺が出現した。上肢の筋力は2、手指内在筋は0~1、下肢は4であった。受傷時の頸部CT(写真A、B)と頸部MRI(写真C)を示す。画像から得られる所見で正しいのはどれか。2つ選べ。ア.CTで第3~5頸椎間に後縦靱帯骨化がみられる。イ.CTで第4・5頸椎部に骨折がみられる。ウ.CTで第5・6頸椎間に脱臼がみられる。エ.MRIで脊髄の圧迫はみられない。オ.MRIで第5頸椎後方の脊髄に高輝度の変化がある。
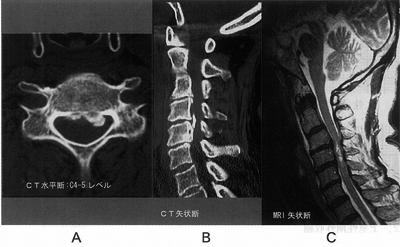
1: ア
2: イ
3: ウ
4: エ
5: オ
- 答え:1 ・5
- 科目:頸髄・脊髄損傷
- 重要度:プレミアム特典
- 類似問題を見る
- この問題について報告する
第52回午前:第10問
75歳の女性。自宅の浴室で転倒し右大腿骨頸部を骨折したため人工股関節置換術(後外側アプローチ)が施行された。担当医からは患側への全荷重が許可されている。この患者に対するADL指導で正しいのはどれか。
1: 割り座で靴下をはく。
2: 和式の畳生活を勧める。
3: 靴ひもを結ぶときはしゃがむ。
4: 椅子は座面の低いものを使用する。
5: 階段を下りるときは右足を先に下ろす。
- 答え:5
- 科目:整形外科疾患
- 重要度:プレミアム特典
- 類似問題を見る
- この問題について報告する
第56回午前:第7問
66歳の女性。左変形性股関節症。後方アプローチによる人工股関節全置換術を受けた。全荷重で術後リハビリテーション中である。退院後の生活指導として正しいのはどれか。
1: 和式トイレを使用する。
2: 椅子に座る際には足を組む。
3: 椅子は通常よりも低いものを選ぶ。
4: 床のものを拾うときには非術側を前に出す。
5: 端座位で靴にかかとを入れるときは外側から手を伸ばす。
- 答え:4
- 解説:後方アプローチによる人工股関節全置換術を受けた患者は、脱臼のリスクを考慮した生活指導が必要です。選択肢の中で正しいのは、床のものを拾うときに非術側を前に出すことです。
- 和式トイレはしゃがみ込む姿勢で使用するため、後方切開で筋肉が切開されている場合、脱臼の危険があります。したがって、和式トイレの使用は避けるべきです。
- 椅子に座る際に足を組むと、股関節が外旋・外転し、外旋筋が緩む。このとき、膝へ外力がかかると大腿骨の長軸に対して前方から後方への力が働き、脱臼しやすくなるため、足を組むことは避けるべきです。
- 低い椅子は股関節の屈曲が増大するため、後方侵入した部分への負荷がかかりやすくなります。そのため、通常よりも低い椅子を選ぶことは避けるべきです。
- 床のものを拾うときに非術側下肢を前に出すと、術側下肢は相対的に後方になり、股関節は伸展方向に働く。この姿勢は後方侵入手術で脱臼の危険が少ないため、作業姿勢として推奨できます。正しい選択肢です。
- 端座位で靴にかかとを入れるときに外側から手を伸ばすと、股関節屈曲が増大する。後方侵入手術を受けた患者には、長柄の靴ベラを使用させ、股関節屈曲姿勢を少なくする動作指導を行うことが適切です。この選択肢は間違いです。
- 科目:整形外科疾患
- 重要度:プレミアム特典
- 類似問題を見る
- この問題について報告する
第47回午後:第11問
68歳の男性。作業中に脚立の上から転落したため搬入された。強い腰痛を訴え、下肢の運動麻痺が認められる。脊椎MRIを示す。同日、脊椎固定術を行い、リハビリテーションを開始した。受傷3か月後のMMTによる筋力を表に示す。この時点で、下肢に使用する装具として適切なのはどれか。
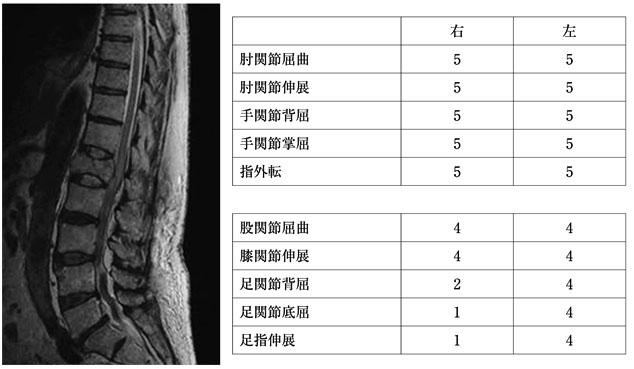
1: MSH-KAFO
2: 右KAFO
3: 右KO
4: 右AFO
5: 右足底装具
- 答え:4
- 科目:整形外科
- 重要度:プレミアム特典
- 類似問題を見る
- この問題について報告する