第57回午後第19問の類似問題
第41回午前:第13問
14歳の女子。痙直型四肢麻痺によって座位保持ができず座位保持装置を使用している。最近側弯が増強したため外来を受診した。脊椎エックス線単純正面像(別冊No. 3A)と骨盤エックス線単純正面像(別冊No. 3B)とを別に示す。座位姿勢を改善させる方法で適切でないのはどれか。
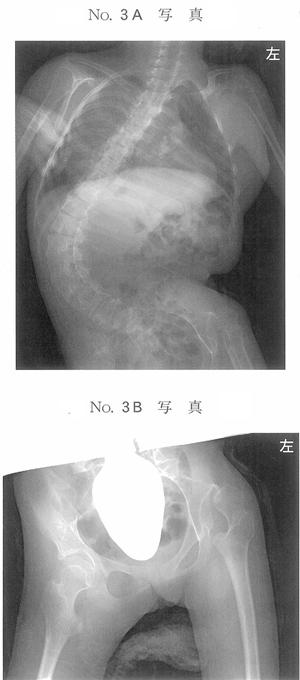
1: 軟性コルセットを使用する。
2: 右側臥位での体幹ストレッチを強化する。
3: ヘッドレストを付けて頭部を保持する。
4: 座面に傾斜をつけ左坐骨を挙上させる。
5: 座位保持装置に右体幹パッドを加える。
- 答え:4
- 科目:発達・小児疾患
- 重要度:プレミアム特典
- 類似問題を見る
- この問題について報告する
第44回午前:第23問
19歳の男性。オートバイ事故による頭部外傷で入院加療中。受傷後1か月。JCS(Japan coma scale)は1点。右上下肢はよく動かすが、左上下肢の筋緊張は亢進し、上肢屈曲位、下肢伸展位の姿勢をとることが多い。座位保持は可能であるが、体幹の動揺がみられる。この時期の理学療法で適切なのはどれか。2つ選べ。
1: 臥位での右上下肢のリラクセーション
2: 臥位での左上肢のFrenkel体操
3: 座位での左下肢筋の持続伸張
4: 立位でのバランス練習
5: 階段を降りる練習
- 答え:3 ・4
- 科目:脳血管障害
- 重要度:プレミアム特典
- 類似問題を見る
- この問題について報告する
第45回午後:第29問
脳卒中による片麻痺の上肢に対するCI療法(constraint-induced movement therapy)で正しいのはどれか。
1: 健側上肢を拘束する。
2: 慢性期例は適応とならない。
3: 理学療法士の近位監視下で行う。
4: 他動的関節可動域訓練を長時間行う方法である。
5: 患側手指がBrunnstrom 法ステージⅡで適応となる。
- 答え:1
- 科目:脳血管障害
- 重要度:プレミアム特典
- 類似問題を見る
- この問題について報告する
第46回午前:第11問
50歳の男性。多発性硬化症の再燃で入院加療中。四肢の痙性麻痺と運動失調とがみられる。立位保持は可能だが、Romberg徴候は陽性。神経症状が安定したため理学療法が開始された。この患者への理学療法で適切なのはどれか。
1: 筋のストレッチングを行う。
2: 早期に歩行補助具を作製する。
3: 痙縮に対して温熱療法を行う。
4: 運動失調に対して重錘を負荷する。
5: 筋力低下に対して1RMで筋力増強を行う。
- 答え:1
- 科目:神経筋・感覚障害
- 重要度:プレミアム特典
- 類似問題を見る
- この問題について報告する
第46回午後:第26問
脳卒中患者の症状と障害との組合せで誤っているのはどれか。
1: 知っている人なのに声を聞かないとわからない。 — 相貌失認
2: 閉眼と挺舌の動作を同時にできない。 — 運動維持困難
3: 移動時、左側の物によくぶつかる。 — 左半側空間無視
4: 指示による敬礼のまねができない。 — 観念失行
5: 上着の左右を間違えて袖を通す。 — 着衣失行
- 答え:4
- 科目:脳血管障害
- 重要度:プレミアム特典
- 類似問題を見る
- この問題について報告する
第54回午後:第8問
60歳の女性。視床出血発症後1か月。左片麻痺を認め、Brunnstrom法ステージは上肢Ⅱ、手指Ⅱ、下肢Ⅳである。左手指の発赤、腫脹および疼痛を認め、訓練に支障をきたしている。この患者に対する治療で正しいのはどれか。
1: 交代浴を行う。
2: 肩関節の安静を保つ。
3: 手指の可動域訓練は禁忌である。
4: 疼痛に対し手関節の固定装具を用いる。
5: 肩関節亜脱臼にはHippocrates法による整復を行う。
- 答え:1
- 解説:この患者は肩手症候群が疑われるため、交代浴が有効な治療法となる。肩手症候群に対する治療には、温熱療法、ステロイド投与、星状神経節ブロックなどが行われる。
- 交代浴は、温水と冷水に交互に治療部位を浸し、末梢循環の改善をはかる方法であり、肩手症候群に対して有効であることがある。
- 肩関節を安静にすると、関節可動域制限を生じ、かえって疼痛を認めることがある。麻痺側の肩関節は、亜脱臼に留意しながら愛護的に関節可動域訓練を行うべきである。
- 手指の可動域訓練は禁忌ではなく、愛護的に関節可動域訓練を実施することが適切である。
- 肩手症候群における疼痛は、手関節の固定装具を用いても改善しないことが多い。また、装具の当たり具合によっては、かえって疼痛を増悪させる可能性がある。
- Hippocrates法は、外傷性肩関節前方脱臼に対する徒手整復法で、上腕の牽引がメインである。肩関節亜脱臼に対しては、三角巾などを利用し、亜脱臼の拡大を防ぐなどの対応が行われる。
- 科目:脳血管疾患
- 重要度:プレミアム特典
- 類似問題を見る
- この問題について報告する
第50回午前:第7問
19歳の男性。オートバイ事故による頭部外傷で入院加療中。受傷後1か月。JCS(Japan coma scale)はⅠ-1。右上下肢は良く動かすが、左上下肢の筋緊張は亢進し、上肢屈曲位、下肢伸展位の姿勢をとることが多い。座位保持は可能であるが、体幹の動揺がみられる。この時期の理学療法で適切なのはどれか。2つ選べ。
1: 介助なしでのT字杖を用いた歩行練習
2: 臥位での左上肢のFrenkel体操
3: 座位での左下肢筋の持続伸張
4: 立位でのバランス練習
5: 階段を降りる練習
- 答え:3 ・4
- 科目:脳血管障害
- 重要度:プレミアム特典
- 類似問題を見る
- この問題について報告する
第54回午前:第17問
35歳の男性。交通事故による外傷性脳損傷で入院となった。受傷10日後から作業療法が開始された。運動麻痺や感覚障害はみられなかった。些細なことで怒りをあらわにし、作業療法中も大きな声をあげ、急に立ち上がってその場を去る、というような行動がしばしばみられた。患者はこの易怒性についてほとんど自覚しておらず病識はない。この患者の怒りへの対応で最も適切なのはどれか。
1: 原因について自己洞察を促す。
2: 感情をコントロールするよう指導する。
3: 周囲に与える影響を書き出してもらう。
4: よく観察し誘発されるパターンを把握する。
5: 脳損傷との関係について理解が得られるまで説明する。
- 答え:4
- 解説:この患者は脳外傷による易怒性や社会的行動障害があり、病識が欠如している。急性期であるため、ADLを安定させるために問題点と障害像を正確に把握することが重要である。患者の易怒性が現れるパターンを把握し、その上で対応策を検討するのが最も適切な対応である。
- 病識が欠如しているため、自己洞察を促すことは困難である。
- 病識が欠如しているため、感情のコントロールを指導しても効果は期待できない。患者の感情や行動のパターンを把握した後に、状況に応じて感情のコントロールに対する具体的な対応を行う。
- 易怒性に対して自覚がないため、現時点で周囲に与える影響を書き出すアプローチは困難である。
- 急性期は、患者の易怒性が現れるパターンを把握するために観察し、そのうえで対応策を検討するのが最も適切な対応である。
- 病識が欠如しており、易怒性に対する自覚もないため、現時点で問題となっている言動と脳損傷との関係を理解させることは困難である。
- 科目:高次脳機能障害
- 重要度:プレミアム特典
- 類似問題を見る
- この問題について報告する
第37回午前:第39問
70歳の独居女性。脳梗塞による右片麻痺。発症から3か月入院しリハビリテーションを受け、退院後2年経過。ブルンストローム法ステージは上肢・下肢ともにIII。屋内は短下肢装具、屋外は短下肢装具と杖とを使用して歩行。コミュニケーションは良好。在宅における指導で適切でないのはどれか。
1: 分離運動の獲得
2: 関節可動域の維持
3: 歩行能力の向上
4: 生活リズムの確立
5: 生活環境の整備
- 答え:1
- 科目:脳血管障害
- 重要度:プレミアム特典
- 類似問題を見る
- この問題について報告する
第57回午後:第8問
47歳の女性。多発性硬化症。30歳で発症し、寛解と増悪を繰り返した後、完全寛解していた。1週前に視力低下と小脳症状が出現し、入院となった。視神経と右小脳半球に脱髄を認める。過回内テストで図のような動きが観察された。この患者にみられる所見はどれか。
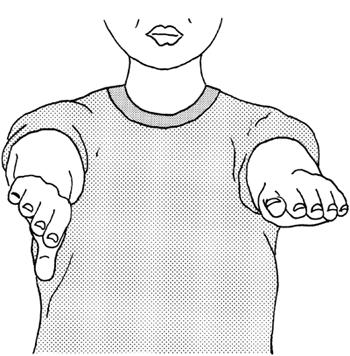
1: 振 戦
2: 運動分解
3: 測定異常
4: 協働収縮異常
5: 反復拮抗運動不能
- 答え:3
- 科目:神経筋・感覚障害
- 重要度:プレミアム特典
- 類似問題を見る
- この問題について報告する
第46回午後:第10問
78歳の女性。脳梗塞による右片麻痺。発症後5か月経過。20 cmの段差であれば、手すりを使用し2足1段で昇段し、後ろ向きに2足1段で降段することが可能となり、自宅に退院することとなった。自宅の玄関の様子を図に示す。この患者に適している家屋改造案はどれか。ただし、上りかまちは36 cmとする。
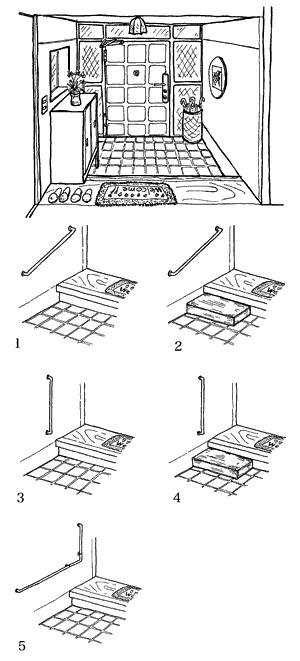
- 答え:2
- 科目:脳血管疾患
- 重要度:プレミアム特典
- 類似問題を見る
- この問題について報告する
第44回午前:第20問
79歳の女性。左視床出血1週後、理学療法を開始した。JCS(Japan coma scale)は2点、喚語困難がみられる。Brunnstrom法ステージは上肢V、手指IV、下肢V。上下肢の関節覚は重度の低下。座位保持は1分程度可能であるが易疲労性。立位保持は軽度の介助で短時間であれば可能である。この患者に対する理学療法で適切なのはどれか。
1: 立位での二重課題
2: 交互型歩行器での歩行運動
3: 麻痺側下肢に対する筋力増強
4: 座位での麻痺側手指の巧緻運動
5: 視覚代償による麻痺側下肢の感覚再教育
- 答え:3
- 科目:脳血管障害
- 重要度:プレミアム特典
- 類似問題を見る
- この問題について報告する
第34回午前:第24問
35歳の男性。痙性斜頸。随意的に頭部を正中位に保持できるが、すぐに右向き斜位になる。適切でない治療法はどれか。
1: 全身リラクセーション訓練
2: 頸部の可動域訓練
3: 左胸鎖乳突筋の筋力増強訓練
4: 緊張の高い筋群の筋電図バイオフィードバック訓練
5: 頸椎カラーの装着
- 答え:3
- 科目:整形外科
- 重要度:プレミアム特典
- 類似問題を見る
- この問題について報告する
第38回午前:第30問
40歳の男性。右橈骨神経麻痺で長橈側手根伸筋の徒手筋力テストは1(Trace)。EMGバイオフィードバック療法で誤っているのはどれか。
1: 治療法の原理を十分説明する。
2: 静かな室内で実施する。
3: 前腕肢位を中間位で行う。
4: 記録電極を前腕尺側に設置する。
5: 筋電波形の閾値設定は細かく調節する。
- 答え:4
- 科目:整形外科
- 重要度:プレミアム特典
- 類似問題を見る
- この問題について報告する
第48回午前:第12問
48歳の女性。2年前に多発性硬化症と診断された。これまで日常生活はおおむね自立していたが、1週前から視力の低下、両側下肢の脱力が増悪し入院となった。薬物治療後に理学療法が開始されたが、視力の低下、両側下肢の筋力低下および軽度のしびれが残存している。この時点の深部感覚障害の程度を適切に検査できるのはどれか。
1: 運動覚試験
2: Romberg試験
3: 内果での振動覚試験
4: 自動運動による再現試験
5: 非検査側を用いた模倣試験
- 答え:1
- 科目:神経筋・感覚障害
- 重要度:プレミアム特典
- 類似問題を見る
- この問題について報告する
第46回午前:第21問
片麻痺患者の車椅子移乗動作訓練に用いる課題と学習機序との組合せで正しいのはどれか。
1: 速度を変えた立ち上がり動作訓練 — プライミング効果
2: 片麻痺患者の移乗動作のビデオ視聴 — 転移
3: 肘台を想定した方向へのリーチ動作訓練— 内的焦点
4: 絵カードを用いた移乗動作順序の課題分析 — チャンク化
5: 骨盤を手すりへ誘導した非麻痺側荷重訓練 — 多様練習
- 答え:4
- 科目:脳血管疾患
- 重要度:プレミアム特典
- 類似問題を見る
- この問題について報告する
第46回午後:第12問
56歳の女性。3年前に右手の振戦で発症したParkinson病患者。数か月前から前傾姿勢を認めるようになった。事務員として仕事をしている。理学療法として優先されるのはどれか。
1: リズム音を用いた歩行訓練
2: 体幹筋のストレッチ訓練
3: 呼吸リハビリテーション
4: 下肢の筋力増強訓練
5: 環境整備
- 答え:2
- 科目:神経筋・感覚障害
- 重要度:プレミアム特典
- 類似問題を見る
- この問題について報告する
第34回午前:第21問
24歳の男性。会社員。オートバイによる自損事故で外傷性脳損傷となった。受傷後2か月経過。抗てんかん薬を内服中。意識は清明。易怒的である。左不全片麻痺と軽度失調症とを認める。歩行は短下肢技装具で自立。ADLはほぼ自立しているが、病室を間違えたり、他患者とけんかするなどの問題があった。社会復帰の準備を始めるにあたり誤っているのはどれか。
1: 病前の教育歴、社会歴を調べる。
2: 記憶、情動制御など高次脳機能を評価する。
3: IADL能力を把握する。
4: 現状での作業能力を検査する。
5: 会社の上司に復職準備を依頼する。
- 答え:5
- 科目:高次脳機能障害
- 重要度:プレミアム特典
- 類似問題を見る
- この問題について報告する
第36回午前:第5問
図は右片麻痺患者の椅子からの立ち上がりを介助しているところである。正しいのはどれか。

1: 患側の足はできるだけ健側の足に近い位置に置かせる方が安定した動作ができる。
2: 介助者は、患者の膝の前面よりも膝の外側に自分の膝をあてるべきである。
3: 座位で体重を前方に移していく段階では、頸を屈曲位にするよう指導するとよい。
4: 腰ベルトよりも患者の両腋下で体幹に手をかけて引き起こす方が介助が容易にできる。
5: 健側の手で介助者の肩につかまらせ、この腕の力を主に使って立ち上がるようにさせるとよい。
- 答え:3
- 科目:脳血管疾患
- 重要度:プレミアム特典
- 類似問題を見る
- この問題について報告する
第45回午前:第10問
42歳の女性。多発性硬化症による両側視神経炎を伴う四肢麻痺。筋力低下が進行し、移動には車椅子を使用している。Danielsらの徒手筋力テストでは上肢近位部3+、遠位部4。有痛性けいれんがある。この患者に対する作業療法で適切なのはどれか。2つ選べ。
1: 木工作業で本棚を作る。
2: 七宝焼きでピアスを作る。
3: ざる編みで籐カゴを作る。
4: 卓上編み機でマフラーを編む。
5: 小さな刻印で革に模様をつける。
- 答え:3 ・4
- 科目:神経筋疾患
- 重要度:プレミアム特典
- 類似問題を見る
- この問題について報告する